光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
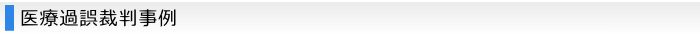
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
膝関節の人工関節置換術後,感染症を生じたことについて,医師に手術実施上の過失は認められなかったが,説明義務違反及び術後管理上の過失は認められ,後遺症が生じなかった高度の蓋然性は認められなかったが,相当程度の可能性が認められたケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第698号 損害賠償請求事件
平成18年3月17日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,入院管理,因果関係】
<事案の概要>
患者(大正15年生,男性)は,平成6年3月22日,右膝痛を訴えて被告病院(総合病院)整形外科を受診し,レントゲン検査の結果等から変形性膝関節症と診断された。担当医師は,患者に,関節注射等の保存的治療を行い,痛みが軽減されなければ人工関節置換術を勧めることを説明し,同年6月11日まで,ヒアルロン酸ナトリウムの関節注射を実施したが,右膝関節痛は軽快しなかった。担当医師は,同月20日,右膝関節の造影検査を実施し,膝蓋軟骨の消失や軟骨面の不整等が見られたが,骨切り術を要するほどの変形は認められなかったため,人工関節置換術を実施することとした。患者は,同年7月12日,被告病院に入院し,同月15日,人工関節置換術を受けた。
患者は,手術直後から,関節液貯留等の症状は見られなかったが,右膝痛,熱感や腫脹などが継続し,体温も微熱傾向にあった。患者は,同年8月12日には,右膝に著明な腫脹や熱感が見られ,血液検査で,CRP値や赤沈値が異常値を示していた。患者は,同年11月30日に被告病院を退院するまで,右膝の熱感,腫脹及び疼痛が継続し,微熱傾向も同年10月末まであり,血液検査で白血球数,CRP値及び赤沈値のいずれかが異常値を示す状況であった。患者は,退院後,被告病院に通院していたが,右膝関節痛や腫脹等の症状が軽快しなかったことから,平成7年9月4日,別の病院(大学病院)の整形外科を受診した。同年10月,同病院に入院して関節液の培養検査を受けたところ,ブドウ球菌が検出され,同病院で,同年11月14日,右膝の人工関節が抜去され,平成8年2月20日に再置換術が実施された。平成14年10月8日には,再置換術後の感染のため,人工関節が再度抜去され,創外固定された。
患者は,平成15年5月29日,右膝下に感覚障害(感覚鈍麻),右下肢全体の運動障害(固縮)及び右下肢の形態異常(短縮)があり,右下肢機能全廃により,屋内では歩行に両松葉杖を要し,屋外では車椅子の使用を要し,階段昇降は不能であるとの診断を受けたが,別の原因で死亡した。
患者の家族(妻及び子)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4412万5046円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 800万円) | ||||
| 争 点 | ①担当医師に,本件手術の危険性等についての説明義務違反があったか。 ②担当医師に,本件手術の際,手術室内の衛生管理を十分行わなかったか,手術時間を遷延させたため患者に感染を生じさせた過失があったか。 ③担当医師に,本件手術後の感染を早期に疑って持続洗浄等により炎症の沈静化を図らなかったため感染症を悪化させた過失があったか。 ④過失と患者の後遺症との間に因果関係の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①説明義務違反による慰謝料 | 100万円 | |||
| ②術後管理上の過失による後遺障害慰謝料 | 600万円 | ||||
| ③弁護士費用 | 100万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
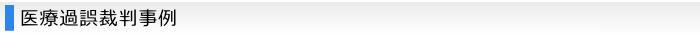
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
股関節化膿性関節炎について,担当医師の検査・治療義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第11004号 損害賠償請求事件
平成17年12月15日判決 控訴
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和16年生,女性)は,子宮癌に対する子宮及び両側卵巣全摘出術の予定で平成10年7月3日,被告病院(市立病院)に入院し,同月6日,マグコロールの投与を受けた。しかし,同月7日,患者に腹部膨満が強く見られ,手術を実施すると合併症の危険が高まること,又,患者が手術拒否の態度を示しており,患者が不穏状態となると創離開の可能性が高いため,同日予定していた手術は延期となった。翌8日,患者は,S状結腸軸捻転症と診断され,放置すれば生命にかかわるため急性腹症及び子宮癌に対する結腸並びに子宮及び両側卵巣の全摘出術が実施された。
患者は,被告病院にて入院加治療を続けていたが,同年9月2日,左股関節の脱臼骨折を生じ,平成11年1月,左股関節化膿性関節炎と診断された。同年3月8日,患者は別の病院に転院し,同年4月28日,障害名「体幹不自由,左下肢短縮及び右手関節機能障害」,総合所見「体幹の機能障害により座っていることができない,左下肢5cm以上の短縮,右手関節の著しい機能障害」との診断を受けた。患者は,同年5月31日,両下肢体幹機能障害により身体障害者等級1級の身体障害者手帳の交付を受けた。なお,患者は,平成13年9月3日に死亡した。
患者の遺族が被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3750万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計850万円) | ||||
| 争 点 | ①子宮等の摘出手術に対する同意の有無 ②腹部外科手術時における前処置用下剤であるマグコロールの投与が禁忌であったか。 ③術後,左股関節の化膿性関節炎と診断して,関節内への抗生物質投与や持続洗浄ドレナージを実施すべきであったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 800万円 | |||
| ②弁護士費用 | 50万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
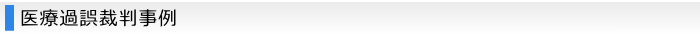
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
眼瞼下垂症に対する上眼瞼切除術について,顔貌が変化する程度の切除幅等について医師に説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成17年(ワ)第9975号 損害賠償請求事件
平成17年11月21日判決 控訴
【説明・問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和21年生,男性)は,加齢により両目の上眼瞼が垂れ下がり視界を遮るようになったとして,平成14年7月29日,被告病院(総合病院)形成外科を受診した。A医師は患者に対し美容整形を行う診療所で,自費診療の手術を受けるよう勧めたが,患者は拒否した。その後,患者を診察した同病院のB医師が,同年8月10日,被告病院において,上眼瞼除切除術(切除幅は顔貌を大きく変化させない最大限の4㎜)を実施した。その後,患者は,平成17年2月,韓国の大統領が上眼瞼の切除を受け視界が大幅に改善したことや手術により二重まぶたになったなどと報じた新聞記事を目にし,同月26日,被告病院及びB医師が院長を務める甲診療所(美容外科及び形成外科)に対し,上眼瞼切除術が不十分であるとして手術のやり直しを求めた。患者は,再手術の費用負担について被告病院と折り合えなかったため,今で再手術は行われていない。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計98万0710円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額15万0710円) | ||||
| 争 点 | 顔貌が変化する程度の切除についての説明義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①手術費用等 | 5万0710円 | |||
| ②慰謝料 | 10万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
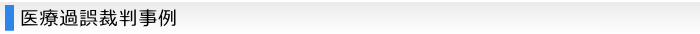
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
カイロプラクティックの施術により患者に頸椎椎間板ヘルニアを生じたことについて患者に対するリスク等の説明義務違反,及び施術時の圧迫の強さ等への配慮義務違反が認められたが,相当因果関係のある損害の範囲が限定されたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第7451号 損害賠償請求事件
平成17年10月28日判決 確定
【説明・問診義務,手技,適応,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和33年生,女性)は,被告施術者が開設していたカイロプラクター養成所で職員として勤務していたところ,平成7年11月19日ころ,養成所内において被告施術者により「ハンマーとノミ」の形態の器具を用いた施術(本件施術)を受けた。
患者は,施術後,首が痛くて下を向けなくなったため,平成7年11月29日,甲総合病院の整形外科を受診し,10日前から首に痛みがある旨訴えた。検査の結果,患者の頸椎に,C2・C3が先天的に癒合しているクリッペルファイル症候群が認められるとともに,C4/5及びC5/6の各椎間板が狭小化して骨棘が形成されていることが認められ,さらに正常であれば前弯している頸椎が,緩やかに後弯していることが判明した。患者は,同病院で何度か診察を受けたが,同年12月15日,乙病院(総合病院)の整形外科を受診した。患者は,症状として頸部痛のみを訴え,頸椎MRI検査の結果,C5/6の椎間板にヘルニアがあり,C6/7の椎間板には膨隆があると診断された。その後,患者は,乙病院を受診し,指のしびれ等を訴えたが,深部腱反射は,左右差がなく,正常であった。平成7年12月30日,患者は,丙病院(総合病院)の整形外科を受診した。他覚的な触覚,痛覚は正常範囲内であったが,患者は,左前腕から手の尺側及び左下腿のしびれ感を訴え,下肢腱反射の亢進が認められた。
患者は,甲,乙及び丙病院を受診していたが,平成8年1月21日,丙病院に入院した。入院時所見で,四肢の特に左側に強く軽度の知覚障害が認められ,深部腱反射の多くに亢進が認められたが,病的反射所見は陰性で,担当医は,患者のJOAスコア(日本整形外科学会による頸髄症治療成績判定基準)につき,11点と判定した。患者は,同年2月3日に丙病院を退院した。患者は,手術療法を希望して,大小様々の医療機関を受診する一方,丙病院の担当医に対しても外来受診の際その旨を訴えていた。同担当医が,患者に対し,手術療法には前方固定術と後方拡大術の2通りがあること,各々の長所短所について説明したところ,患者は,前方固定術を受けることを希望し,平成8年4月24日,同病院に再入院した。再入院時,患者は,時に頸部から左肩,胸部に痛みがあると訴え,スパーリングテストでは時に左上下肢に放散痛が認められ,各腱反射の亢進が認められたが,ジャクソンテストは陰性で,病的反射も,左のバビンスキー反射が擬陽性であったほか,陰性所見であった。JOAスコアは,発作時においては12点,通常時は15点と判定された。再入院の際,前方固定術の術式や,頸部脊柱管狭窄症が基礎にあるため,将来,頸部脊柱管拡大術(後方拡大術)を要する場合があることなどが記載された手術説明書が患者に交付され,医師から改めて前方固定術に関する説明がされた。
平成8年4月26日,患者は,丙病院の担当医師A(整形外科)の執刀により,C5/6椎間板ヘルニアに対する前方固定術(本件第1手術)を受けた。術後のX線写真では,移植骨の位置が良好であることが確認され,同手術において採取された,後縦靭帯を破り硬膜外に脱出していた組織を検査した結果,髄核と判明した。
患者は,本件第1手術後,頸部を固定され安静状態に置かれたが,術前以上の胸苦しさや息苦しさを訴え,27日未明,患者の希望により酸素投与が開始されたが,なお息苦しさを訴え続け,「麻酔したときに胸が何か痺れたようで。内科の先生に診てもらいたい。」などと訴えた。同日早朝には,本件第1手術により痛みがひどくなったと訴え,しびれがずっとある,耐えられないとも訴えた。その後も同様の訴えが続いたものの,同年5月1日のX線検査では状態良好で,同月3日,担当医師Bから患者に対し,脊椎からの神経症状で患者が訴えるようなチック様ピクツキは認められず,ヒステリー様症状であるとの説明がされ,患者は,いったん納得したような表情となったが,その後,看護師に繰り返し内科医による診察を求めた。同日午後,担当医師Aが患者を診察し,患者の握る・離す動作が円滑かつ速やかであることを確認し,患者に対し,上肢の不随意運動は,脊髄からの症状としては非定型的で,会話,質問の返答を聴いている際には生じない,神経の働きより精神的,心理的な側面が強いと考えていることを説明した。患者は,下腹部の圧迫感が残存していることや,椎間板造影が悪化の原因ではないかといった訴えをしたが,担当医師Aは,前者については,以前には自覚していなかったものを自覚するようになったのではないか,後者については,神経学的には悪化の原因とは思わなかったが,検査が途中で中止されたこともあり術式選択が不能となることに不安を募らせた結果ではないかと説明した。患者は,医師から説明を受けても同様の訴えを繰り返し,後方拡大術を希望するようになったが,丙病院では後方拡大術を直ちに行うことに消極的であったことから,患者は,丙病院に入院中,他院を受診するようになった。
平成8年5月29日,患者は,丁病院の担当医師C(整形外科)の診察を受けた。C医師は,腿反射(両上腕二頭筋,右膝蓋)の亢進を認めるとともに,病的反射であるバビンスキー反射とホフマン徴候がいずれも陽性で,腹部以下で痛覚の鈍麻があると認め,MRI写真上,C4/5レベルで脊髄の圧迫があり,C3/4からC6/7にかけて脊髄の前方が狭くなっていると認めた。担当医師Cは,患者に対し,今すぐ手術をする必要はなく,しばらく経過観察をするよう説明し,精神安定剤(ドグマチール)を処方した。患者の主訴については,心因性の疑いがあったが,担当医師Cは,心療内科医から,整形外科的に症状を説明することのできる圧迫があるなら手術適応がある旨の回答を得たことから,同年10月7日,同医師の執刀で,患者に対し,C1〜3の椎弓切除術及びC4〜7の後方拡大術(本件第2手術)を実施した。患者は,平成9年6月2日,C3/4及びC4/5で前方から圧迫があるとの所見が認められたためC3〜C5にかけての前方固定術を受け,術後の頸椎MRI検査でC4/5になお脊髄の軽度の圧迫が認められたことから,同年8月18日,前回手術と同様の前方固定術を受け,同年10月21日には,C3〜C5の2椎間前方固定術を受け,平成10年3月18日には同2椎間のプレート固定術を,平成12年5月10日にはC1硬膜拡大術を受けるなどし,その間多数の病院を受診した。平成16年5月11日以降,患者は,戊病院脳神経外科で,患者の症状が脳脊髄液減少症によるとの診断を受けた。
患者が,被告施術者に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7600万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額1476万4428円) | ||||
| 争 点 | ①本件施術が頸椎椎間板ヘルニアの原因か ②被告施術者は,施術に当たり圧迫の強さ等に配慮したか ③本件施術により生じた椎間板ヘルニアと患者の現在の症状との相当因果関係の有無 ④損害の範囲 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費 | 34万6207円 | |||
| ②入院雑費 | 7万6700円 | ||||
| ③装具・器具購入費 | 1万0000円 | ||||
| ④休業損害 | 121万8778円 | ||||
| ⑤後遺症逸失利益 | 1030万3851円 | ||||
| ⑥入通院慰謝料 | 140万0000円 | ||||
| ⑦後遺症慰謝料 | 340万0000円 | ||||
| ⑧弁護士費用 | 170万0000円 | ||||
| ⑨素因減額 | 20% | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
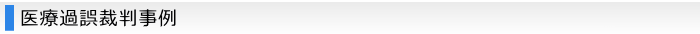
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
入院患者が湯たんぽで熱傷を負ったことについて,湯たんぽの取扱いについて看護師の過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第8610号 損害賠償請求事件
平成16年2月16日判決
【入院管理,看護過失,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和47年生,男性)は,平成13年10月,右膝の手術のため被告病院(総合病院)に入院し,全身麻酔下で手術を受けた。被告病院の看護師は,手術後のベッドを温めておくため患者のベッド内に湯たんぽを入れた。
患者は手術後,病室の患者のベッドへ移されたが,看護師がベッドから湯たんぼを取り出すまでの間に,湯たんぼの熱により左下肢外側に熱傷深度Ⅱ度の熱傷を負った。熱傷は平成14年4月に治癒したが,患者の左下肢には,縦10cm,横5cmの大きさの瘢痕が残った。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計250万円(777万6216円の一部請求) | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計66万円) | ||||
| 争 点 | ①看護師に湯たんぼの取扱いについて過失が認められるか。 ②損害額(傷害慰謝料,後遺症慰謝料) | ||||
| 認容額の内訳 | ①傷害慰謝料 | 30万円 | |||
| ②後遺症慰謝料 | 30万円 | ||||
| ③弁護士費用 | 6万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
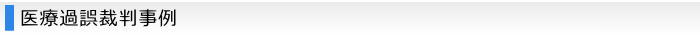
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
人工股関節置換手術の予後について説明義務違反が認められ,手術後に生じた脱臼の徒手整復時の骨折についても病院の責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第7154号 損害賠償請求事件
平成15年3月27日判決
【説明義務,問診義務,手技,手術適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,男性)は,平成4年8月,バングラデシュから来日し,発泡スチロール型組み立て作業に従事していた。患者は,甲病院(大学病院)の紹介を受け,平成11年8月11日,被告病院(総合病院)を受診した。被告病院は,患者の主訴を左股関節痛とし,左変形股関節症と診断し,同年9月9日,左人工股関節全置換術を実施した(本件手術)。
患者が入院中の同月21日,左股関節脱臼が生じ(本件脱臼),徒手整復を施行中,左大腿骨遠位に螺旋骨折を生じた(本件骨折)ため,被告病院は,同月22日,左股関節観血的整復術及び左大腿骨観血的整復固定術を施行し,本件脱臼及び、本件骨折の治療を行った。患者は,同年12月15日,乙病院に転院した。
患者は,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計5066万4500円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計804万8804円) | ||||
| 争 点 | ①被告病院は手術適応がないのに本件手術を実施したか。 ②被告病院に本件手術に関する説明義務違反があるか。 ③被告病院に本件脱臼を生じたことに過失があったか。 ④被告病院に本件骨折を生じたことに過失があったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | 本件骨折と相当因果関係にある損害 | 合計534万8804円 | |||
|
| ①治療費 | 61万0812円 | |||
| ②入院雑費 | 23万1400円 | ||||
| ③休業損害 | 150万6592円 | ||||
| ④傷害慰謝料 | 250万0000円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 50万0000円 | ||||
| 説明義務違反と相当因果関係にある損害 | 合計270万円 | ||||
|
| ①慰謝料 | 250万円 | |||
| ②弁護士費用 | 20万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
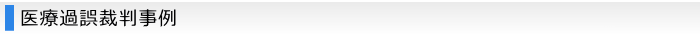
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
心筋梗塞の急患患者に対する適切な検査等の治療措置を怠ったとして,整形外科病院の責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第9400号 損害賠償請求事件
平成13年9月20日判決
【検査義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和21年生,男性)は,平成11年9月,午後3時前ころ,仕事の打ち合わせ中に嘔吐し,左肩部の激痛を訴え,救急車で,現場から最も近い被告病院(整形外科。指定診療科目を整形外科単科とした二次救急医療機関)に搬送された。
患者は,糖尿病・高血圧の既往症があり,投薬等の治療を受けていたほか,1か月前ころ,近所の接骨院で左肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)と診断されていた。
患者は,駆けつけた救急隊に対し,1か月くらい前から左肩の痛みがあり,会社近くの接骨院で五十肩と言われていたこと,仕事中に急に肩の痛みが激しくなったことなどを伝え,救急隊が患者の申告内容及び患者の観察結果(意識清明,呼吸毎分24回,脈拍毎分72回)を被告病院に伝えた。被告病院に搬送された時点で,患者は,意識清明,呼吸毎分18回,脈拍毎分63回,発汗はあったが,酸素マスクは付けていなかった。
被告病院の担当医師は,石灰沈着性肩関節周囲炎及び頚椎椎間板ヘルニアの可能性を考え,肩と頚椎のエックス線検査の指示を出したが,エックス線の所見では,左肩関節に石灰の沈着が見られず,スパーリングテスト(椎間孔圧迫テスト)によっても,頚椎椎間板ヘルニアの所見はなく,神経学的にも異常がなかった。
担当医師は,カルテに頚椎椎間板症と記載し,患者に対し,肩関節周囲炎の治療として,左肩関節に注射をし,左肩を三角巾で固定した上,飲み薬・座薬の消炎鎮痛薬,胃薬等を処方し,痛むようなら来週来院するようにと指示して帰宅させた。
患者の左肩の痛みは,その後も変わらず,患者は,翌日午前0時ころに意識を失い同日午前1時46分,急性心筋梗塞(前壁中隔)による心破裂により死亡した。
患者の家族が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億0493万2108円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計7795万9284円) | ||||
| 争 点 | 担当医師が,患者の訴えや症状から,心筋梗塞を疑い,心電図検査等を行い,適切な医療措置を施すべきであったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①診察費 | 7万0340円 | |||
| ②逸失利益 | 4988万8944円 | ||||
| ③慰謝料 | 2200万0000円 | ||||
| ④弁護士費用 | 600万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
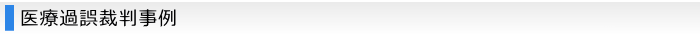
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
腰椎すべり症を見落とした過失,骨盤牽引による保存的治療を採用した過失,外科的手術を実施しなかった過失,保存的治療に関する説明義務違反等がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第9511号 損害賠償請求事件
平成18年3月15日判決 確定
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は腰痛の持病があり,平成10年7月,腰椎椎間板ヘルニアの手術を受けた。平成12年4月19日,患者は,足と腰の痛みを訴えて,被告医院を受診し,腹部超音波検査,胸部及び腰部X線検査,腹部CT検査の結果,腰椎椎間板ヘルニアに対する腰椎椎弓部分切除術の術後所見が認められ,第3ないし第5腰椎の変形及び腰椎すべり症が認められた。被告医師は,カルテに腰椎すべり症との診断名を記載しなかった。被告医師は,X線写真を患者に交付するとともに,保存的治療として,薬剤の処方や骨盤牽引,下肢等の電気治療,エアマッサージ等のリハビリ治療を開始した。患者は,被告医院に通院し,骨盤牽引などの保存的治療を受けていたが,平成12年7月ころから両腕及び下肢のしびれが強くなり,9月ころには両下肢痛や不眠を訴えるようになったものの,9月5日に実施されたX線検査の結果では,両下肢及び腰部に著変は認められなかった。
患者の腰部症状は,9月以降増悪し,10月20日から,患者は勤務先の会社を休むようになった。患者は,10月26日,甲病院(大学病院)のA医師の診察を受け,第4腰椎すべり症と診断され,乙病院(総合病続)を紹介された。10月27日,患者は,乙病院のB医師の診察を受け,X線検査により,第4第5腰椎間すべり症と診断された。患者は,乙病院に通院し,保存的治療を受けていたが,症状の改善が見られなかったため,平成13年1月13日,同病院に入院し,同月16日,腰椎前方固定術を受け,平成13年3月2日,乙病院を退院した。
患者は,被告医院を経営する被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3361万8875円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①腰椎すべり症を見落とした過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
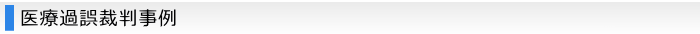
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肘部穿刺によってり橈骨神経が損傷したことについて,穿刺手技を選択した注意義務違反,穿刺方法における注意義務違反,穿刺後の指導における注意義務違反,説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第13102号 損害賠償請求事件
平成18年2月27日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(女性)は,平成14年6月20日,左肘内側にしこり(後にガングリオンと判明)を認めたため被告医師が開設する医院を受診した。被告医師は,触診し,エックス線検査,超音波検査を実施し,ガングリオンや膿瘍を疑い,悪性,良性の鑑別のため,嚢腫内容物の穿刺を行って細胞診検査を行うこととした。被告医師は,患者に対し,穿刺を行うことを説明し,局所麻酔を行い,注射器に穿刺針(24G,長さ2.5cm)を付けて,腫瘤に対し1度目の穿刺を行ったが,患者が穿刺後強い痛みを訴えたため,穿刺針をいったん抜き,近くの部位を再度穿刺した。このとき患者は,痛みを訴えなかったが,軽い痛みを感じていた。注射器を吸引したところ,ゼリー状の物質がl吸引された。被告医師は,穿刺の際,患者の橈骨神経浅枝(知覚校)を損傷した。6月22日,患者は,被告医師に電話をし,手がしびれる旨を訴え,被告医師から直ちに受診するように指示されたため,同日,被告医師を受診した。被告医師は,患者の左腕にしびれを確認したが,触覚,痛覚などの知覚障害,手の動き等の運動障害は見られなかった。被告医師は,ガングリオンによる圧迫症状の増悪や穿刺時の神経損傷等を疑い,患者に対し,回復しない場合は神経修復手術やガングリオンの摘出術を受けるように勧め,手の外科の専門医の診察治療を受ける必要があるとして,複数の医療機関名を挙げて,湿布薬を処方した。被告医師は,6月27日,患者に対し,細胞診検査の結果,良性所見(クラス1)であることを告げ,手のしびれについては,早急に受診する病院を決めるよう勧めた。7月1日,患者が被告医師に,甲病院の受診を希望したため,被告医師は,同病院整形外科あての紹介状を作成し,患者に,被告医師が実施した検査資料等一切を渡した。7月2日,患者は,甲病院を受診し,A医師の診察を受けた。患者は,穿刺痕(橈骨神経領域)のしびれを訴え,左肘関節屈側に穿刺痕が見られた。7月23日,患者は,乙病院を受診し,B医師の診察を受けた。患者は,B医師に対し,被告医師に穿刺された際,左母指背側に放散痛を感じ,その後1か月疼痛が持続していることを伝え,B医師が触診したところ左肘内側に硬結を認めた。B医師は,各種検査の結果,橈骨神経浅枝損傷と診断し,左肘ガングリオン摘出術及び橈骨神経剥離術の実施を決定し,患者は,7月31日,乙病院に入院した。主治医は,C医師で,8月1日,B医師の執刀,C医師等の助手により,患者に対し手術が実施され,患者は,同月3日乙病院を退院した。患者は,平成15年3月25日,同年6月11日,乙病院を受診し,同日で治療が打ち切られ,その後は,医療機関で治療を受けていない。B医師は,平成17年6月8日,患者の左肘について,橈骨神経周膜の裂け目から神経繊維が突出する状態で,これが疼痛の原因であると判断し,疼痛は消失したが,左橈骨神経の固有知覚領域に知覚過敏と異常感覚が残っていると診断した。
患者が,橈骨神経損傷の損害を被ったのは,被告医師に穿刺手技を誤った注意義務違反などがあったからであると主張し,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1421万4555円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①損傷した神経の種類,部位,本件ガングリオンとの位置関係 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
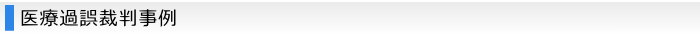
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
腰椎椎弓切除・拡大開窓手術について手術適応違反,及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第10693号 損害賠償請求事件
平成18年2月24日判決 確定
【説明・問診義務,適応】
<事案の概要>
患者(昭和6年生,女性)は,平成12年8月ころ,左下腿前面や左大腿下部に痛みを覚え近医を受診し,腰部MRI検査の結果,腰部脊柱管狭窄症及び椎間板ヘルニアと診断された。同年10月17日,患者は,被告病院(大学病院)整形外科を紹介受診し,翌日,脊椎専門外来で担当医師の診察を受けた。担当医師は,下肢に広範な痛みがあり,MRIも多椎間の椎間板の変性や膨隆所見が認められたため,患者を腰部脊柱管狭窄症と診断した。又,患者の両膝に,内側の関節裂隙の圧痛等が認められ,加齢による軽度の変形性膝関節症の可能性はあったが,膝に限局された痛みではなかったことから,腰椎由来の痛みが主であると診断した。担当医師は,患者に対し2回,仙骨部硬膜外ブロックを実施したが,左下肢痛が改善しなかったため,同年12月,患者を短期入院させ,脊髄造影検査,造影後CT検査,腰椎MRI検査,左第5腰神経根に対する選択的神経根造影検査及び神経根ブロックを行った。その結果,第2/3,第3/4,第4/5腰椎間で脊柱管狭窄像が認められ,神経根穿刺時に患者の疼痛部位と合致する痛みが誘発・再現され,ブロックにより消失し,その後約4日間,症状改善がみられたことなどから,左第5腰神経根障害が患者の症状の主たる原因であると判断した。
平成13年2月9日,患者は,被告病院に入院し,同月16日に担当医師から術前説明を受け,同月20日,第4/5腰椎間の椎弓切除術及び第2/3,第3/4腰椎間の拡大開窓術を受けた。術後, 患者は,下肢痛を訴えなくなり,同年4月4日,被告病院を退院した。しかし,患者は,左膝関節痛や腰痛の悪化を訴えるようになり,同年6月,別の総合病院の整形外科を受診した。MRI検査の結果,左膝外側半月板断裂が疑われ,同年7月4日,同病院に入院し,同月5日に関節鏡視下半月板切除術を受けた。患者は,平成14年5月ころ,右膝関節痛を訴えるようになり,同年11月8日,別の大学病院に入院し,同月12日,関節鏡視下右膝外側半月板切除術を受けた。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1295万4222円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①椎弓切除術及び拡大開窓術の手術適応の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
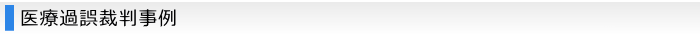
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
頸椎椎弓形成術後,左上肢麻痺が生じたことについて,手術の術式選択の誤り,手術手技上の過失,説明義務違反がいずれも認められなかったケース
地方裁判所 平成16年(ワ)第1224号 損害賠償請求事件
平成18年2月22日判決 控訴・和解
【説明・問診義務, 手技, 治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,女性)は,平成13年9月19日,腰が痛くて下肢に力が入らないと訴えて甲外科病院を受診した。腰部MRI検査の結果,第4,第5腰椎間が狭窄している所見が認められ,患者は,甲外科病院へ通院を続けたが,痛みが増強し,左足の知覚減退,つま先の伸展が不可能などの所見が認められため,10月3日,甲外科病院に入院し,腰の牽引療法や頭,頸,背部のマッサージ療法を受けるなどしたが,改善せず,同月24日に退院した。患者は,その後も甲外科病院に通院したが,背下部痛や左殿部から下肢にかけて,しびれ感,痛みが継続し,同年11月10日,甲外科病院の医師から,痛みが長引くようなら手術も一つの方法であると告げられたため,同月13日に,乙病院の整形外科を受診したところ,同様に手術を勧められた。
患者は,同月20日,左殿部から足の親指にかけての痛みやしびれ,間欠跛行症状,手指巧緻性障害を訴え,被告病院(総合病院)を受診し,神経学的検査並びに腰椎及び頸椎の単純X線写真検査を受け,同年12月3日,腰椎のMRI検査を受けた。同月12日,担当医師(整形外科)は,上下肢の神経学的検査の結果,両上腕三頭筋反射低下,両下肢深部腱反射亢進,ホフマン反射右陽性,右第5頸髄節以下の知覚麻痺,左第5腰神経支配領域の知覚過敏等が認められ,既に撮影されていたX線,MRIフィルムから頸椎症性脊髄症による手巧緻性障害,腰部脊柱管狭窄症による間欠性跛行及び左下垂足と診断し,頸髄症については,重度でかつ進行性のものであると判断した。担当医師は,頸椎症性脊髄症による重篤な運動麻痺の進行予防及び現存症状の改善並びに腰部脊柱管狭窄症による現存症状の改善のため,頸椎椎弓形成術及び腰椎開窓術による治療が望ましいと考え,患者に対し,頸髄症と腰部脊柱管狭窄症であり,手術による治療を受けるよう勧めた。患者は,同月14日,被告病院を受診し,頸部MRI検査を受け,担当医師から第5,第6,第7頸椎間の狭窄症があると診断された。患者は,他院でのセカンドオピニオンを希望し,平成14年1月10日,乙病院を受診し,医師より,頸椎症性脊髄症と診断され,右手及び歩行の不自由が進行するようであれば,頸椎の手術は必要であると告げられた。
患者は,1月31日,被告病院に入院し,2月1日,担当医師から,手術方法等について説明を受け,同月4日,担当医師の執刀により頸部脊柱管拡大術(頸椎椎弓形成術)及び腰椎開窓術を受けた。術後,患者には,左第7頸神経の麻痺症状を生じ,被告病院や他院においてリハビリ治療を受けたが症状は改善しなかった。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3300万円(4665万6547円の一部請求) | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①頸部脊柱管拡大術の術式選択の誤りの有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
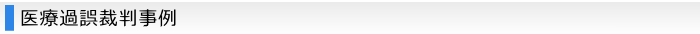
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
在監者の患者について,外部脊椎専門医の診察及び手術を受けさせるべき注意義務違反,適切な保存治療を行うべき注意義務違反,外部脊椎専門医等に後縦靭帯骨化症に関する適切な説明をさせるべき注意義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第2250号 損害賠償請求事件
平成17年11月16日判決 控訴・控訴取下
【説明・問診義務,治療方法・時期,転医義務】
<事案の概要>
患者(昭和23年生,男性)は,平成14年11月10日,鉄砲刀剣類所持等取締法違反で逮捕され,同年11月29日,起訴された。患者は,逮捕後,警察署留置場に勾留されていたが,平成15年2月4日,拘置支所に移監された。拘置支所の入所時の健康診断で,患者は,刑務所医務部所属のA医師(内科)に対し,ヘルニア手術など腰椎及び頸椎に対する手術を過去5回受けたことがあり,頸部痛があること等を伝えた。患者が,平成15年4月ころから,左手のしびれの持続,左腕のやせ及び左握力低下を訴えたためA医師は,整形外科医の受診を指示し,患者は,同年5月1日,医療刑務所整形外科医であるB医師の診察を受けた。B医師は患者の症状を後縦靭帯骨化症に起因する脊髄症状と診断しメチコバール及びユベラ(末梢循環改善剤)を処方し,患者に対し,投薬による保存療法が続けられた。患者は,同年5月21日,患者の元主治医であり,脊椎外科の専門医である甲病院F医師の診察を希望したが,刑務所医務部所属のC医師(外科)は,その必要性はないと考え,F医師の受診を認めなかった。患者は,同年6月12日,乙病院(総合病院)において,D医師によりMRI検査を受けた。MRI所見は,脊髄自体の回復は高度障害により既に困難と考えられるもので,手術療法による効果もあまり期待できない状態であった。D医師は,捜査関係事項照会書に対し,患者には脊椎専門医の診察が必要であり,神経症状が悪化すれば,拘置所内で拘置し続けることに医学上支障がでると思われることなどを回答した。
F医師は,同年6月30日,患者の弁護人と面談し,頸椎ヘルニア及び頸椎後縦靱帯骨化症による症状の発生ないし進行が予測され,患者がそのような症状を訴えた場合,直ちに精査することが望ましいとの意見書を提出した。G医師(後縦靭帯骨化症を含めた脊椎疾患に関する治療の第一人者)は,同年9月8日付けで,捜査関係事項照会書に対し,乙病院のMRI検査結果によれば,患者に対する外科治療は,症状改善の予見又は保証が困難であるばかりか,かえって症状が悪化し,生命にかかわる障害が生じる可能性も稀とはいえないため,現状では現実問題として外科治療の適応はない旨回答した。
同年9月29日,患者は,丙病院(総合病院)を受診した。E医師の診察を受けた。同医師は,捜査関係事項照会書に対し,手術療法が望ましいが技術的に困難であり,手術可能な施設があれば手術を受けるという選択肢もあることなどを回答し,患者の弁護人による弁議士会照会に対し,患者に頸椎後縦靭帯骨化症の症状があり,対症療法では治らないため,F医師が手術可能と判断するなら受けてもよいと思うなどと回答した。F医師は,同年11月8日,患者の弁護人あてに,患者の手術歴及び丁病院のMRI検査結果上,頸椎ヘルニア及び頸椎後縦靭帯骨化症が残存している所見が認められるので,四肢麻痺などの症状が進行しているのであれば,早急にMRI等の検査を受ける必要があるとの意見書を提出した。
拘置支所長は,同年11月27日付けで,患者の弁護人による弁護士会照会に対し,同年5月1日,整形外科専門医による診察を,同年6月12日,MRI検査を,同年9月29日,整形外科専門医の診察を各々受けさせていること,施設内で可能な対症療法を実施しており,現状のまま勾留を継続することは可能と考えられる旨を回答し,平成16年1月21日付けで,患者に対する外科手術は難しく,対症療法を実施していること,手術によって回復できる時期は既に過ぎていて手術適応はなく,元主治医の治療を受ける必要性はないと判断している旨を回答した。F医師は,拘置支所長による平成16年2月20日付け照会に対し,患者には頸椎ヘルニア及び頸椎後縦靭帯骨化症による症状の発生進行が予測され,四肢麻痺も進行しているとのことであるから,早急に検査を受ける必要があると思われる旨回答した。
患者は,刑務所医務部所属医師及び拘置支所長が,患者に対して適切な保存療法を行わず,患者を放置したため,手術によって回復可能な時期を徒過し,将来的に脊椎麻痺に陥る可能性がある状態にされたなどとして,刑務所医務部所属医師及び拘置支所長の職務上の義務違背を主張し,国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①外部脊椎専門医の診察及び手術を受けさせるべき注意義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
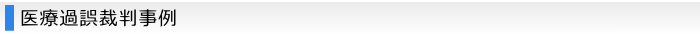
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
四肢機能障害を被った患者の転落防止措置における注意義務違反,手術選択,手術時期,投薬における注意義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所
平成16年(ワ)第2296号,平成16年(ワ)第2297号 損害賠償請求事件
平成17年11月9日判決 控訴・控訴棄却
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(大正6年生,男性)は,2月27日,他院から紹介を受け,被告病院整形外科を外来受診した。被告病院A医師(主治医)は,レントゲン検査,頸椎MRI等の検査の結果,頸椎症性脊髄症(頸髄症),巧緻性障害,歩行障害と診断し,患者に対し,頸髄症等の治療のため,頸椎椎弓形成術が必要である旨説明した。患者は,3月6日,被告病院を受診し,A医師は,頸椎MRI検査の結果,C3/4(第3/4頸椎)から6/7(第6/7頸)までの多椎間に頸髄の圧迫を認め,頸椎椎弓形成術の適応があると判断し,同月15日に施術を実施することとした。患者は,同月13日,被告病院に入院したが,その際,頸髄症のため末梢の神経症状が増悪気味であるとして,ベッド柵が設置された。又,患者が,ここ2週間ほど,腹痛,腰痛で眠れないと訴えため,同月14日,患者に対し,頸椎椎弓形成術前夜の麻酔前投薬として,入眠剤マイスリー5㎎2錠,緩下剤プルセニドを2錠処方した。患者は,同月15日午前O時20分ころ,ベッドから転落しているのを発見され,転落により,右上腕骨頸部及び右大腿骨転子間を骨折した。
同日,A医師は,患者に対し,頸椎椎弓形成術を実施した。同月16日,頭部CT検査が行われたが,外傷性の変化は認められなかった。患者は,同日,被告病院精神科で診察を受け,B医師により,せん妄を伴う痴呆(疑い)と診断され,グラマリール,デジレル,セレネースが処方され,デジレル,セレネースは,退院まで続けられた。患者のせん妄は,3月23日ころから軽快したが,2,3日後悪化傾向となり,4月2日前後から少しずつ軽快し,同月10日〜11日ころ症状の増悪が見られたが,同月17日ころから軽快した。A医師は,患者に対し,同月22日,右大腿骨転子間骨折の治療のため,髄内釘固定術(ガンマネイル法)を施術し,同月26日からリハビリ治療を開始し,退院までほぼ毎日実施された。6月5日,患者は,整形外科からリハビリテーション科に転科し,9月26日,C病院に転院した。被告病院医師は,患者の身体障害について,7月30日,四肢機能障害(後遺障害第1級)と診断した。
患者とその家族は,患者が被告病院に入院中ベッドから転落して右大腿骨転子間等を骨折したり,手術後四肢機能障害を被ったのは被告病院医師らの投薬,手術時期選択等に過失があったからであるとして,被告病院を開設している地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計9408万7067円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①転落防止措置について過失があったか | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
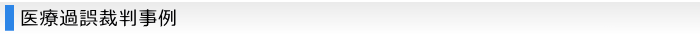
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
大腿骨転子下粉砕骨折の治療のために挿入されていた髄内釘等の内固定材料を抜去できなかったことについて,担当医師に過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第1468号 損害賠償請求事件
平成17年10月20日判決 控訴
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
厩務員であった患者(昭和45年生,男性)は,平成11年10月10日,競走馬の調教中に落馬し,右大腿骨転子下粉砕骨折と診断され,被告病院(大学病院)に入院した。患者は,同月19日,被告病院において,右大腿骨に骨折部分を固定する髄内釘,スクリュ一等の内固定材料を挿入する観血的整復術を受けた。患者は,平成14年6月24日,被告病院に再入院し,同月25日,内固定材料の抜釘術を受けた。抜釘術では,骨皮質を削除するなどして内固定材料の抜去が試みられたが,抜去することができなかった。患者は,抜釘術後,数日して右下肢の疼痛やしびれを覚えるようになった。患者は,同年8月14日に退院し,勤務を再開したが,長時間歩いたり同じ姿勢をとると断続的に右下肢の疼痛及びしびれを生じるため,騎乗による調教を行うことはできなかった。平成16年5月17日,患者は,右股関節周辺の疼痛及び熱感並びに右下肢の疼痛及びしびれの後遺障害がある旨の診断を受けた。
患者が,被告病院を開設する学校法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2183万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①抜釘時期の適否(より早期に抜釘を実施すべきであったか) | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
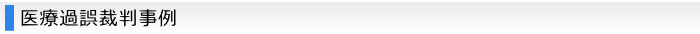
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
下顎骨の骨折整復固定術を受けた患者が,術後3日目に死亡したことについて,担当医師が術中,下顎骨固定用ワイヤーを患者の脳内に刺入させた過失,及び死亡原因となった敗血症やDIC(播種性血管内凝固症候群)を看過した過失がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第9991号 損害賠償請求事件
平成17年1月31日判決 控訴
【手技,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和52年生,女性)は,平成9年12月8日夜,荒川に架かる橋上から水中に落下し,多数の外傷を負った。患者は,同日午後11時すぎ,甲医院を受診し,背部腹部打撲擦過傷,顔面打撲擦過傷,右鎖骨骨折,下顎骨骨折,左第6・第7肋骨骨折等の診断を受けて入院した。患者は,翌9日,非常勤医として甲医院に勤務していたA医師の診察を受け,左第6・第7肋骨骨折については自然治癒を待ち,右鎖骨骨折については保存的療法で完治可能であるが,下顎骨の2か所の骨折は,皮膚を切開し骨折部位を直視下に整復固定する観血的整復固定術を施行する必要があると診断された。
患者は,下顎骨の整復固定術を受けるため,12月11日,被告病院へ転院し,12月15日,被告病院形成外科において,執刀医A医師,B医師(第1助手),C医師(第2助手)らによる観血的整復固定術を受けた。手術では,右関節突起の骨折部位を固定するため,右下顎角から上方の関節突起に向けて,下顎骨内にキルシュナー銅線(Kワイヤー)が挿入された。
患者は,術後,敗血症を基礎疾患とするDICを発症し,術後3日目である12月17日,DICから多臓器不全を生じて死亡した。DICの原因は不明であるが,12月16日に採取された動脈血の培養検査で血中からグラム陰性桿菌であるセラチア菌が検出された。
患者の両親が,病院の開設者である学校法人に対し,医師が術中に下顎骨固定用のワイヤーを誤って患者の脳内に刺入させたことが敗血症の原因である,又,敗血症やDICの徴候を看過して適切な診療を怠った過失があるなどと主張し損害賠償請求訴訟を提起した。なお,本件は,B医師が,数年後,患者の両親に対し,脳へのKワイヤー刺入を目撃したと告発したことをきっかけで訴え提起に至った事案であり,B医師の供述の信用性についても争われた。
| 請求金額 | 合計1億0600万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①手術中,Kワイヤーが脳内に刺入したか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
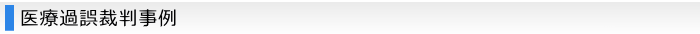
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
鞭打損傷及び第4頸椎骨損傷,第5,第6頸椎椎間板狭小,右上肢のしびれにつき,誤診,検査義務違反が認められず,因果関係も否定されたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第12175号 損害賠償請求事件
平成16年10月27日判決 確定
【検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭利24年生,男性)は,平成10年6月16日交通事故にあって受傷し,同日,被告医師を受診した。被告医師は,頸部エックス線検査を実施して,鞭打損傷及び第4頸椎骨損傷と診断し,患者に対し,ビタミンB1誘導体の静脈注射,鎮痛薬,湿布処置を行い,投薬,湿布薬を処方した。患者は,被告医院に通院し,これらに加えマイクロ波照射を行うとともに,頸椎固定べル卜の装着を指示し,7月から9月にかけて同処置を続け,適宜エックス線写真を撮影して経過を観察した。9月30日,被告医師は,患者の了承を得た上で,治療を終了した。患者は,その後,被告医師の紹介により,10月15日,他院を受診し,頭部CT,頭部正面及び側面,頸椎正面及び側面のエックス線検査を受けたが,検査結果に異常は認められず,特段の治療処置は受けなかった。患者は,10月27日,交通事故の加害者側損害保険会社との間で,将来後遺障害が判明したときは,別途協議することを内容とする示談をした。
患者は,交通事故によって第5,第6頸椎維間板狭小に起因する右顎部痛,右上肢しびれ,右上肢筋力低下を来たし,右手のしびれ,握力低下,首・肩の痛みがあるが,これは被告医師がなすべき治療を行わなかったため悪化したものであり,又,被告医師の誤診によりMRI検査が受けられなかったことにより,交通事故による外傷性器質的損傷を立証できず後遺障害認定を受けることができなかったとして,被告医院を開設している被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2228万4013円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①被告医師に,右手,右腕の痛みとしびれについて適切な診断,治療を怠った過失があるか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
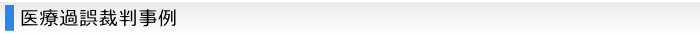
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
骨の固定のため橈骨に固定された金属プレートが変形して折損したことについて担当医師に過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第23300号 損害賠償請求事件
平成16年9月9日判決 控訴・控訴棄却
【適応,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(1昭和35年生,男性)は左手首の疼痛等を訴え,平成13年2月5日,被告病院(総合病院)整形外科を受診し,左外傷性変形性手関節症と診断され,3月26日,被告病院に入院し,同月28日,橈骨楔状骨切り術,及び三角骨・豆状骨固定術を受け,4月17日,退院した。骨切り術では,橈骨遠位端(橈骨の末梢側の端)掌側が楔状に切除され,切除部位がT字型の金属プレートで固定され,固定術では,三角骨と豆状骨が金属ピン2本で固定された。
被告病院を退院後,骨固定のための金属プレートは,徐々に掌側に屈曲し,折損するに至った。患者は,10月30日,被告病院に再入院し,同月31日,折損した金属プレートを新たな金属プレートに交換する手術を受け,11月2日に退院した。
患者は,手術等を原因として,手首の組織(筋,腱,神経)の圧迫・損傷,正中神経,尺骨神経及び橈骨神経の麻痺が生じ,手首を上下左右に5度以上曲げようとすると激痛を生じ,示指から小指の全ての遠位指節間関節,近位指節間関節,中手指節関節が5度ないし30度以内にしか曲がらなくなるなどの障害を負ったと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億6004万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①固定術の手術適応の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
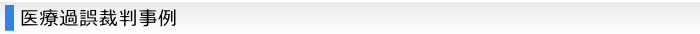
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
腰椎椎間板ヘルニア及び脊柱管狭窄症に対する後方椎間板切除術について,担当医師に過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第18149号 損害賠償請求事件
平成16年4月8日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,手技,適応】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は,腰痛と下肢痛の再発と軽快を繰り返していたが,平成5年4月16日,甲大学病院を受診し,第4,第5腰椎間の椎間板ヘルニアと黄靭帯肥厚が合併した混合型の脊柱管狭窄症と診断された。患者は,硬膜外神経ブロック,神経根ブロック等の治療を受けたが,ほとんど効果がなかった。患者は,A医師の勧めにより,5月12日,被告病院(総合病院)に入院し,同月24日,後方椎間板切除術(ラブ法)を受けた。術後,患者は,手術前にあった臀部痛や下肢の激しい疼痛は消滅したが,足のしびれが残存し,新たに両拇趾にしびれを生じた。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4557万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①後方椎間板切除術の適応の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
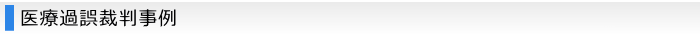
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
関節鏡視下遊離体摘出術及び外側半月板部分切除術の手術中に右総腓骨神経及び脛骨神経が損傷したとは認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第4191号 損害賠償請求事件
平成15年10月29日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,女性)は,平成9年5月,自宅で転倒して右膝が痛くて歩けなくなったため,被告病院整形外科を受診した。担当医師(整形外科医)は,数回の診察,及び,レントゲン,MRI検査などの結果,右膝関節内遊離体嵌頓,外側半月板損傷と診断し,同年6月5日,関節鏡視下遊離体摘出術及び外側半月板部分切除術を実施した。担当医師は,術後,及び,翌日の診察で,右足関節・足趾の運動及び知覚に問題がないことを確認し,以後,ほほ毎日患者を回診した。
同月18日,患者が担当医師に対し,右足趾が底屈しにくいと訴えたが,同医師は,緊急性を要するほどの症状ではないと判断し,経過観察とした。その後,1か月,担当医師は,ほぼ毎日患者を回診したが,患者が,右足関節及び足趾の異常を訴えたことはなかった。
同年7月23日,患者が,右足趾の疼痛,術後右足趾が動かしにくいと訴えたため担当医師は,理学療法士に右足趾のリハビリテーションを指示したが,症状の原因は不明であった。患者が退院する同年8月1日までの間,患者が担当医師に対し右足関節及び足趾の異常を訴えたのは,2回のみであったが,看護師に対しては,頻回に異常を訴えていた。
担当医師は,患者が退院した後も,定期的に外来で患者を診察していたが,同年9月24日以降,右足関節及び足趾の筋力低下,知覚鈍麻などの訴えがあったためレントゲン,MRI,脊髄造影,筋電図等の検査を実施したが,患者の訴える症状の原因は判明しなかった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①手術時に総腓骨神経及び脛骨神経を損傷させたか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
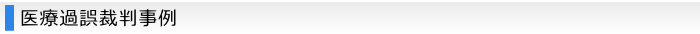
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
骨接合術後,担当医師が,患者が退院するに際し,経過観察のため定期的に通院する必要があり,1年後程を目途に髄内釘を抜去する必要があることを患者に指示説明したと認め,髄内釘の抜去義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第14333号 損害賠償請求事件
平成15年7月28日判決
【説明義務,問診義務,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和26年生,男性)は,昭和63年10月4日,交通事故で左大腿骨骨折,両足脛骨骨折などの傷害を負って被告病院(総合病院)に入院し,同月6日,観血的骨接合手術を受けた。担当医師(整形外科)らは,骨折部位を整復固定するための金具として,左大腿骨にステンレス製の髄内釘を挿入しねじ釘で固定し,左右の脛骨にはステンレス製のプレートを添えねじ釘で固定した。
患者は,平成元年3月末ころ,被告病院を退院し,平成13年1月まで,被告病院を受診することはなかった。
患者は,平成12年11月ころ,左大腿部に痛みを感じるようになり,膿の流出が見られたため,平成13年1月2日,甲病院を受診した。検査の結果,左大腿骨に挿入されていた髄内釘が突出し,感染症を生じていた。患者は,同月4日,被告病院に入院し,左大腿骨骨折後骨髄炎と診断され,同月11日,左大腿骨に挿入されていた髄内釘の抜去手術を受け,同年3月1日,左右の脛骨に添えられていたプレートの除去手術を受け,3月19日に退院した。
患者は,平成13年5月17日,大腿骨骨折による左下肢機能障害により身体障害程度等級4級の認定を受けた。
患者は,被告病院を経営する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計8383万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①被告病院の担当医師が,患者が退院するに際し,経過観察のため定期通院が必要があること,1年後程を目途に髄内釘を抜去する必要があることを患者に指示説明したか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
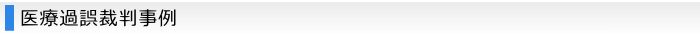
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
眼瞼瘢痕除去手術に関する説明義務違反が認められなかった一方,患者に対する面談強要行為等の差止めや慰謝料の請求が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8639号 債務不存在確認等請求事件
平成15年1月29日判決
【説明義務,問診義務,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,男性)は両上眼瞼に傷跡があり,平成10年3月3日,原告法人の経営するクリニックを来院して,左上眼瞼の傷跡につき医師A(形成外科で原告法人の理事長)の診察を受け,同年4月4日,原告法人の医師B(形成外科)の診察後,同医師の執刀で左上眼瞼瘢痕除去手術を受けた。患者は,同年7月18日,B医師の診察時,右上眼瞼の傷跡ついても手術を希望し,同年8月29日,B医師の執刀で右上眼瞼瘢痕除去手術を受けた。
患者は,平成12年5月13日,クリニックに来院し,B医師に対し,各手術前の説明が不十分であった,傷跡が残っている,治療費を返してほしいなどと主張し,その後もたびたび来院して,A医師らに対し,責任を追及する旨の主張を繰り返した。原告法人は,患者との間で,同年11月27日,原告法人は患者がクリニックに支払った治療費を全額返還し,患者は,原告法人に対し,今後一切本件に関する異議を申し立てないことを内容とする誓約書を取り交わし,原告法人は,同日患者に治療費全額を返還した。
しかし,患者は,その後も,頻繁に来院したり,電話や手紙を送り続け,原告法人やA医師らに対して,面談強要や脅迫を繰り返したので,原告法人及びA医師が,患者に対し,債務不存在確認等を求める訴訟を提起した。
| 請求金額 | ①患者・原告法人間の各治療行為を原因とする損害賠償債務の不存在確認 | ||||
| 結 論 | 一部認容 | ||||
| 争 点 | ①説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
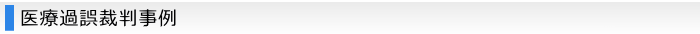
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
悪性腫瘍について検査義務違反,早期発見義務違反が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第5297号 損害賠償請求事件
平成14年11月27日判決
【検査義務,早期発見義務】
<事案の概要>
患者(昭和46年生,男性)は,平成2年9月ころ,左肘尺側に類上皮肉腫の原発があり,平成4年に原発局所である左前腕に再発し,平成8年10月,好発転移部位で,予後決定因子である肺への転移が出現し,同年11月,胸腔鏡視下肺切除手術が施行されたが,術中,胸膜播種が見つかり,胸水からも悪性細胞が証明されたため,最大病巣を切除したのみで,胸膜に播種する病巣については切除できなかった。患者には,化学療法や放射線療法の適応がなかったため,根治的治療が断念され,姑息的な延命治療として,被告病院(総合病院)において胸腔内温熱併用化学療法を行い,同療法の実施後,平成9年1月22日から,インターフェロンによる免疫療法を行いながら,病変の残存する胸部に対し,定期的にレントゲンやCT検査が実施された。
被告病院担当医師は,平成9年1月22日以降,好発転移部位である胸部,リンパ節等について問診,視診,触診等を行って経過観察をしたが,全身について触診等を行うことはせず,画像診断についても,胸部以外は,同年9月5日にガリウムシンチを行った他,平成11年4月19日に鎖骨上窩のMRIを行うまで,特に画像診断を行わなかった。
担当医師が,同年4月19日,触診したところ,鎖骨上窩に圧痛を認めたためMRI検査を実施したところ,肺尖部の胸膜肥厚に再発病巣が描出された。
患者は,その後,腹腔部,大腿部,皮膚,右眼瞼膜等に順次転移が検出され,平成11年11月12日,類上皮肉腫を原因とする腹腔内出血を死因として死亡した。
患者の家族らが,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 担当医師に,患者の悪性腫瘍の転移状況について,全身の観察や定期的かつ適切な画像診断を怠り,早期発見に努めなかった過失ないし注意義務違反があるか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
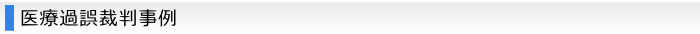
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
胸椎伸展矯正法を実施した柔道整復師が,患者に脊髄損傷等を発症するおそれを予見できなかったとして施術の過失が否定されたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第7953号 損害賠償請求事件
平成14年9月30日判決
【手技,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和18年生,男性)は,平成9年5月23日から,被告整骨院に通院し,頸椎捻挫,腰椎捻挫,右前腕部挫傷の診断で,1週間に1〜3回の割合で,継続的に通院していた。患者は,平成11年初めころから,通院3回につき1回程度の割合で,担当の柔道整復師により,プチブロックを用いて胸郭を前方向に押し広げる胸椎伸展矯正法(本件施術)を受けるようになった。
患者は,平成12年4月下旬ころから,左肩甲骨と背骨間の部分の強い痛みが取れないため,同年5月1日,甲病院を受診した。患者は,知覚異常,手指運動障害は認められなかったが,後屈時に疼痛が生じ,スパーリングテスト,ジャクソンテストで左陽性,握力は左8kgに低下していた。X線検査の結果,C5〜C6に軽度の狭小化が認められ,C6に骨棘が認められたため,担当医師は,頸椎症性神経根症と診断し,安静を指示し,痛み止めの内服薬と湿布を処方した。
患者は,同月9日,同月12日,被告整骨院で施術を受けたが,甲病院を受診したことは告げなかった。
患者は,同月13日午前9時ころ,甲病院で投薬を受け,同日午前10時過ぎ,被告整骨院で電気治療を受けた後,担当柔道整復師の治療を受けたが,問診に対しては,いつもと同様に首と肩が凝っていると答えたものの,甲病院を受診したこと告げなかった。
担当柔道整復師は,患者に対し,指圧,膝関節,股関節を屈曲するストレッチを行った後,背部の筋緊張を緩和するため,胸椎伸展矯正法を施した。患者は,施術終了後,自転車で帰宅した。
患者は,同日午後8時ころ,自宅でテレビを見ているとき,腰がスッと抜けるような異常な感覚を2回感じ,翌14日午前2時過ぎころ,体に異変を感じて目覚め,寝返りが打てず,左腕と両足が動かず,胸から下の部分が麻痺していることに気付き,同日午前9時ころ,甲病院に救急搬送され入院した。
患者は,同日,甲病院でのMRI等の検査の結果,C5-6,C6-7の2か所に頸椎椎間板ヘルニアがあり,C6-7でヘルニアが脊髄を圧迫ないし損傷していることが判明したため,同年9月1日,頸椎椎椎間板ヘルニア除去術,頸椎前方固定術を受けた。
患者は,下肢麻痺,しびれ感,歩行障害,膀胱直腸障害,頸部痛,腰痛等の後遺障害,C5-7の前方固定術により脊柱の変形を残し,頸椎部に運動障害が残った。
患者は,担当柔道整復師及び被告整骨院を経営する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億5450万8244円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者の胸椎伸展矯正法施術前の状態 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
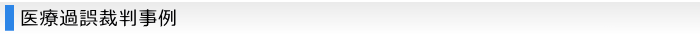
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
左下腿部の黒色腫の切除術及び植皮術を実施したことについて,手術適応の判断を誤った過失,手技を誤った過失,説明義務違反がいずれも否定されたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第12186号 損害賠償請求事件
平成14年9月25日判決
【説明義務,問診義務,手技,検査,手術適応】
<事案の概要>
患者(平成11年当時26歳,女性)は,平成11年8月27日,左下腿部に黒色腫ができたため被告病院(大学病院)形成外科を受診した。担当医師(形成外科)は,患部の所見と患部から出血が続くとの患者の訴えから,悪性の皮膚腫瘍を疑い,最も悪性度の高い悪性黒色腫との鑑別のため,腫瘍部の組織検査を兼ね,できるだけ早く腫瘍部を完全摘出する必要があると判断し,同日午後,黒色腫の切除術を施行した。
同年9月7日,切除部の病理組織検査の結果,スピッツ母斑(良性の皮膚腫瘍)と考えられるが,スピッツ母斑にしては核異型が強いので経過観察が必要と診断されたため,担当医師は,皮膚科の診断も経て確定診断する必要があると考え,患者に対し,皮膚科を受診するよう勧めた。
患者が、皮膚科を受診したところ,基本的にはスピッツ母斑でよいと思うが,悪性黒色腫と異型性母斑との鑑別判断を要するため,患部から5mm離して切除し経過観察を要すると診断された。同月17日,担当医師は,患者に対し,左下腿部皮膚腫瘍拡大切除術・遊離植皮術を実施した。
同年10月4日,患者は左下肢の跛行及び長時間の荷重による疼痛を訴えたが,担当医師は,全体としては症状の軽減が認められたことから患者を退院させた。
患者は,退院後,形成外科を外来受診し,左下肢の腫れと疼痛を訴え,リハビリテーション科でリハビリテーションを受け,平成13年6月には甲病院(総合病院)にて瘢痕切除術を受け,同年9月19日,被告病院形成外科を外来受診した際,左下肢の下3分の1から足先までしびれ感があり,左踵部後方に浮腫があって,長時間歩行すると疼痛が出ると訴えた。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 634万6782円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①悪性黒色腫は,DMSやスタンプ蛍光法の補助診断法によって確定診断が可能で,これら補助診断法で確定診断できない場合に限って皮膚生検を行うべき注意義務があったか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
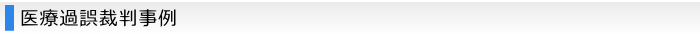
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
椎弓拡大術を実施した患者について,説明義務違反はなく,装具の交換時において患者の頸椎を骨折させた過失も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第18689号 債務不存在確認請求事件
平成14年6月19日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(男性)は,平成4年6月25日,船舶内で作業中,大波で転倒して頭部を強打し,激しい頭痛,めまい,手のしびれ及び吐き気を生じ,症状が改善しなかったため,同年12月11日,原告病院(総合病院)へ入院した。
担当医師は,頸椎後縦靭帯骨化を伴う頸髄不全損傷と診断し,頸椎牽引を行った結果,症状は軽減したものの,しびれ感が取れなかったことから,平成5年2月17日,椎弓拡大術を予定した。しかし,患者が過体重で,血糖値も高かったため手術を延期し,食事療法及び運動療法を行った後,同年3月12日,第2頸椎椎弓部分切除,第3頸椎椎弓切除,第4から第7頸椎までの椎弓拡大術(人工骨使用)を実施し(本件手術)。
患者は,本件手術後,頸椎固定器具SOMIを装着したが,同年5月12日,担当医師の指示を受け,装具取扱業者であるAは,SOMIより簡易な回定器具であるフレームカラーに取り替えた(本件交換処置)。
患者は,同年9月27日,頚部痛,頭痛及び手足のしびれが改善しないため精査目的で原告病院に入院した。同年10月5日,脊髄造影とCT検査を行ったところ,患者に造影剤によって,検査直後から蕁麻疹様の皮疹が出現した。
その後,担当医師は,第2頸椎の椎弓の拡大手術,人工骨の異常の有無の確認,第4頸椎の人工骨の摘出等を行ったが,患者は,原告病院への通院を続けるうち金員の要求をするようになった。
病院側が,患者に対し,債務不存在確認請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 病院側から患者に対し,平成4年12月11日から平成13年8月31日までの治療行為を原因とする損害賠償債務が存在しないことの確認請求 | ||||
| 結 論 | 請求認容(病院側に債務が存在しない) | ||||
| 争 点 | ①担当医師は,本件手術に際し,頸椎椎弓切除について説明し,患者の承諾を得たか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
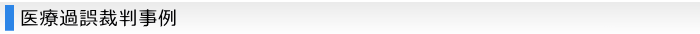
整形外科・形成外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
椎間板ヘルニアについて,保存療法ではなく手術療法を選択したことに誤りはなく,検査及び手術にも過失が認められず,説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第20844号 損害賠償請求事件
平成14年2月27日判決
【説明義務,問診義務,手技,手術適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和42年生,男性)は,勤務中腰に強い痛みを感じ,近所の病院を受診して椎間板ヘルニアの疑いと診断された。患者は、精査目的で,平成6年6月2日,被告病院(総合病院)を受診した。患者は,当時,適法な在留資格を得ないまま日本で労働に従事していたイラン人で,健康保険に加入していなかったため,自費で診察を受けた。
患者は,同年7月14日,被告病院へ入院し,同日A医師(整形外科)立会の下で,B医師(整形外科)により,脊椎造影検査が実施された。
同月21日,B医師は,患者に対し,椎間板(L5/S1)造影検査(本件ディスコグラフィー検査)を実施した。本件ディスコグラフィー検査の刺入時,放散痛があり,検査後,患者の腰部と左臀部に痛みが現れた。
担当医師らは,同月26日,患者に対し,腰椎ヘルニア摘出術の説明を予定していたが,同月28日に延期し,同日,手術同意書が作成され,同月29日に腰椎ヘルニア摘出術が実施された。その際,無症状であった左側も開窓した(本件手術)。
患者は,本件手術後も,左臀部から左下肢にかけての痛みやしびれが続いていたが,同年8月2日に左臀部に軽度のしびれ,同月7日に左臀部から左大腿後面にかけて痛みを訴えたていたが,それ以後,同月22日に被告病院を退院するまで左臀部と左下肢の痛みを訴えなかった。
患者は,同年10月25日以降,再び左臀部から左大腿後面にかけて痛みを訴えるとともに,左大腿前面,左右の大腿内側,鼠径部,ペニスや陰嚢の痛みも訴えるようになった。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4796万3061円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①保存療法ではなく,手術療法を選択したことに過失があるか否か | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




