光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
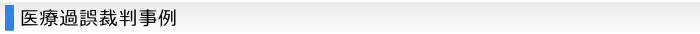
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
上行結腸癌の手術後,患者が術後感染症により死亡したことについて,担当医師に肺炎の診断を遅延した過失,及び,肺炎の診断後に抗MRSA剤の投与を怠った過失がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第4745号 損害賠償請求事件
平成18年2月24日判決 控訴
【検査,治療,入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は昭和60年10月ごろから気管支喘息の治療を受けるようになり,一時入院加療していたが,上行結腸癌が発見されたため,平成13年7月30日,外科的治療目的で被告病院(公立病院)に入院し,同年8月2日,担当医師の執刀により手術を受けた。
患者は,手術翌日から同月7日までの間,CRP値及び白血球数が基準値を上回り,肺雑音が認められたが,酸素飽和度は概ね90%台前半を維持し,呼吸苦を訴えることはなく,体温も概ね平熱であった。同月8日,患者の希望もあり解熱鎮痛剤であるボルタレン坐薬を1日1〜2回から1日3回に増加した。患者は,多少食欲減退もあったが,呼吸苦の訴えはなく,発熱もなかった。同月9日,患者が創部痛を訴えたため1日3回のボルタレン坐薬が投与され,食欲減退や倦怠感が現れたが,呼吸苦の訴えはなく,発熱もなかった。翌10日,胃部症状を軽減するためボルタレン坐薬の使用を中止したところ体温が38.4度まで上昇し,酸素飽和度が90%を切るようになり,「胸が重くなった」など呼吸苦様の症状を訴え始め,翌11日朝には体温が40度を超え,喘鳴があるなど呼吸状態がさらに悪化したため酸素投与が行われ,レントゲン上肺炎所見が認められた。担当医師は,同日,抗菌薬をセファメジンからユナシンS(適応症は肺炎等)へと変更した。患者は,同月11日午後から翌12日朝にかけて,嘔気と創部痛を交互に訴え,酸素飽和度が80%台にまで下がり,酸素投与が再開されたが,同日の体温は概ね36度台で推移し,レントゲン上,右下肺野の陰影は悪化していなかった。同月13日には,白血球数が著明に減少して基準値内となり,体温も37度前後で安定し,酸素飽和度は酸素投与がなくても90%台後半を維持するようになった。同月15日に報告された同月13日に採取された喀出痰の検査結果,グラム陽性球菌が2+と多めに検出され,グラム陰性桿菌も検出されたが,MRSAは検出されなかった。患者に対する抗菌薬の投与は同月16日夕方分で終了となったが,同月19日夜,体温が38度台まで上昇したことがあったが,同月20日のレントゲン上,肺炎を窺わせる陰影は消失していた。
同月28日,レントゲン検査の結果などから患者は肺炎と診断され,同月29日からユナシンSを投与されるようになったが,尿からMRSAが検出され,肺炎は急速に悪化した。患者は,同月30日,ICUに入室し,抗MRSA剤であるタゴシットを投与された。その後,患者は,MRSA肺炎と診断され,平成14年2月24日,死亡した。
患者の転院手続のための報告書には,平成13年8月11日にMRSA肺炎を発症したと記載され,退院時要約(サマリー)にも同日MRSA肺炎を発症したと記載されていた。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する地方公共団体及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6285万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①平成13年8月9日に肺炎と診断すべきであったのに,これを怠った過失があるか否か | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
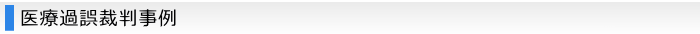
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と診断して腹腔鏡下で腎全部摘出をした過失及び説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第5527号 損害賠償請求事件
平成18年2月15日判決 控訴
【説明・問診義務, 検査,適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,女性)は,平成15年12月22日,甲診療所において,左腎嚢胞の疑いを指摘された。患者は,平成16年1月19日,乙病院において腹部CT検査を受け,左腎に2cm大の出血を伴う結節の存在が判明した。患者は,同年2月16日,被告病院(大学病院)の関連病院である丙病院(総合病院)を受診し,腹部CT検査の所見から,左腎細胞癌と診断された。同年2月21日,患者は,担当医師より,手術の必要性や手術方法等について説明を受け,被告病院において手術を受けることに同意した。
患者は,同年3月5日,被告病院に入院し,同月11日,担当医師により,腹腔鏡下での左腎全部摘出術が実施された。患者の左腎は全部摘出されたが,摘出された腎臓について術後に実施された病理組織診断の結果,左腎の腫瘍は腎細胞癌ではなく,良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫であることが判明した。
患者は,担当医師により良性腫瘍である腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と誤診され,良性腫瘍の可能性などについて適切な説明がなされず,摘出の必要のない左腎を摘出されたとして,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1862万8012円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①必要な鑑別診断を怠り,腎血管筋脂肪腫を腎細胞癌と誤診した過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
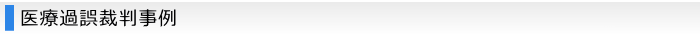
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
食道癌に対する放射線化学療法の実施期間中,患者が深夜突然急性胃潰瘍に起因する大量出血を起こし死亡したことについて,担当医師にあらかじめ抗潰瘍薬の投与をすべき義務や出血を具体的に予見して止血のための措置をとるべき義務が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第1184号 損害賠償請求事件
平成17年2月16日判決 控訴 判タ1195号202貢
【検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和9年生,男性)は昭和55年8月ころから,糖尿病及び胃の治療のため,甲病院へ通院し,胃の薬として,メサフィリン,タガメット,セルベックス,SM散等を処方されていた。昭和58年6月27日,胃内視鏡検査が実施され,潰瘍瘢痕等は認められず,胃の萎縮が強いと診断された。同年11月18日,患者は入院を勧められたが,乙省の要職にあるため入院できないとしてこれを断った。平成6年1月20日,上部消化管内視鏡検査が実施され,食道に異常はなく,胃内にも潰瘍瘢痕等は認められず,萎縮性胃炎であると診断された。
患者は,平成13年7月30日,嚥下困難を訴えて丙大学病院内科及び外科を受診し,同年8月2日,内視鏡により食道及び胃・十二指腸のファイパー検査及び食道の生検を受け食道癌と診断された。患者は,同月10日,入院となり,消化器外科のA医師,B医師,C医師及びD医師らが主治医となった。D医師は患者の娘婿であった。同月13日,光学医療診療部において,内視鏡による食道及び胃・十二指腸のファイパー検査とこれらの部位の生検が同部のE医師,A医師及びD医師により実施され,食道粘膜,胃の表面粘膜,胃底腺粘膜等が採取された。検査の結果,胸部中部食道に長径約7cmの3型食道癌(進行食道癌),全周性で深達度はT2(固有筋層まで浸潤)のものと,それに付随する0-Ⅱbの表在型食道癌があると診断された。診断結果に基づき,患者に対し,抗癌剤であるブリプラチンと5-FUの投与と30ないし40Gyの放射線照射を併用する放射線化学療法を1コース施行して癌を小さくした後,切除手術をする治療方針が決められた。
同月20日から,患者に対し,放射線化学療法が実施され,抗癌剤については,3週間にわたり週5回投与する計画で,1日当たりブリプラチンを15.3㎎,5-FUを512.6㎎投与することとされたが,当初の1週間の投与が終了した同月24日の時点で経過を観察することとされ,それ以降投与は実施されなかった。放射線照射は,当初1日2.5Gyを3週間にわたり週4回,合計で30Gy照射する計画であったが,1日当たりの照射量を減らして同月20日から同月24日までの5日間,同月27日,同月28日及び同月30日にそれぞれ1日2Gyずつ照射された。患者は,同月30日まで,貧血傾向,抗癌剤の副作用による食欲不振,嘔気,嘔吐等はあったものの,身体所見の著明な変化はみられなかった。同日夕方,患者は「便が黒いような気がする」と述べていた。
同月31日,午前4時ころ看護師が見回った際,患者は就寝中で異常は認められなかったが,午前5時15分,ベッドを離れ窓際で100ml程度吐血して倒れているのが発見され,心肺停止状態であった。蘇生措置が施されたが,同日午前7時05分に患者は死亡した。
病理解剖によって,直接の死因は,5cm程度の大きさの胃潰瘍からの大量出血であることが明らかになった。胃内には凝血塊を含む血液が約1000ml貯留し,十二指腸,空腸,回腸内容物は血性であった。結腸,直腸内にも血性内容物が見られ,潰瘍の口側後壁寄りの辺縁部に径1.0㎝大の潰瘍瘢痕が認められた。
患者の家族(妻及び子ら)が,主治医であったA医師,B医師及びC医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6068万0719円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①抗潰瘍薬の投与を怠った過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
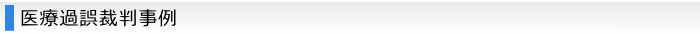
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
幽門側胃切除術後に発症した縫合不全の発見及び術後管理について,担当医師の過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第10209号 損害賠償請求事件
平成17年1月24日判決 確定
【手技,検査,入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和35年生,男性)は,平成12年2月28日,心窩部痛等を訴え,国が開設していた被告病院(大学病院)を受診し,胃癌と診断された。患者は,同年4月5日,胃癌の手術目的で被告病院外科に入院した。患者は,同月19日,担当医師(外科)の執刀により,ビルロート-Ⅰ法による幽門側胃切除術,胆嚢摘出術,リンパ節郭清術(D3)を受けた。胃切除部の吻合には,アルベルトーレンベルト縫合と称される吻合方式が用いられた。
患者は,術後,同病院において術後管理を受けていたが,残胃と十二指腸との縫合部に縫合不全を生じ,同年5月11日,同部位からの胃液等の内容物の漏出に起因して発症した胃十二指腸動脈瘤の破裂によって出血性ショック及び多臓器不全の状態に陥り,同月13日に死亡した。
患者の遺族らが,被告病院を開設していた国の地位を承継した国立大学法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億7280万0340円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者に縫合不全が発生したことについて,担当医師の吻合手技に過失があったか否か。 ②縫合不全発見の遅滞があったか否か
| ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
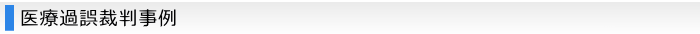
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
食道癌治療のため,胸腔鏡・腹腔鏡下食道亜全摘手術を受けた患者が,その後死亡したことについて,説明義務違反,術後に発生した胃管気管瘻に対する治療方法の選択についての過失等がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第7787号 損害賠償請求事件
平成16年10月29日判決 確定
【説明・問診義務,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(当時50代後半,男性)は,平成14年7月24日,甲病院(総合病院)のA医師(内科)から,食道癌の宣告を受けた。患者は,A医師らから,食道癌の治療法について説明を受けるとともに手術を勧められたが,化学放射線療法を希望し,A医師から被告病院(公立病院)の担当医師(消化器外科部長)を紹介してもらい,同医師から,セカンドオピニオンを聞くこととなった。
担当医師は,同年8月6日,患者とその家族に,化学放射線療法は,切除不能食道癌か,切除再建手術が行えない症例に対して行われている治療法であり,一部施設からは手術成績にほぼ匹敵する治療成績の報告がなされ最近注目されているものの,未だ症例数も少なく放射線照射後の遠隔期の合併症についての検討や他施設でのデータはほとんどないこと,患者には軽度の肺気腫があり,放射線による肺機能障害も予想されることを説明し,表在癌で術前検査では腹部に1つのリンパ節転移を認めるのみなので,手術で根治切除が可能であると判断されることを説明した。担当医師は,手術が適当であると考えられることを説明するとともに,手術を行うのであれば,患者に肺結核の既往及び軽度の肺気腫があり軽度の閉塞性の呼吸機能低下が認められるため,開胸開腹手術よりも術後の呼吸機能の低下が少なく再発のリスクも低い内視鏡下切除術が適当であることを説明したが,内視鏡下切除術の開胸開腹術等と比較した短所等については説明しなかった。
患者は,被告病院において,内視鏡下食道切除術を受けることを決め,同手術の予約を行った。同年9月6日,担当医師らは,患者とその家族に対して,手術の具体的な術式,合併症として肺炎,縫合不全及び胃管壊死等が考えられ,命にかかわることもあり得ること,気管切開を必要とする場合があること等を説明し,患者の同意を得た。
同月9日,担当医師らは,患者に対し,胸腔鏡・腹腔鏡下食道亜全摘手術を実施した。
同月17日,患者に,縫合不全に起因すると考えられる胃管気管瘻が発見されたことから担当医師らは,患者の家族に対して,挙上胃管と食道との吻合部と気管に交通があるため気道内への胆汁の流れ込みがあり,放置すると肺炎が必発なので手術が必要であること及びその術式について説明した後,挙上胃管切除気道修復術を実施したが,患者は,同年10月20日に死亡した。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計9494万9493円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①食道癌の治療方法について,説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
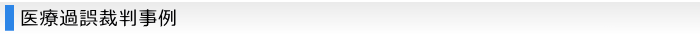
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
中心静脈栄養のチューブを抜去する際,チューブを固定する糸を切断しようとして誤ってチューブ自体を切断し,チューブを体内に残留させたことについて過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第8066号 損害賠償請求事件
平成16年7月12日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,手技】
<事案の概要>
患者(男性)は,平成11年8月19日,被告病院(総合病院)において,胃癌に対する幽門側胃切除術を受けた。同年9月9日以降,患者がイレウスを発症したため鎖骨下静脈から中心静脈栄養(IVH)が実施された。担当医師は,同月25日,患者のイレウスが軽快したためIVHを抜去しようとして,チューブを固定する糸を切断しようとして,誤ってチューブ自体を切断し,チューブを体内に残留させてしまった。チューブは,上大動脈を経由して右心房から右心室に達していたたため,切開された右鼠径部から挿入した心筋生検用カテーテルによってチューブを右心室内から右大腿静脈まで誘導し,鼠径部から体外に取り出された。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計730万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 70万円の慰謝料が認められたが,口頭弁論終結直前に被告が70万円を超える金員を弁済供託したため,患者の損害賠償請求権は消滅した。 | ||||
| 争 点 | ①チューブ切断に係る過失の有無 ②損害額及び損害賠償債務の消滅 | ||||
| 判 断 | ①鎖骨下静脈に切断されたチューブが残留すると,血流によってチューブが心臓内に至り,感染や血栓を生じる危険があるため,IVHを抜去するためチューブを皮膚に固定する糸をを切断する際は,誤ってチューブを切断することのないよう十分な注意を払いつつ,糸のみ切断すべき注意義務がある。担当医師には,注意義務に違反した過失がある。 ②担当医師の過失により,患者は,本来必要のない心臓カテーテル術を受けることとなり,退院が本来より20日余り遅れたが,心臓カテーテル術は成功し,チューブが心臓内に入ったことで患者の健康が害される事態には至らず,右鼠頚部の切開痕も殆ど分からない程度に治癒したことから,被告病院は,患者の精神的苦痛を慰謝するため70万円の慰謝料を支払うべきである。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
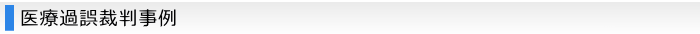
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝細胞癌の治療のために肝右葉切除手術を受けた患者が死亡したことについて,手術適応,手術の手技上の過失,説明義務違反等がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第21942号 損害賠償請求事件
平成16年5月31日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,適応,入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和28年生,男性)は,慢性肝炎等の既往があったが,平成12年6月5日,被告病院(総合病院)内科を受診し,肝腫瘍の疑いと診断された。同病院で6月14日に実施されたCT検査の結果,肝右葉に長径約10cmの巨大な腫瘍が肝外に突出する形で発育していることが明らかとなった。A医師(内科)は,肝細胞癌である可能性が高いと判断し,患者とその妻に対し,肝臓に10cmほどの腫瘍ができており,内科的治療法(TAI,TAE,PEI)もあるが,腫瘍が大きいために治療効果が得られにくく,第1選択は手術であることなどを説明し,患者の妻にのみ,進行癌であることを説明した。患者の妻は,A医師に,患者本人には癌の告知をしないように依頼した。
6月20日,腹部血管造影検査が実施され,肝細胞癌と診断された。A医師は,患者が被告病院内科に入院してから,被告病院外科のB医師やC医師らと連絡を取り合い,手術適応について相談していたが,インドシアニングリーン(ICG)検査(肝臓の異物排泄機能を調べる検査)の結果について兵庫医大方式の計算式を用いて計算したところ,手術適応があると考えられたことから,6月28日,患者を外科に転科させた。被告病院外科のB医師,C医師らも,兵庫医大方式の計算式を用いて手術適応があることを確認し,7月6日に肝右葉切除術を実施することとした。B医師は,手術前日の7月5日,患者と患者の妻に対して術前説明を行い,本件腫瘍が肝蔵癌であることを告知した。
7月6日午後2時ころから,B医師,C医師らによって患者に対し肝右葉切除術が開始された。手術では,ベンツ型切開法が採用され,B医師らは,患者の肝臓を周囲から剥離する作業を進めたが,肝静脈周囲を剥離したところ,肝腫瘍が肝静脈の根部に膨張するように被さっていて右肝静脈と中肝静脈の分岐部分が確認できず,肝実質内へ向かう部分を剥離しようとしたところ,腫瘍を露出しそうになったため,このまま肝静脈の処理を進めると,肝静脈を損傷して大出血を招く危険があると考え,肝静脈の処理を断念し,肝実質の切離を先行し,午後8時ころ,手術は終了した。
術後,7月10日午後6時ころから,患者の体温は38度を超えるようになり,同月12日には,37度台半ばを推移し,白血球数が1万1900に増加した。B医師は,感染巣は不明であったものの,腸管から細菌が入り込むなどして何らかの感染が生じている可能性を考え,それまで投与していたセフメタゾン(抗生剤)に代え,予防的に,カルベニン(抗生剤),ダラシン(抗生剤)の投与を開始した。7月17日,患者に頻呼吸が現れ,白血球数が2万を超え,手術創に汚れが見られたため,B医師らは,ジフルカン(抗真菌薬)の投与を開始した。同日,B医師らは,患者に対し,正中創ドレナージを行い,1400g近い腹水の排出をみたが膿性腹水は認められなかった。7月19日,患者の手術創部の膿の培養検査の結果,MRSAが検出されたため,B医師らは,患者に対して,テイコプラニン(抗生剤)の投与を開始した。B医師らが抗生剤としてテイコプラニンを選択したのは,患者に腎障害が見られていたため,腎毒性が少ないテイコプラニンが有効と考えたためであった。7月21日,患者の喀痰培養検査の結果,MRSAが検出され,B医師らは,患者に対して,パンコマイシンの吸入を開始した。7月25日,持続援助式血液ろ過透析が開始され7月26日から,パンコマイシンの投与が開始されたが,患者は,同月30日午後7時30分死亡した。
患者の家族(妻と子)は.患者に手術適応がなかったにもかかわらず,担当医師らが手術を実施したなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7000万円(8197万3209円のうち一部請求) | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 説明義務違反の有無 | ||||
| 判 断 | ①手術適応の有無
| ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
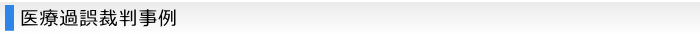
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
早期胃癌の診断直後に病名を告知しなかったことが医師の裁量の範囲内とされ,医師の説明義務違反が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第5563号 損害賠償請求事件
平成16年4月26日判決 控訴・控訴取下
【説明・問診義務,検査】
<事案の概要>
患者(男性)は,平成11年4月20日,被告病院(総合病院)で,胃内視鏡検査を受けた。担当医師Aは,びらん性胃炎の印象をもち,病理組織検査の結果,異型性グループⅢ(良性と悪性の境界領域の病変)であったため経過観察とした。
A医師は,同年6月22日,患者に対し,再度,胃内視鏡検査を実施し,萎縮性胃変,表面陥凹型又は表面隆起型+表面陥凹型の早期胃癌等を疑い,病理組織検査を依頼したが,患者の胃の病変が悪性である可能性が大きいと認識していた。同年7月にA医師と主治医を交替したB医師は,病理組織検査の結果,グループV(癌)であったことから,表面陥凹型の胃癌と診断した上,同年7月22日,患者に病名を告げないまま,精査加療と場合によっては手術を行うことを目的として入院を勧めた。
被告病院内科部長は,病名が分からないまま手術を勧められたとの患者の苦情を伝え聞き,同月24日,患者に対し,早期胃癌であることを告知し,超音波内視鏡検査(EUS)実施のため入院を指示した。
患者は,同年8月2日,EUSを受け,検査の結果,早期胃癌,予測深達度SM2(粘膜組織への浸潤,粘膜筋板からO.5㎜以上)と診断された。B医師らは,患者に対し,早期胃癌で2層までの浸潤が疑われること,1層までの浸潤なら内視鏡的粘膜切除(EMR)が可能であること,2層まで浸潤している場合リンパ節転移が10%見られ,SM2の場合20%になること,治療方法としてEMRで断端を調べ,癌組織が取り切れない場合,外科的手術をする方法と最初から外科的手術をする方法があること,深達度がSMになればリンパ節転移も十分考えなければならず,その場合死につながるからよく考える必要があること等を説明した。
患者は,被告病院外科部長のセカンド・オピニオンを得るため,同月6日,同部長の診察を受け,早期胃癌であること,病変が粘膜のみにとどまれば転移はないが,患者の場合,粘膜下層にまで至っているため,リンパ節転移の可能性があるとの説明を受け,幽門側胃切除術を受けることとした。転移の有無を確認するため,同年8月7日,胸部CT検査が,同月10日,肝臓の超音波検査が実施されたが,転移の所見は認められなかった。患者は,同月19日,幽門側胃切除術を受け,胃の約5分の3を切除されたが,その後,転移,再発は見られない。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計65万2450円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 説明義務違反の有無 | ||||
| 判 断 | B医師が,平成11年7月22日,胃癌と診断した際,患者に直ちに病名を告知しなかったのは,癌の告知については,患者の性格や家族の意向等を踏まえる必要があり,わずか2回接したに過ぎない患者への告知に慎重な姿勢をとったからであり,こうした判断は医師の裁量の範囲内であり相当である。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
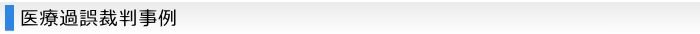
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝動脈再建手術を血管外科医ではなく消化器外科医が実施したことに過失はなく肝動脈再建ないし修復後,ドプラー超音波検査を行わず抗凝固療法を行いながら経過観察しことにも過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第3654号 損害賠償請求事件
平成16年2月25日判決
【手技,検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和10年生,男性)は,平成9年,被告病院(大学病院)外科に入院し,大腸癌の手術を受けた。患者は,退院後,外来通院していたが,平成10年2月4日転移性肝癌が発見され,同月12日,被告病院に入院し,同年3月5日,担当医師(消化器外科)らの執刀で,肝左葉切除術を受けた(本件手術)。担当医師は,術中,癒着剥離の際,腸管の一部と右肝動脈を損傷したが,これらを修復し,肝左葉を切除し手術を終了した。
その後,患者は,残肝に虚血性変化を生じ,多発性肝膿瘍を起こして,同年8月2日,被告病院において,肝不全等により死亡した。
患者の家族(妻及び子ら)は,担当医師に,①右肝動脈損傷は右肝動脈の完全離断であり,かかる損傷に過失がある,患者の術後の状態の悪化は肝動脈再建(修復)後に肝動脈血栓症が発症したためである,②肝動脈修復を血管外科医に担当させなかった過失,又は③肝動脈再建(修復)についての手技上の過失,④術後ドプラー超音波検査で、右肝動脈に血流があるか否かを継続的に検査し,血栓閉塞が疑われれば,直ちに血管造影を行い,動脈再建を行って血栓を除去すべきであったのに怠った過失があったとして,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4310万0240円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①肝左葉切除術において右肝動脈を損傷させた過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
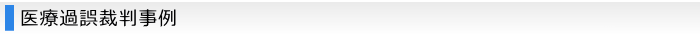
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
胃癌手術後の注射によってC型肝炎ウイルスに感染したと主張して慰謝料請求したところ,注射によってC型肝炎ウイルスに感染したとは認められないとの理由で請求が棄却されたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第5496号 損害賠償請求事件
平成16年2月5日判決
【入院管理】
<事案の概要>
患者(昭和9年生,男性)は,平成3年5月7日,被告病院(大学病院)に入院し,同月16日,胃癌の手術(本件手術)を受け,同年6月12日に退院した。
患者が,C型肝炎ウイルス(HCV)抗体検査(第2世代による。基準値は1.00)を受けたところ,平成6年3月14日は1.09,同年4月11日は1.24,平成14年12月3日は0.97,平成15年3月10日は0.86,同年6月24日は0.73で,平成6年3月14日及び同年4月11日は基準値を超えていた。
HCV-RNA検査では,平成14年12月10日のHCV-RNA定性PCR検査及び平成15年3月10日のHCV-RNAモニタ一定量検査で,いずれも陰性であった。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,被告病院で受けた本件手術直後の注射によって,C型肝炎ウイルスに感染したとして,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 4675万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 被告病院で受けた本件手術直後の注射によって患者がC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
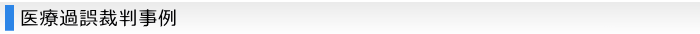
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者の家族が,患者に対する癌の告知を望まず,かつ医師に対しその意思を明示している場合,医師が患者に対し,癌の告知をしなかったこと及び開胸手術を実施する際に肋骨切除の手技を採用することについて,医師が患者に説明をしなかったことにつき過失がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第2297号 損害賠償請求事件
平成16年1月30日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法,手術適応,時期】
<事案の概要>
患者(昭和2年生,男性)は,平成3年,人間ドックで食道下部の異変を指摘され,精査目的で同年7月3日,被告病院(国立病院)の消化器科を受診した。
被告病院担当医師(消化器外科)は,同月11日,内視鏡検査及び細胞診断を行ったところ,患者の食道中部から下部の食道にびらん及び発赤の散在が認められ,その異状部分から採取した組織に癌細胞が発見されたため,食道癌の確定診断をした。同年8月20日,被告病院が2回目の内視鏡検査及び細胞診断を行ったところ,癌細胞は発見されなかったが,被告病院は当初の確定診断を維持した。
被告病院は,患者の妻に対し、食道癌の診断結果を伝えたものの,妻の要請で患者本人に対しては,癌の告知をせず,食道潰瘍であると告げた。
担当医師は,同月27日,患者に対し,胸部食道全摘手術を施行し,その際,開胸のため,右第5肋骨及び第6肋骨を1cmほど部分的に取り除いた。
被告病院が,術後,切除組織の病理組織診断を行ったところ,癌細胞は発見されなかった。
患者は,そもそも食道癌はなく本件手術は不要であったこと,肋骨の切除は不要であったこと,患者に対し癌の告知をしなかったこと,本件手術施行後に手術部に激しい痛みの後遺症が生じることについて説明をしなかったことなどを主張し,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計5000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①本件手術の必要性
②2本の肋骨を部分的に切除したことの許容性 ③説明義務違反の有無
| ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
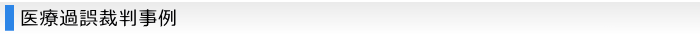
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
進行性肝門部胆管癌の再発患者に対し,化学療法を行わなかったことに過失はなく又,吐血を訴えて入院した後の治療にも過失は認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第16458号 損害賠償請求事件
平成15年6月27日判決
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(男性)は,平成5年,大腸癌の手術を受け,平成11年9月9日,被告病院(大学病院)において,進行性肝門部胆管癌により肝門部肝臓切除を伴う胆管切除術を受けた。
患者は,平成12年4月初旬ころから黄疸が出現したため,同月13日,被告病院に入院した。胆管癌の再発が疑われたことから,肝門部の胆管閉塞の改善を目的として,患者に対し,胆管にステントを挿入する手術が実施された。
同年8月8日,患者は,吐血をして被告病院に入院し,胃角部前壁に拍動性の出血を伴う潰瘍が認められ,胃下部及び十二指腸上部には狭窄が認められ,十二指腸への癌の浸潤が疑われたことから,癌性腹膜炎状態と診断された。
患者は、その後退院し,自宅で静養していたが,同年10月3日10時30分,吐血して被告病院に入院した(本件入院)。上部内視鏡検査の結果,胃内に黒灰色の貯留液が大量に存していたものの,明らかな新鮮出血は認められなかったが,同日15時から酸素投与と輸血を開始されるなどしたが,輸血の滴下不良が認められ同日19時ころ輸血の針と輸血ルートが変更された。
患者は,同日20時40分ころから呼名反応が鈍くなり,22時20分,呼吸停止,心停止となり,心臓マッサージが行われたが回復せず,翌4日0時28分死亡した。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3600万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①平成12年4月13日の段階で,患者の胆管癌に対し化学療法を行わなかった過失があるか否か ②本件入院時に,患者の著しい肝障害及び肝不全に対して適切な治療を行わなかった過失があるか否か ③患者に対する輸血の滴下不良を放置した過失があるか否か ④被告病院の過失と患者の死亡との因果関係の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
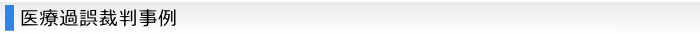
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が当初入院した際,絞扼性イレウスであるとの確定的診断を下すことができず,翌日確定診断がついた後,緊急開腹手術に踏み切ったことに過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13146号 損害賠償請求事件
平成15年2月28日判決
【説明義務・問診義務,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和48年生,女性)は,出生後,プラダーウィリー症候群(乳幼児期に筋無緊張症等が認められ,その後筋無緊張症の消失と並行して,漸次肥満及び知能発達遅延等が出現する疾患)と診断され,平成4年6月8日,治療目的で被告病院(大学病院)外科に入院し,同月18日,プラダーウィリー症候群改善のための胃亜全摘手術を受けた。
患者は,術後下痢等の症状が続いたが,平成5年10月29日9時30分ころ,腹痛のため,職場から甲病院へ搬送され,同日12時過ぎ,救急車で被告病院外科へ搬送された。
患者は、被告病院へ入院したものの,患者本人の希望によりいったん帰宅した。
しかし,腹痛が再発し,患者は,同日22時30分ころ,被告病院外科に再入院した。
同月30日18時過ぎ,患者の容態が急変したため,被告病院外科において,翌31日3時45分,緊急イレウス手術が行われ,その結果,絞扼性イレウスであったことが判明し,小腸を約1m50cm切除するなどの処置が行われた。
患者は,術後,被告病院外科において術後管理が行われていたが,平成6年2月24日,呼吸状態の悪化を引き金に多臓器不全を併発して死亡した。
患者の父が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①胃亜全摘手術についての説明義務違反の有無 ②緊急イレウス手術の時期の適否 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
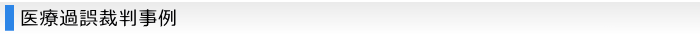
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
膵臓癌の患者に対し,二期的膵空腸吻合や膵胃吻合ではなく膵空腸吻合を実施したことに過失はなく,その他,縫合不全を発症させた過失,術後管理の過失,MRSA感染対応の過失等のいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第13920号 損害賠償請求事件
平成15年1月31日判決
【説明義務・問診義務,手技,入院管理,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和22年生,男性)は,平成7年2月,人間ドックにおいて膵臓癌の疑いがあると指摘され,精査目的で同年7月7日被告病院(癌専門病院)を受診した。
担当医師(外科)らは,膵臓細胞腫の可能性も否定できないが,通常型膵管癌であることを前提に治療計画を立て,全胃幽門輪温存膵頭十二指腸切除術(本件手術)を行うこととし,患者とその妻に対し,同月21日及び24日,手術説明をした。
同月25日,患者に対し、本件手術が実施されたが,患者は,本件手術後,MRSA腸炎に罹患し,その影響もあり縫合不全を起こした。
担当医師らは,同月29日には,患者に膵臓の離断面から膵液のみが漏出するマイナーな縫合不全が起こっていることを認識し,同年8月8日,腸管が解放され,腸内溶液が腹腔内に漏出し,膵液が活性化する状態であるメジャーな縫合不全を疑い,同月10日,メジャーな縫合不全を認識した。この間,ドレーン管理により膿や壊死物質の洗浄が試みられたが,発熱が続いていたため,同月29日,開創ドレナージを行ったものの,患者が,同年9月21日に動脈出血を起こしたため,緊急開腹手術が行われた。
しかし,手術による出血のコントロールは不能であり,血管造影による動脈塞栓術が行われ,開放創とされたが,同月3日に門脈閉塞が起こり,同月4日に門脈内血栓除去の開腹手術が行われ,その後も動脈出血を繰り返し,同年11月27日,患者は多臓器不全により死亡した。
本件手術後の病理組織検査の結果,患者は膵島細胞癌であったことが判明した。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億3080万7132円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①本件手術についての説明義務違反の有無 ②術式選択における過誤の有無 ③縫合不全を起こしたことについて,本件手術手技上,注意義務違反があったか否か ④適切な術後管理を行う注意義務違反の有無 ⑤本件手術前に,膵島細胞癌と確定診断すべきであったか否か。 ⑥被告病院において,MRSA感染対応に不備があったか。 ⑦メジャーな縫合不全に対し,ソマトスタチンを投与すべきか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
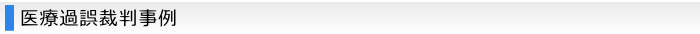
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
大腸癌及び肝臓癌の同時切除術を行ったことに過失はなく,説明義務違反も認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第6841号 損害賠償請求事件
平成14年8月28日判決
【説明・問診義務,適応】
<事案の概要>
患者(死亡時64歳,男性)は,平成11年3月,甲病院において肝臓癌の疑いがあると診断され,同年4月20日,精査目的で,被告病院を受診した。
被告病院の医師は,腹部エコー,上腹部内視鏡の各検査,造影CT検査の結果,アルコール性肝硬変,肝細胞癌の疑いが強いと判断し,精査加療目的で,患者は,同年5月27日,被告病院に入院した。
被告病院の内科医師は,肝臓病変のうち,右葉前区域上部部分(S8),右葉後区域下部部分(S6)の生検の結果,S8には,中分化型肝細胞癌が見つかり,S6には,癌とは断定できないが前癌病変である腺腫瘍過形成が認められたため,同日から6月3日にかけて経皮的エタノール注入療法(PEIT)を3回施行した。
同年5月28日,便潜血検査で陽性となったため,被告病院消化器外科医師(担当医師)が同年6月2日,患者に対し大腸内視鏡検査を実施したところ,S状結腸に2個,上行結腸にも2個のポリープが発見され,S状結腸部分のポリープはポリペクトミーを施行したが,上行結腸部分のポリープは直径が大きかったため,ポリペクトミーができず,生検の結果,高分化腺癌であり,粘膜下層に達し,リンパ管を浸潤していることが判明した。その後,同部分をポリペクトミーして,ポリープの大部分を切除した。予後を観察するため,同年7月6日,ポリペクトミー及び大腸病変の精査を行うこととして,患者は,同年6月17日,いったん被告病院を退院した。
患者は,同年7月5日,被告病院に入院し,同月6日,大腸内視鏡検査が実施された。検査の結果,上行結腸の病変は肉眼的にはほぼ切除されていたが,肉眼では見えない癌組織が残存していないか精査するため,切除部分の生検が実施された。
担当医師は,患者とその妻に対し,上行結腸のポリープは切除できているが,組織検査の結果,大腸癌は粘膜下層まで浸潤しており,リンパ管を通じて転移している可能性が10%程度認められるから,治療のため開腹して大腸を切除し,リンパ節を郭清する手術を行うのが適当であること,又,肝細胞癌についても,外科的治療として肝切除を行うほうがよいなどと説明した。患者は,通院して経過観察をすることとなり,同年7月7日に退院した。
担当医師は,同年8月6日,来院した患者に対し,大腸癌と肝細胞癌について外科手術(本件手術)を受けることを勧め,患者はこれに同意して,同月31日,被告病院へ3回目の入院をした。
担当医師は,同年9月8日,患者に対し,大腸癌及び肝臓癌の同時切除術を実施した。
患者は,手術当日ICUで経過観察し,翌9日一般病室に転室したが,胸水貯留,腎機能低下,肝機能低下の症状が認められ,血液検査の結果,CRP,白血球数の上昇が認められ,体温も上昇するなど,感染症状が認められたことから,同月14日にはICUに転室して管理が行われたが,同月28日,多臓器不全により死亡した。
患者の妻が,被告病院を開設する地方公共団体に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①大腸切除術と同時に肝切除術を行ったことが担当医師の過失ないし義務違反といえるか否か。 ②説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
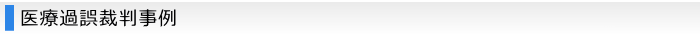
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
進行性胃癌の手術後に患者が死亡したことについて,術前及び術後の説明義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第8000号 損害賠償請求事件
平成14年6月24日判決
【説明義務・問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和13年生,男性)は,平成11年6月28日,被告病院(大学病院)を受診し、同年9月6日,胃癌全摘,脾全摘,肝部分切除,リンパ節郭清手術(本件手術)を受けたが,その後,転移性肺癌により,同年12月23日に死亡した。
患者の妻及び2人の子どもらは,被告病院を開設する法人に対し,
①本件のような進行性胃癌の場合,根治手術がほとんど不可能であり,予後は不良であるのだから,担当医師らは,本件手術に先立って,早期に再発することが多く,5年生存率が10%程度であることや,化学療法等の有効な内科的治療法の有無,経過観察の有効性などについて説明すべきであったにもかかわらずこれを怠った(手術前の説明義務違反),
②担当医師らは,本件手術後の予後について楽観的なことを告げ,患者に対して,過剰な期待を抱かせ,結果的にわずか2か月後に再発したことについて,納得させるための説明・弁明を行わなかった(手術後の説明・弁明義務違反)などと主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計560万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①手術前の説明義務違反の有無 ②手術後の説明・弁明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
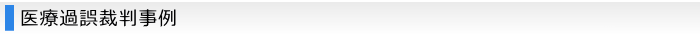
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
大腸癌の手術後に患者が汎発性腹膜炎を生じたことについて,担当医師の行った縫合措置や術後管理に過失はないとされたケース
大阪地方裁判所 平成11年(ワ)第4273号 損害賠償請求事件
平成14年5月22日判決
【手技,入院管理】
<事案の概要>
患者(女性)は,被告病院において,大腸癌と診断され,平成8年8月26日,S状結腸切除術を受けた。患者は,同月29日,熱発し,ドレーンからの排液が胆汁様(緑色)に汚濁していたことから,A医師がガストログラフィンによる注腸検査等を実施したところ,ピンホール大の縫合不全が認められた。
A医師が,抗生物質を投与するなどしたところ,次第に解熱して,血圧も安定し,ドレーンからの排液も漿液性のものへと薄くなったが,同年8月30日ころから患者に洞性頻脈,過呼吸,精神不穏状態が見られるようになった。
A医師は,同月31日,患者に対し,腹部レントゲン検査を実施したが,汎発性腹膜炎や膿瘍形成による麻痺性イレウスを示す所見は認められなかった。
患者は,洞性頻脈,過呼吸,精神不穏状態が継続していたが,同年9月2日,高熱を発し,その後呼吸不全となった。
A医師は,腹部膿瘍等を確認するため,試験的腹腔内穿刺を実施したが,排液は正常であったことから,腹部膿瘍と併せて,開腹手術に基づく甲状腺クリーゼの可能性も考え,腹部症状のチェックのため血液細菌培養等の検査を行うとともに,甲状腺機能を確認する検査を実施した。同日夜から翌3日早朝にかけて,患者の血圧が80〜50に低下したため,患者は,甲病院に転送され,緊急開腹手術が実施されたところ,S状結腸吻合部に縫合不全が発見され,腹腔内膿瘍,汎発性腹膜炎を併発していることが判明した。
甲病院のB医師は,縫合不全を発症した吻合部を除去するとともに,人工肛門を設けるなどの手術を施行した。
患者は,被告病院の開設者に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計 1億4489万6017円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①A医師は,吻合部の血流が不十分であったのにこれを確認せずに吻合したことにより,縫合不全を引き起こしたか否か。 ②A医師は,術後管理を怠って縫合不全を悪化させたか否か。 ③上記①,②の過失と患者の両下肢に生じた著しい運動障害との間の因果関係の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
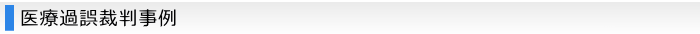
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
腹部内のカテーテルの残置について慰謝料の支払義務を肯定したケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第973号 損害賠償請求事件
平成15年11月28日判決
【損害論】
<事案の概要>
患者(昭和16年生,男性)は,平成11年3月31日,急性膵炎のため,被告病院(総合病院)に入院し,同年4月8日,後腹膜腔膿瘍のドレナージ術(本件手術)を受けた。担当医師は,手術の際、超音波ガイド下に膿瘍の穿刺を行い,ピッグテールカテーテルを留置した。
平成13年8月7日,患者は,慢性膵炎と糖尿病の精査目的で,被告病院に入院した。腹部X線検査で,患者の左腎周囲腔に,1.5cmから2.0㎝の糸状のもの(本件異物)が発見された。被告病院は,本件異物は,本件手術時に使用したピッグテールカテーテルの一部が残置されたものであり,被告病院に責任があることを認めた。
しかし,患者と被告病院との間で,本件異物の除去手術の必要性,慰謝料額で話し合いができなかったことから,患者は,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
当初,患者は,本件異物除去手術の手術代金及びそれに伴う慰謝料を請求していたが,本件異物の除去手術を当面行わないこととしたため,この部分の請求を撤回している。
| 請求金額 | 110万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額30万円) | ||||
| 争 点 | 患者の腹部に本件異物を残置したことにより,患者が被った精神的苦痛に対する慰謝料額 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 25万円 | |||
| ②弁護士費用 | 5万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
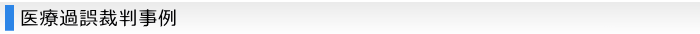
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝癌・肝部分切除術及ぴ胆のう摘出術において,術後出血の徴候となる所見を看過し術後出血の診断及び再開腹止血術の実施が遅れた過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第13471号 損害賠償請求事件
平成15年9月29日判決
【説明義務、,問診義務,手技,入院管理,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和4年生,男性)は,平成9年,定期健康診断で,C型肝炎ウイルスに感染し,肝硬変を発症していることが判明した。以後,患者は,被告病院(総合病院)において,インターフェロン等の治療とともに,血液生化学検査及び画像検査を定期的に受けていた。患者は,平成12年11月及び12月の検査で,肝細胞癌と診断され,同月被告病院内科に入院した。
肝癌に対する治療として,当初はPEIT(経皮的エタノール注入療法)が予定されたが,カンファレンス等の結果,治療法を肝部分切除術へ変更することになり,患者は外科へ転棟となった。同月18日,担当医師(外科)が執刀し,患者に対し,肝部分切除術が実施された。肝部分切除術に際しては,胆のうも摘出するのが一般である上,患者の胆のうに胆石が認められたことから,胆のう摘出術も併せて行われた。胆のう底部を肝床部から剥離するに際し,肝硬変による出血傾向などのため,数百ミリリットルの出血が生じたが,担当医師は,結紮,電気メス,圧迫などによって止血し,閉腹した。
患者は、同日から翌19日にかけて,血圧低下,尿量減少を生じ,昇圧剤や利尿剤が投与されたが改善せず,同日午前の血液検査でヘモグロビンの低下等が認められたが担当医師はドレーンからの排液がそれほど認められなかったこともあり,術後出血を疑わなかった。
同日午後,ドレーンから継続的に血性排液があったため,術後出血と診断され,同日夜,再開腹止血術が行われた。患者は,止血術後も肝不全等の重篤な状態が続き,平成13年1月28日,腎不全及び肝不全を直接死因として死亡した。
患者の家族が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7964万2716円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計3754万4357円) | ||||
| 争 点 | ①肝部分切除術の適応があったか否か ②胆のう摘出術の適応があったかいなか ③胆のう摘出術実施時の胆のう剥離手技,止血処置に不適切な点があったか否か ④術後管理において,術後出血の徴候となる所見を看過し,術後出血の診断及び再開腹止血術の実施を早期に行うことができなかった過失があるか。 ⑤術後管理における過失と患者の死亡との間の因果関係の有無 ⑥肝部分切除術及び胆のう摘出術実施前の説明義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費 | 32万9780円 | |||
| ②葬儀費用等 | 100万0000円 | ||||
| ③逸失利益 | 781万4577円 | ||||
| ④死亡等慰謝料 | 2000万0000円 | ||||
| ⑤遺族固有の慰謝料 | 500万0000円 | ||||
| ⑥弁護士費用 | 340万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
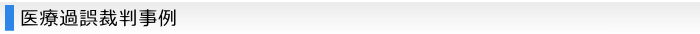
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
虫垂切除術に際し,虫垂間膜の十分な結紮が行われたものとはいえないとして手技上の過失を認め,切除術後の開腹止血手術とその後に発症したイレウスとの相当因果関係を認めたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第13264号 損害賠償請求事件
平成15年6月2日判決
【手技上の過失,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和39年生,男性)は,平成5年3月18日,急性虫垂炎のため被告病院(総合病院)の外科に入院し,同日午後9時15分から,虫垂切除手術を受けた。
担当医師(外科勤務医)は,腰椎麻酔下,臍と右腸骨前上棘とを結ぶ線の外側から3分の1の点を中心として皮膚に長さ約5cmの斜切開を加え,交差切開の方法で腹壁を切開し,虫垂を検索し,虫垂間膜(虫垂に付着し,その中を虫垂動脈が走行している膜)を結紮して切り離し,虫垂を根部で結紮し,そこから数mm末梢部で虫垂を切除し,残った虫垂断端を盲腸内へ埋没させて巾着縫合し,結紮部位からの出血が見られないことを肉眼で確認した上閉腹して,午後9時36分手術を終了した。
手術から3日後の3月21日,腹腔内出血が判明したため,患者に対し,緊急開腹止血手術が実施された。
担当医師が臍の上下を長さ約20cmにわたり正中切開で開腹したところ,結紮した虫垂間膜の断端が結紮部位を挟んで上下に裂けて出血し,凝血塊が付着している状態が認められ,出血部位を結紮して止血し,閉腹して手術を終了した。
患者は,4月3日に被告病院を退院した。
患者は,平成5年4月から平成11年3月までに11回,開腹手術に起因する癒着性イレウス(腸閉塞)を発症して入院を繰り返した。その間,平成6年4月と平成11年3月には,他院において開腹によるイレウス解除手術を受けている。
患者は,虫垂切除手術において十分な結紮を行わず,腹腔内出血の早期発見も怠ったと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2562万1630円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計824万5330円) | ||||
| 争 点 | ①虫垂間膜の結紮が不十分だったか否か ②開腹止血手術とイレウスとの因果関係の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 700万0000円 | |||
| ②入院治療費 | 52万1630円 | ||||
| ③通院交通費 | 2万3700円 | ||||
| ④弁護士費用 | 70万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
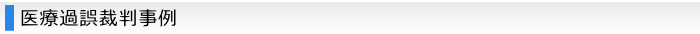
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝硬変の既往症を有し,血中アンモニア値上昇,意識状態悪化等の所見があった患者に対し,適切な検査,治療等を怠るなどした過失があり,これによる患者の生存可能性の侵害が認められたケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第3016号 損害賠償請求事件
平成15年5月28日判決
【検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和15年生,男性)は,肝硬変,糖尿病,食道静脈瘤等により,平成8年から平成10年にかけて,被告病院に断続的に入通院をしていた。
患者は,タール便や吐血があったことから,同年10月25日23時ころ,甲病院を受診し,翌26日0時34分,被告病院の救急救命センターへ入院した。
患者は,同センターにおいて,食道動脈瘤が認められるが,現在は止血している,再出血をすれば重篤な状態になるなどの診断を受け,同日3時ころ,被告病院第一外科へ転科した。同日11時30分、主治医がA医師(当時2年目の研修医)らに決定したた。同日の患者の主な検査結果等は以下のとおりである。
1時05分 血液pH7.326[HC03]10.3
3時 意識レベルⅠ-2
8時30分 血中アンモニア値158
11時30分 血液pH7.451[HC03]12.4
15時 意識レベルⅡ-10
17時 意識レベルⅢ-200
17時35分 血中アンモニア値503
20時40分 血中アンモニア値490 血液pH7.747[HC03-]19.0
4時から23時までの尿量 計943ml
患者は,同日17時ころ,呼びかけに対して返答がない状態になり,翌27日1時ころ心拍数が低下して呼吸停止状態に陥り,同日4時10分に死亡した。
患者の遺族(妻及ぴ子ら)が,被告病院を開設している法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億0485万8369円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計800万円) | ||||
| 争 点 | ①検査義務及び治療義務の不履行の有無 ②治療措置が不十分又は不適切なものであったか否か ③被告病院の過失と患者の死亡等との因果関係の有無 ④損害額 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 700万円 | |||
| ②弁護士費用 | 100万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
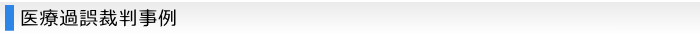
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
胃癌に対する手術後,手術部位の縫合不全による腹膜炎等の可能性を疑って諸検査を行い,膿瘍を発見して排膿を実施すべきであったと認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第9485号 損害賠償請求事件
平成15年3月31日判決
【検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和10年生,男性)は,胃の不調を覚え,かかりつけの医師の紹介で,平成10年9月4日,被告病院の内科外来を受診した。検査の結果、胃癌(未分化型腺癌)と診断され,同月14日,患者は,被告病院に入院し,同月24日,胃全摘出術,膵尾部脾合併切除,胆嚢摘出術及び食道空腸吻合術(本件手術)を受けた。手術の際,腹腔内からのドレナージのため,右及び左ドレーン(本件ドレーン)が留置されたが,同年10月2日には,右ドレーンが抜去され,同月5日には,左ドレーンが抜去された。
同月9日午後2時ころ,患者に39度1分の発熱があったため,担当医師は,カテーテル熱を疑い,TPN(中心静脈カテーテル)を抜去した。
担当医師が,同月12日,患者に対し,腹部超音波検査,CT検査を実施したところ,左横隔膜下に液体の貯留が認められたので,左横隔膜下膿瘍を疑い抗生剤の投与を開始した。同月16日,腹部超音波で,依然として左横隔膜下に貯留物が認められたため,超音波ガイド下に穿刺ドレナージ術を実施したところ,膿の排出が認められ,左横隔膜下膿瘍と診断された。
同月19日,担当医師は,腹部CT検査等の結果,汎発性腹膜炎と診断し,開腹ドレナージ術を実施したところ,食道空腸吻合部に縫合不全が確認された。
患者は,同年12月18日に被告病院を退院したが,平成11年1月19日に被告病院に再入院し,同年2月5日に開腹手術を受け,癌性腹膜炎と診断され,同年5月16日,被告病院を退院し,同年7月17日,自宅で死亡した。
患者の妻は,患者が入院中に汎発性腹膜炎を発症して長期の入院を余儀なくされ精神的苦痛を被ったのは,担当医師が,術後管理等において適切な措置を講じなかったためあると主張し,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1100万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 110万円) | ||||
| 争 点 | ①担当医師は,本件ドレーン抜去時において,縫合不全による腹膜炎を疑い,予防的ドレナージのために,本件ドレーンの留置を継続すべきであったか否か。 ②仮に,本件ドレーンを抜去したことが適切だったとしても,担当医師は,発熱が認められた平成10年10月7日か,39度台の発熱が認められた同月9日,もしくは遅くともその熱が継続していた同月11日までには,縫合不全を疑って,胸部レントゲン,腹部エコー,CT,吻合部造影等により左横隔膜下の膿瘍の有無や左胸水の有無の確認,血液凝固能,血液培養及び各臓器機能検査を行うべきであり,検査の結果,膿瘍が見つかった場合,膿瘍局所に対する適切なドレナージと抗生物質投与などの全身治療をすべきであったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 100万円 | |||
| ②弁護士費用 | 10万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
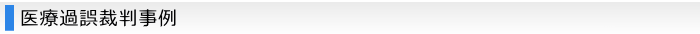
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が飲み込んだ胃内の義歯をスネアにより取り出す際,医師がこれを食道壁に食い込ませた過失があり,そのような場合,緊急開腹手術が必要となることを説明しておくべきであったのにしなかった説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第7414号 損害賠償請求事件
平成14年4月26日判決
【説明・問診義務,手技】
<事案の概要>
患者(男性)は,平成10年4月18日,夕食中に上顎左部分の義歯を飲み込んでしまい,同月20日の午後から胃に不快感を感じるようになったため,同月21日10時40分ころ被告病院(総合病院)外科外来を受診した。外科部長であったA医師は,患者に対し,患者の胸部を撮影したレントゲン写真を示し,内視鏡による操作(内視鏡的処置)によって義歯を摘出する旨告げたが,内視鏡的処置で義歯を摘出できなかった場合に開腹手術が必要となること及び内視鏡的処置の際,緊急手術が必要となることがある旨を患者に説明しなかった。
A医師は,B医師(10年程度の経験者)に対し,患者の義歯を内視鏡により摘出するよう依頼し,同人とC医師(3年程度の経験者)が,当初は異物鉗子を使い,その後スネアを使って内視鏡的処置を繰り返し試みたが,義歯を摘出することができず,スネアに義歯を引っ掛けて義歯を胃から食道に引いてくる際,義歯のブリッジを食道壁に食い込ませた。A医師は,報告を受けて,患者に対して開腹手術を実施することを指示し,B医師が開腹手術を実施して,義歯,スネア及びワイヤを摘出した。
患者が,被告病院を開設する地方公共団体に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計172万7760円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計113万円) | ||||
| 争 点 | ①内視鏡的処置を行うについての説明義務違反の有無 ②担当医師らが内視鏡的処置に際し操作器具を食道壁に食い込ませたか。担当医師らが操作器具ないし義歯のブリッジを食道壁に食い込ませたのは過失と評価されるか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 80万円 | |||
| ②証拠保全費用 | 13万円 | ||||
| ③弁護士費用 | 20万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
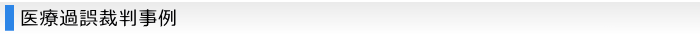
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
術後,高カロリー輸液を投与されていた患者が,ウェルニッケ脳症を発症した場合において,医師にビタミンB1の投与を怠った過失があるとされたケース
東京地方裁判所 平成10年(ワ)第25812号 損害賠償請求事件
平成14年1月16日判決
【入院管理,因果関係】
<事案の概要>
患者(大正4年生,男性)は,平成8年9月,被告病院(国立病院)消化器外科において,上行結腸癌の疑いとS状結腸の穿孔のため,上行結腸とS状結腸穿孔部を切除する手術を受けた。
患者は,術後8日まで絶食の後,術後9日から流動食の経口摂取が開始されたが,食欲不振,下痢症状が現れたため,再び絶食とされ,術後13日から16日まで高カロリー輸液であるピーエヌツイン1号を毎日1本,術後17日にはピーエヌツイン2号が1本投与された。術後16日と17日には流動食の経口摂取も行われた。術後18日から,ピーエヌツインの投与は中止され,三分粥と常食の経口摂取が開始された。
術後21日、患者に腸閉塞症状が出現したため,再度経口摂取が中止され術後23日と24日はピーエヌツイン1号が毎日1本,術後25日から31日までピーエヌツイン2号が毎日1本投与された。術後24日には流動食が経口摂取となり,術後26日からは常食の摂取も行われた。高カロリー輸液の投与は,術後31日で打ち切られた。
本件手術日から高カロリー輸液の投与が中止されるまでの間,患者に対して,病院食の提供以外にビタミンB1の補給が行われたことはなかった。
患者は,術後40日ころから,めまい,複視,歩行障害などの症状が生じ,術後44日ころまでには,発語の減少,反応の鈍麻など意識障害も出現し,ウェルニッケ脳症を発症したものと認められた。
術後49日の頭部MRIでは,左右ほほ対称の脳障害が認められた。被告病院の医師は,ビタミンB1欠乏を考慮し,術後50日から69日までの間,ビタミンB1を含む複合ビタミン剤(シーパラ)を1日3〜4アンプル投与した。
術後77日の頭部MRIでは,術後49日の時点で認められた病巣はほぼ消失していた。
患者は,退院後,短期記憶の障害,無表情,徘徊,歩行障害などの症状が続き,記憶障害などを訴えて他の診療機関(精神科)を受診したが,老年性痴呆症と診断された。
平成9年から平成11年にかけて撮影された頭部MRIでは,脳萎縮の所見が認められ,平成9年に実施された脳波検査では,脳波の異常が認められ,ウェルニッケ脳症と矛盾しないとの診断がされた。
そこで患者は,被告病院を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計800万円 | ||||
| 結 論 | 全部認容(認容額 合計800万円) | ||||
| 争 点 | ①患者に生じた記憶障害,見当識障害などの脳障害は,ウェルニッケ脳症によって生じたものか,老年性痴呆によって生じたものか。 ②被告病院の医師が,患者に対してビタミンBIを補給せず高カロリー輸液を投与したことに過失があるか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | 患者本人の慰謝料 | 800万円 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
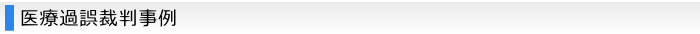
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
気管切開術の際,頸動脈を損傷して患者が失血死したことについて,担当医師の手技上の過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第14689号 損害賠償請求事件
平成18年2月23日判決 確定
【手技,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和18年生,男性)は平成11年9月1日,被告病院(大学病院)を受診し,同月13日,被告病院に検査入院した。検査の結果,食道癌と診断され同年11月1日,患者に対し食道癌根治手術が実施された。その後,患者は,呼吸不全の状態に陥ったため,12月28日,気管切開術が施行されたが,気管切開の際,頸部から大量出血してそのまま失血死した。
患者の遺族が,被告病院を開設する学校法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7932万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計2466万円) | ||||
| 争 点 | ①患者の死因は何か。 ②手技上の過失の有無 ③損害(患者の余命) | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 96万円 | |||
| ②慰謝料合計 | 2000万円 | ||||
| ③葬儀費用 | 150万円 | ||||
| ④弁護士費用 | 220万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
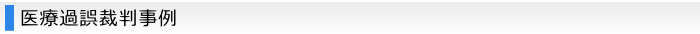
消化器外科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
大腸がん及び多発転移性肝がんで死亡した患者について、診断及び治療を怠った過失、ラジオ波焼灼術(RFA)に関する説明義務違反がいずれも否定されたケース
東京地方裁判所 平成20年(ワ)第22982号 損害賠償請求事件
平成23年3月24日判決
裁判内容 請求棄却・控訴
【説明義務、検査、治療方法】
<事案の概要>
| 請求金額 | 2500万円 |
| 結 論 | 請求棄却 |
| 争 点 | ①大腸がんの診断及び治療を怠った過失の有無 ②RFAに関する説明を怠った過失の有無 |
<判決の要旨>
①後方視的には、2月8日までに下行結腸がんに罹患しており、そのためCEAが軽度上昇していたことが高度の蓋然性をもって認められるが、注意義務違反の有無は、当該医療行為を行った時点でその判断に誤りがあったか否かという観点から判断すべきものである。そこで4月26日当時、患者が大腸がんに罹患している可能性が高いと疑う状態にあったか検討すると、CEAは偽陽性を示す場合があることに照らすとがんに特異的とはいえず、CEAが軽度上昇していると医師が認識していたからといって、直ちに、大腸がんに罹患している可能性が高いと疑うべき状態にあったとはいえない。同日のMRI上、胃がんの兆候はなく、CEA上昇が軽度で健常者や良性疾患者でもCEAが基準値を上回ることがあること、消化器がんを疑わせるような症状がみられなかったことから医師が、CEAの再検査を約2か月後とした措置は裁量の範囲内である。医師が、5月中に大腸内視鏡検査、6月中に大腸がんに対する外科手術を行わなかったとしても、直ちに不適切であるともいえない。
②本件手術では、でき得るならすべての転移巣について肝部分切除を行う方針で、RFAを行うか不確定であったことが認められるから、医師が、術前に、転移巣を切除できなかった場合の予後、RFAの有効性及び合併症、外科手術以外の治療方法などについて説明すべき義務があったとはいい難い。又、手術当時、RFAは、転移性肝がんの治療方法として特に先進的なものであったわけではなく、その治療効果は相当程度高いと考えられていたことから、仮に患者の肝転移巣が切除不能でRFAを施行せざるを得ないとしても、直ちに、説明義務があったということはできない。更に、原告らが医師に対し、患者に合併症、予後などの厳しい話をあまりしないように要望していた場合、医師が患者の病状、精神状態等を考慮した上、恐怖感など不必要な精神的ショックを与えないように、告知ないし説明をする内容及び程度を慎重に検討することも許されてしかるべきで、医師が患者に対し、上記のような説明をしなかったとしても、直ちに不適切であるとはいい難い。
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




