光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
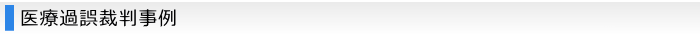
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
担癌状態にある患者について,重症感染症ないし敗血症を疑って検査を実施すべき義務,経管栄養又は中心静脈栄養を実施すべき義務,患者及びその親族に対し癌を告知すべき義務がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第10019号 損害賠償請求事件
平成17年12月2日判決確定
【説明問診義務,検査,入院管理】
<事案の概要>
患者(大正12年生,女性)は,昭和36年,子宮癌のため,子宮摘出術及び放射線治療を受けたが,平成2年ころ,放射線治療の晩期合併症として,両側尿管狭窄症から両側水腎症に陥り,腎後性腎不全の状態が進行していた。平成2年5月,甲病院泌尿器科のA医師が患者を診察したところ,両側尿管腸骨動脈交叉部以下の高度の狭窄症により,左腎は無機能腎,右腎は機能低下と診断されたため,A医師の執刀で,左腎摘出術及び右経皮的腎瘻術等が行われた。その後,腎後性腎不全の状態は回復し,同年10月,患者は,甲病院を退院し,患者の長女である被告B医師が勤務し,その夫被告C医師が開設する被告病院(総合病院)に転入院した。被告B医師が,全身状態管理及び尿路感染予防のための腎盂洗浄を行った。患者はA医師の下にも通院し,4〜6週ごとに同医師による腎瘻カテーテル交換が行われた。
患者は,平成12年6月20日,甲病院を受診し,A医師に対し,半年ほど前から不正性器出血があると訴えた。A医師が遺残膀胱をカテーテル洗浄すると出血が認められ,患者の膣を内診すると硬い腫瘤が触れたため,A医師は,甲病院産婦人科のD医師に患者の診祭を依頼した。翌21日,D医師は,患者の子宮癌が再発を考えたが,同年7月19日に検査を行った乙病院の担当医は,子宮癌再発ではなく膣癌で診断した。患者は膣断端から膀胱にかけ浸潤した癌と診断されたが,D医師は,患者が子宮癌のため放射線治療を受けていたことから,さらに放射線治療を施すのは困難であり,化学療法も,単腎で腎機能が低下している患者に行うのは困難であると考え,対症療法を行うこととした。患者は,同年7月ころ,炎症反応を示す白血球数やCRP値が継続的に高値となり,感染症予防のため抗生剤投与等が行われていたが,炎症所見が治まらなかった。患者の体温は特に上昇することはなく,同年10月5日,被告病院入院後も平熱が続いた。患者のは,倦怠感,ふらつき,食思不振を訴えることはあったが,自力歩行可能で,食事も,概ね半分程度は摂取することができていた。
平成13年2月ころ,被告B医師(患者の長女)は,患者の状態が安定しているうちに海外旅行に連れて行きたいと考え,3月23日から患者をスペイン旅行に連れて行った。患者は,帰国後,被台病院に戻り,この時点でバイタルサインに異常はなく,夜間も良眠状態であったが,徐々に旅行前よりも食欲が低下し,病院食を2,3割程度しか摂取しないことが目立つようになった。6月,患者の食欲はさらに低下し,6月中旬には,37度台の熱発を繰り返すようになり,同月13日には,CRP値が上昇するなど,炎症所見の悪化が認められた。患者の容態は次第に悪化し,経口摂取の回数及び量が減少し,自力体動も不可能になっり,白血球数及びCRP値も悪化し,体動時には疼痛を訴えた。被告B医師は,8月1日から,連日毎朝1回点滴を行い,9月6日からは毎夕点滴を行うようにした。しかし,患者の体温は37.0度前後で推移しており,腎機能も透析が必要な程度ではなく,尿量も,10月8日まで,概ね乏尿とはいえない程度で,尿比重も特に異常値を示すことはなかった。ところが,10月10日,患者の尿量減少が大きくなり,翌11日午前O時以降,尿量がなくなり,同日午前10時52分,患者は死亡した。
患者の長男が,姉である被告B医師及びその夫である被告C医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 主位的請求 1530万8044円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①平成13年6月以前に,月1回の細菌検査及び胸部X線検査を実施すべきであったか。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。 | お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
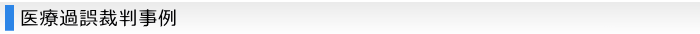
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
子宮全摘術後に水腎症を生じたことについて,子宮全摘術の際,尿管を縫合糸に巻き込んだ過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第22729号 損害賠償請求事件
平成17年11月14日判決 確定
【手技】
<事案の概要>
患者(昭和36年生,女性)は,平成13年7月30日,被告病院において子宮筋腫の診断を受け,同年8月13日,担当医師(婦人科)の執刀で経腹的単純子宮全摘術を受け,同月28日に退院した。患者は,9月13日,37度前後の発熱と右側の腹部及び背部の痛みを訴えて被告病院を受診し,腎超音波検査の結果,右水腎症及び水尿管を示す像が検出された。患者は,担当医師の紹介で甲病院(大学病院)を受診し,右尿管にほぼ完全閉塞に近い高度の狭窄があり,そのために右水腎症に罹患していることが判明した。患者は,同年10月24日,被告病院泌尿器科のA医師(非常勤)から尿路再建術が必要と診断され,A医師の指示で,同医師の常勤する乙病院(総合病院)泌尿器科を受診し,11月5日,乙病院に入院し,同月13日,A医師の執刀により尿路再建術(右尿管膀胱新吻合術)を受け,同月30日に退院した。
患者が,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4604万6271円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 尿管狭窄が子宮全摘術当時に手術操作によって生じたか。 | ||||
| 判 断 | 水腎症による背部痛が子宮全摘術直後になく,退院後しばらく経ってから生じたとすれば子宮全摘術の際に尿管を縫合糸に巻き込んだとは考え難く,尿管狭窄が子宮全摘術当時,手術操作によって生じたとは認められない。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
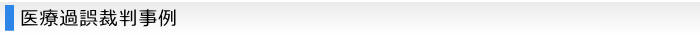
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
分娩2時間後に昏睡状態に陥り死亡したことについて,担当医師に適切な輸液及び輸血を怠った過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第6022号 損害賠償請求事件
平成17年9月30日判決 控訴
【治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和49年生,女性)は,平成14年8月22日,分娩のため被告病院(産婦人科)に入院した。同日21時25分,患者は分娩室に入室し,22時18分,担当のA医師の立ち会いの下,吸引分娩によって女児を娩出した。22時33分,胎盤娩出の際,819g(凝血約569g,羊水を含めた出血約250g)の出血が認められ,22時55分,意識はあるが,血圧70/50,心拍数が微弱となった。23時15分,担当のB医師が来室し,子宮底マッサージを施行し,23時15分までに約550gの出血が認められたが,その後出血は少量となった。23時06分,血液検査でヘモグロビン値9.7g/dl,へマトクリッ卜値28.4%であった。23時21分,血圧が70/42に低下し,B医師はエフェドリン投与,ヴィーンFの輸液を行い,経膣超音波測定法により子宮内を確認した。明らかな胎盤の遺残はなく,腹腔内出血は生じていなかったが,その後も収縮期血圧は70台で推移した。患者の顔色は不良であったが,意識は認められ,両鼠径部痛を訴えていた。23時55分,患者の血圧が110/50,心拍数が154となったため,B医師は患者を帰室させたが,患者は,0時07分ころから胸部痛を訴え,意識が混濁し,刺激にも反応しなくなり,Sp02が40%前後となり,0時25分,自発呼吸が消失した。B医師はアンビュー,挿管などを施行し,甲病院への搬送を要請し,患者は,0時32分,救急車で甲病院へ搬送された。被告病院で行われた輸液総量は,ヴィーンF1030mlで,輸血は行われなかった。
患者は,甲病院到着時,心電図上心室性頻脈を生じ,脈が触知できない状態で,当直のC医師らは心臓マッサージ,ボスミン投与,徐細動などの救命措置を行い,蘇生後,MAP及びFFPの輸血やFOYの投与などが行われたが,同日5時ころから出血,DIC傾向が生じ,翌24日5時ころから収縮期血圧が40台に低下し,患者は,同日13時15分,急性呼吸循環不全により死亡した。甲病院において採取した血液からは,亜鉛コプロポルフィリンが63pmol/ml,シアリルTn抗原が13U/ml検出された。
患者の家族(夫及び子)は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7797万0208円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①出血性ショックを看過し,適切な輸液及び輸血を怠った過失の有無 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
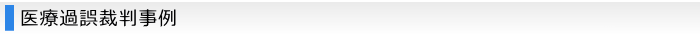
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
分娩誘発の適応がないのにこれを行った過失及び出生後の児に対する気管内挿管の手技上の過失が認められたが,過失と臍帯脱出ないし児の死亡との間の因果関係が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第6862号 損害賠償請求事件
平成17年6月29日判決 確定
【手技,適応,治療方法ー時期,因果関係】
<事案の概要>
患者は,平成13年1月26日,被告医院(個人医院)を受診し,妊娠と診断され,同年2月14日に出産予定日を同年9月10日であると診断された。患者は,被告医院に通院していたが,8月27日になっても内診所見が進んでいなかったため,被告医師(産婦人科)は,9月3日までに自然陣痛が来なければメトロイリーゼを行うこととした。9月13日午前10時ころ,被告医師が患者を内診したところ,ビショップスコアで1,2点しかない状態で,8月27日からほとんど進展がなかったことから,子宮頸管熟化不全と判断し,患者を入院させ,子宮腔内にオバタメトロを挿入した。同日午後1時ころ,被告医師が内診したところ,陣痛はあったが,子宮口の開大が進んでおらず,微弱陣痛と判断し,オキシトシンの点滴を開始し,午後1時45分ころから午後4時10分ころにかけて,オキシトシンを増量し,陣痛促進を図った。午後4時10分ころ,被告医師が内診をしたところ,オバタメトロが膣内に脱出していること(コルポの状態)を確認した。午後6時46分ころ,担当医師は,オバタメトロを抜去し,内診指を膣内に挿入したところ,いきなり多量の羊水とともに拍動する索状物が出てきたので,臍帯脱出と判断し,すぐに臍帯還納を試みたが成功しなかった。被告医師は,患者を分娩室に搬入して酸素を投与し,A医師(小児科医)ほか,院内の職員に集まるよう指示したが,帝王切開手術を介助した経験のあるB准看護師が在院していなかったため,B准看護師を含む非番の看護師に連絡をとるよう指示するとともに,帝王切開手術や新生児蘇生の準備をするよう指示した。午後7時ごろ,近医に応援を依頼するとともに,臍帯還納術を試みたが成功しなかった。用手的に子宮頸管の開大を図ったところ,午後7時10分ころ,子宮口はほぼ開大となった。このころ,近医から来院できない旨連絡があり,担当医師は吸引分娩を施行することを決め,臍帯を保護しながら吸引したが娩出できなかったため,A医師によるクリステレル圧出法を併用した上で,さらに2度吸引分娩を試みたが成功しなかった。午後7時20分,臍帯の拍動が弱くなり,被告医師は,B准看護師が到着していなかったが,帝王切開手術の施行を決め,午後7時29分ころ,手術を開始し,直後に児を娩出した。被告医師は,その後,胎盤を剥離し,子宮を縫合して止血しようとしたが,出血が激しく縫合に手間取り,手術開始後10分ほどして到着したB准看護師の介助でようやく縫合を終えた。出血量は,推定で約1000ml以上で,輸血が800ml行われた。
児の出生1分後のアプガースコアは1点であった。A医師は,児の娩出後,直ちに鼻腔等の吸引を行った後,酸素マスクによるマスク・バッグで換気を行い,心マッサージを開始し,5分経過したころ,心拍は100程度に回復したが,心マッサージを止めるとすぐに100を切る状態で,午後7時45分ころ,母子センターに出動を要請した。A医師は,30分ほど心マッサージやバギングを続け,気管内挿管をした。午後8時20分ころ,母子センターのC医師が被告医院に到着し,児を診察したところ挿管チューブが14cmの深さであったことから,10㎝に固定し直した。その後,児は甲病院に搬送されたが,同年10月2日,低酸素性虚血性脳症により死亡した。
患者及びその夫は,被告医院を開設する被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6551万7854円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①本件出産に,分娩誘発の適応があったか否か。 ②臍帯脱出後の被告医師の対!応について ③気管内挿管について ④被告医師ないしA医師の過失と児の死亡との間の因果関係の有無 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
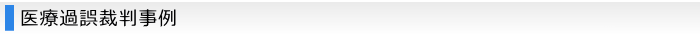
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
死胎児の分娩目的で被告病院に入院した患者が,分娩後の出血により死亡したことについて,MAPの投与を怠ったなどの過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第5652号 損害賠償請求事件
平成17年6月10日判決 控訴
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和35年生,女性)は,平成14年6月14日(妊娠35週6日),胎動の減少及び腹緊を訴えて被告病院(総合病院)の産婦人科外来を受診し,超音波断層検査の結果,子宮内胎児死亡と診断され,死胎児の分娩目的で被告病院に入院した。同月15日土曜日9時40分ころ,A医師は,患者の陣痛誘発を開始し,患者は,15時7分,男児を死産した。A医師は,分娩直後,臍下一横指に子宮底を触れたが,硬度はやや良であった。15時13分,胎盤が娩出され,胎盤娩出時に,50gの出血があり,A医師が子宮内腔を確認したところ,胎盤卵膜遺残,凝血塊,完全子宮破裂は認められず,臍下一横指に子宮底を触れ,硬度は不良であった。A医師は,15時35分,会陰裂傷の縫合を終了したが,会陰縫合時,420gのどす黒く,さらさらした出血が認められた。A医師は,その場で採血を行い,自ら緊急検査室で血液検査を行った。血液検査の結果,白血球数11700,赤血球数413万,Hb値11.1g/dl,Ht値33.3%,血小板数17.6万/μlであった(15時で検査室の業務は終了しており,血液凝固系の検査は行われなかった。)。15時40分,A医師が,患者の下腹部を触診したところ,子宮底が臍下二横指に触れ,子宮収縮は良好で,この時点までの総輸液量は,左前腕から5%ブドウ糖液600mlであった。15時43分,A医師は,来室したB医師とともに超音波検査等の検査を実施し,子宮内胎盤遺残,腹腔内出血,頸管裂傷はなく,触診の結果,子宮体部の収縮は良好であったが,650gの出血が認められた(総出血量1120g)。C医師が来室し,担当医師らは,へスパンダー500mlの点滴,MAP輸血の準備,FOYの点滴投与を行った。患者の意識は清明で,バイタルサインに特段の異常は認められなかったが,出血傾向は改善せず,16時10分,子宮収縮不良となり,16時16分,尿道にバルーンカテーテルを挿入留置したところ,肉眼的血尿が認められた。担当医師らは,患者を甲病院(大学病院)へ搬送することとし,17時00分,患者は救急車で搬出された。搬送中も含め,被告病院で行われた輸液総量は,左前腕,左手背,右手首(FOY,メテナリンを除く)の3ルートから,5%ブドウ糖液1300ml,ヘスパンダー500ml,ヴィーンF800ml,ラクトリングル300mlの合計2900mlで,出血総量は2482gであった。
17時15分,患は甲病院に到着し,到着時のバイタルサインは,血圧91/66,脈拍173,呼吸数28/分,Sp02測定不能で,問いかけには開眼した。甲病院の医師らは,DIC及び重症の出血性ショックと診断し,MAP3単位,新鮮凍結血漿(FFP)1単位を投与したが,出血傾向は収まらず,子宮全摘術,子宮動脈塞栓術も考慮されたが,DIC傾向が強く外科的処置が危険な状態であったため実施されず,患者は,翌16日2時04分,DICを原因とする出血性ショックで死亡した。
患者の家族(夫及び子ら)は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計9260万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①出血の原因(弛緩出血か否か) | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
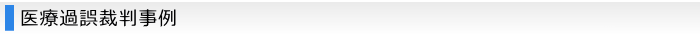
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
子宮頚癌で患者が死亡したことについて,診断,手術適応,治療方法,説明義務違反の過失がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第11102号 損害賠償請求事件
平成16年7月26日判決 控訴・和解
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,女性)は平成11年11月1日,被告病院(大学病院)産婦人科を受診して入院し,広汎子宮全摘出術及び骨盤リンパ節郭清術を受けた。同年12月27日,患者は,腸閉塞の診断を受け,イレウス管を挿入され,後に抜去された。平成12年1月16日,患者は,産婦人科に戻り,放射線科にて放射線治療が開始され,同年2月29日,産婦人科を退院し,以後外来を受診をしていた。同年12月4日,患者は,産婦人科に再入院し,化学療法を受け,平成13年4月28日,産婦人科を退院した。患者は,その後,外来受診し,同年7月24日,産婦人科に再々入院し,同年9月8日死亡した。
患者の家族は,担当医師が,手術適応がないのに,手術を行い,又手技を誤り,術後腸閉塞を発症させ,これに対する必要な治療を行わず,さらに放射線治療や抗癌剤投与について必要な説明を行わず,患者死亡後も適切な対応をしなかったとして,担当医師及び被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計5500万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①死亡原因 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
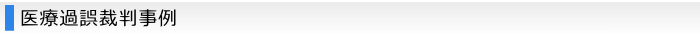
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が胎児を死産したことについて,産婦人科医師の分娩監視義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4644号 損害賠償請求事件
平成16年3月29日判決
【検査,分娩監視義務違反】
<事案の概要>
患者(昭和46年生,女性)は,平成12年1月,被告医院において,妊娠6週1日と診断され,その後,定期的に被告医院に通院し,同年10月2日午後2時,分娩のために被告医院に入院した。
患者は,同日午後4時から翌3日午前9時10分まで,オパタメトロを挿入され,引き続いて午前10時15分から午後5時30分まで,プロスタグランジンF2αが投与され,午後6時30分と午後8時30分ころ,B看護師による陣痛間隔の測定等を受け就寝した。
患者が就寝していた同月4日午前2時ころ,B看護師が患者の胎児の心拍数を計測しようとしたところ,聴取できず,同日午前3時ころ,A医師によって,胎児の心拍が消失していることが確認された。
患者は,同日午前5時45分ころ,甲病院(大学病院)に転送され,甲病院において,人工的に破水された後,同日午後5時15分ころ,既に死亡していた胎児が娩出された。
患者は,被告医院を開設していたA医師及びC医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1200万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①本件胎児の死亡原因 | ||||
| 判 断 | ①本件胎児には、頚部に臍帯が2回巻絡していたことが認められ,他に死亡原因となり得る症候が見当たらないことから,死亡原因は,臍帯巻絡と推認される。 ②10月3日午後8時30分の時点で,本件胎児に異常が生じていなかったことからすると,同時点以降,患者に分娩監視装置を装着して分娩監視をすべき法的義務があったとまで認めることはできない。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
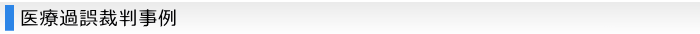
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
単純子宮全摘術及び両側付属器切除術の適応,手技,説明義務違反が争われ,いずれの過失も認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第11987号 損害賠償請求事件
平成16年2月25日判決
【説明義務,問診義務,手技,手術適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生)は,被告病院(総合病院)のA医師(産婦人科)から子宮筋腫で子宮が新生児頭大に腫大し,卵巣腫瘍の可能性があって手術が必要との診断を受け,平成11年11月11日,被告病院に入院した。
被告病院のB医師(産婦人科,平成11年5月まで研修医)が主治医,A医師がB医師の指導医として患者の診察に当たった。A医師は,患者に対し,単純子宮全摘術及び片側付属器(卵巣と卵管)切除術を実施する旨説明していたが,B医師は,年齢的に閉経の近い本件患者にとって,片側付属器を残して女性ホルモンの分泌を維持するメリットよりも,両側付属器を切除して卵巣癌等になるリスクをなくしてしまうメリットのほうが大きいと考え,両側付属器切除術のメリット,デメリットを患者に説明し,両側付属器切除術に変更する旨の患者の同意を得た。
平成11年11月15日,B医師を執刀医,A医師を助手として,患者に対し,単純子宮全摘術及び両側付属器切除術が実施され,患者は同月29日被告病院を退院した。患者は,退院後,被告病院に外来通院し,のぼせ,発汗等の更年期障害の出現に対し女性ホルモン療法を受けたが更年期障害は続いた。
平成14年2月,患者は,手術で開腹した辺りに違和感を感じ,甲病院(国立基幹病院)を受診したところ,術後腹壁瘢痕ヘルニアであるとの診断を受け,同年5月2日,甲病院で術後腹壁瘢痕ヘルニア根治術を受けた。
患者が被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1100万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①被告病院担当医師は,患者の子宮筋腫が本件手術を要するほどの大きさでなかったにもかかわらず,超音波検査も行わないまま,手術適応があると誤診し,実施したのか否か。 | ||||
| 判 断 | ①片側付属器切除術,両側付属器切除術いずれもメリット,デメリットがあり,患者には,両側付属器切除術の適応があったと認められ,手術適応の判断を誤った過失は認められない。 ②患者の腹壁瘢痕ヘルニアは、術後1か月以上経ってから発症したものであり、かつ、患者には腹壁瘢痕ヘルニアを発症しやすい要因(女性,肥満)があったことからすれば、患者の腹壁瘢痕ヘルニアは患者の要因により発症したものと考えられ,担当医師が不適切な縫合を行ったとは認められない。 ③説明義務違反はない。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
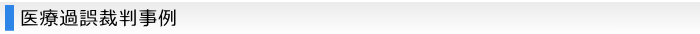
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
妊婦に対し帝王切開を行うべきであったとはいえず,経膣分娩の措置にも過失が認められないとされたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第6121号 損害賠償請求事件
平成15年9月19日判決
【手技,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(平成9年生,男児)の母親は,平成9年2月24日,妊娠の可能性があったため被告病院(大学病院)産婦人科を受診した。母親は,妊娠していたが,被告病院産婦人科の担当医師は,母親がC型肝炎ウイルスの保有者で,母子感染の危険性があることなどから,被告病院での出産を勧め,母親もこれに同意した。
母親は,出産予定日の同年10月15日を経過しても出産に至らなかったため,同月23日,被告病院産婦人科へ入院した。同月25日1時,陣痛が始まり,同日9時02分には子宮口全開大となったが,児頭が下降せず,担当医師及び担当助産帥は,吸引分娩などにより患者を娩出した(出生時体重4123g)。同日,被告病院小児科医師により,患者には上腕部の麻痺が存在すると診断された。患者は,被告病院にてリハビリを受けていたが,平成11年12月1日,被告病院での治療をやめた。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 5905万6843円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①被告病院は,母親に対し,帝王切開を行うべきであったか否か。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
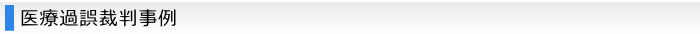
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
出産の際,臍帯脱出の兆候が認められたにもかかわらず,直ちに帝王切開に踏み切らなかった過失及び臍帯脱出の原因となる不適切な散歩指示をした過失が認められず,説明義務違反も認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第3546号 損害賠償請求事件
平成15年5月28日判決
【説明義務,問診義務,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(女児)の母親は妊娠し,平成12年3月21日から,担当医師の開設する被告医院(産婦人科,個人病院)で定期的に検診を受け,母児ともに順調に経過していた。母親は,妊娠38週3日目の同年11月8日午後10時15分ころ,被告医院で破水の診断を受け入院となった。翌9日になっても陣痛が起こらなかったため,担当医師は,母親に陣痛誘発のため散歩を指示した。同日午後10時ころ,陣痛が始まり,看護師が母親に胎児心拍陣痛図(CTG)を装着したが,胎児心拍数に問題はなかった。
同月10日午後1時21分ころ,CTGの胎児心拍数が突然60から80bpmまで低下したため,助産師は,母親に酸素マスクを装着するとともに,胎児の徐脈が,臍帯が子宮内で胎児と子宮壁の間で圧迫され血流が妨げられていることによる可能性があったため,母親の体位を変換して圧迫の除去を試みた。助産師から連絡を受けた担当医師が駆けつけ,直ちに内診したところ,子宮口から膣内に臍帯が10cmほどの環状になって脱出しており(臍帯脱出),臍帯が児頭と子宮口の間で圧迫され血流が妨げられ胎児心拍が悪化していることが判明した。
担当医師は,脱出した臍帯を子宮内に入れて還納しようとしたが,再脱出したため,午後1時30分ころ,緊急帝王切開術実施を決定し,大学病院医局に電話をして緊急の応援医の派遣を要請するとともに,助産師や看護師らに対し,手術室や手術器具の整備,母親に対する子宮収縮抑制剤の投与と点滴のための血管確保等を指示した。
その後も胎児心拍数は回復しなかったため,担当医師は,胎児の生命の危険を考え,帝王切開よりも吸引分娩に切り替えることを決意し,午後1時50分ころ,児頭に吸引カップを装着して吸引し,助産師が母親に対し,クリステレル娩出法を実施したところ,2回の吸引により,午後2時ころ,胎児を娩出した。大学病院から派遣された応援医2名が到着したのは,午後2時ころであった。
出生した胎児(患者)の生後1分及び5分のアプガースコアはいずれも1点で重症仮死であった。担当医師は,応援医の協力を得て,心臓マッサージ,気管内挿管等により,蘇生術を実施し,その後,甲病院に患者を搬送した。
患者は,分娩中の臍帯脱出により,全身チアノーゼ,無呼吸などを伴った低酸素性脳症の症状を呈する重篤な仮死状態で出生し,低酸素性虚血性脳症を原因とする重度脳性麻痺,精神発達遅滞,てんかんの障害を負い,寝たきりの状態で全介助を要し,身体障害者障害等級2級の認定を受けた。
患者及び両親は,被告医院を開設する担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億1058万2580円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①11月10日午前11時ころ臍帯脱出の兆候が認められたにもかかわらず,直ちに帝王切開に踏み切らなかった過失ないし注意義務違反の有無 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
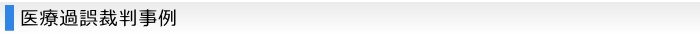
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
妊婦に対し,入院の上検査を受けさせる義務は認められず,帝王切開を選択した時期に過失は認められず,説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第1401号 損害賠償請求事件
平成15年2月28日判決
【説明義務,問診義務,検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(平成9年及び12年に出産した経産婦)は,平成12年11月28日,被告病院(総合病院)を受診し,妊娠しており,出産予定日が平成13年6月30日ころとの診断を受け,1か月に1回程度の頻度で被告病院に外来通院していた。
患者は,分娩週数31週5日の同年5月3日午後5時過ぎ,下着が濡れるほど水が出たため,午後6時ころ被告病院に電話をしたところ,すぐ来院するよう指示され,午後6時30分ころ,被告病院を受診し,A医師(産婦人科)の診察を受けた。患者は,体温36.9℃,血圧111/67,脈拍79であった。患者は,A医師の問診で,水が出たのは1回で,腹部の張りはなく,胎動は良いと回答した。膣鏡診で膣内を診察したところ,帯下と判断される白色,中等量の膣内容物が認められたのみで,羊水流出を推測させる所見は認められなかった。BTB検査を2回実施したが陰性であった。内診で,不正性器出血は認められず,外子宮口は閉鎖していたが,児頭はやや下降していた。約1分間程度の触診の結果,患者の腹部には子宮収縮自体認められず,患者の腹部は,切迫早産で子宮収縮を起こしている時に通常子宮が呈するような硬さもなく,軟らかい状態であった。経膣超音波検査では,経管長は19mmと短縮し,児頭の高さはST-2とやや下降していた。
A医師は,破水は否定的と判断し,患者に安静を指示して帰宅させた。
患者は,翌5月4日午前3時ころ破水したと訴えて,午前9時50分ころ,被告病院を受診し,B医師(産婦人科)の診察を受けた。B医師は,患者に,分娩監視装置を装着し,胎児頻脈(基線190〜200)及び軽度の子宮収縮を認めた。B医師は,膣鏡診で,膣内に淡黄緑色の液体を認め,BTB検査及びアムニテストを実施したところいずれも陽性であり,破水と判断し,これらの所見から,患者が切迫早産の状態にあると診断した。羊水はわずかに混濁し,患者の体温は36.9℃,血圧は104/68であった。その後,30分に及ぶ持続性頻脈があったことから,B医師は,午前10時20分ころ,子宮内感染を疑い,午前10時25分ころ,患者に対し血液検査を実施し,帝王切開の可能性を考えて,患者に絶飲食を指示した。
午後0時13分ころ血液検査結果が出て,白血球数21100,CRP値3.9と感染を示す値が出たため,B医師は,子宮内感染を理由とする緊急帝王切開手術を決定し,患者らに説明し同意を得た。
B医師は,休日であったため自宅待機していた麻酔医を呼び出し,手術室の準備をし,午後1時15分ころ患者を手術室に入室させ,午後1時46分に手術を開始し,午後1時50分に児を娩出した。
児は,同日午後9時42分,肺炎球菌による子宮内感染に起因する呼吸不全及び脳内出血により死亡した。
患者が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 7391万4630円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①平成13年5月3日の受診時,患者を入院させ必要な検査(頸管分泌液の細菌培養検査,子宮底を圧迫し羊水流出の有無を確認する検査,羊水の胎児由来細胞の確認,患者の白血球,CRP等の血液検査超音波による推定体重計測や羊水ポケット計測等)を行わなかった過失の有無 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
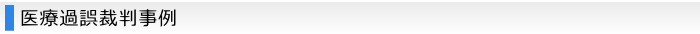
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
双胎の第2子が胎児仮死に陥ったことについて担当医師の不法行為責任が否定されたケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第26241号 損害賠償請求事件
平成14年12月25日判決
【治療方法手術適応,時期】
<事案の概要>
患者は,双胎分娩目的で被告病院(大学病院)に入院していた。患者は,平成11年10月9日午後0時30分,分娩室に入室し(陣痛発来後17時間10分経過),同時点で第1子,第2子ともに頭位であった。午後3時40分,陣痛は微弱のまま推移し,担当医師は,患者の疲労が蓄積していたことから,吸引分娩の実施を決定した。午後3時50分ころ,第1子の胎児心拍数は,基線が毎分120回台であったが,90回以下まで下降し,第2子の胎児心拍数も,100回程度まで下降していた。
午後3時55分,担当医師は,吸引カップを2回目の試行で第1子の児頭に吸着させ吸引を行い,午後4時1分,第1子が娩出された。アプガースコアは1分後8点,5分後9点であり,問題はなかったが,2195gの低出生体重児であったため,新生児集中治療管理室で管理された。
午後4時4分,陣痛がほぼ消失し,第2子の児頭はステーションマイナス3以上と高い位置にあり,骨盤内に固定しない状態で,子宮口も狭窄していた。第2子の胎児心拍数は,午後4時10分ころまで,毎分100回から110回程度の軽度の徐脈であったが,基線細変動は存在した。午後4時10分ころから20分ころ第2子の胎児心拍数は,毎分90回以下の徐脈が出現する状態であったが,基線細変動は存在した。午後4時20分,陣痛は相変わらず微弱で,児頭は高位で,午後4時25分,児頭の位置に変化はなく,手も先進していた。担当医師は,有効な陣痛の回復を待つこととして,助産師に対し,分娩台上での経過観察を指示した。
午後4時20分ころから午後4時40分ころ,第2子の胎児心拍数は,子宮収縮のたびに,毎分80回から90回台までの下降と,150回から170回台までの上昇とを繰り返し,基線細変動は存在した。担当医師は,遅発一過性徐脈と考え,パルトグラムにその趣旨の記載をした。徐脈の際の心拍数が毎分60回を下回ることはなく,1分弱で回復していたことから,担当医師は,軽度の変動一過性徐脈と判断し,高度変動一過性徐脈が繰り返し出現する場合のみ胎児仮死と認めるという考え方に従い,この時点で第2子が胎児仮死に至ったとは判断しなかったが,徐脈が繰り返し出現したため,第2子に異常がないとはいえないと考え,監視を続けた。その後も有効な陣痛の回復は見られず,児頭の下降と子宮口の開大もなかった。
午後4時40分前後になると,毎分150回程度の胎児心拍数が,100回程度の徐脈になり,回復しても150回を超えることがほとんどなくなったため,担当医師は徐脈の回復が不良であると判断をした。基線細変動は存在したが,元気である(well-being)といえるほどではなかった。担当医師は,娩出方法について,母体の安全のため帝王切開術の実施には慎重であるべきと考えていた。そして,第2子が横位になるとか,臍帯脱出を起こすなどの帝王切開術の適応ではなかったこと,帝王切開術の準備には手術室への移動や麻酔の導入などで30分以上かかること,第1子が経膣で娩出されたことなどを考慮し,第2子の分娩はこのまま経睦分娩で行うとの方針を立てた。
午後4時53分ころ以降,胎児心拍数は毎分60回台まで下降して,回復にも時間を要するようになり,午後4時57分ころ以降は,記録もほぼ途切れるようになった。午後4時58分,児頭が骨盤に陥入してきたが,依然として手が先進していた。
午後5時ころ,人工破膜が行われ,その際,第2子の臍帯脱出が起こった。午後5時5分,担当医師は吸引カップの吸着を試みたが,子宮口が全開しておらず,先進していた手が邪魔になって,1回目は失敗し,午後5時7分,2回目も吸着できず児頭が浮遊してしまった。担当医師は,吸引分娩を断念し,鉗子分娩に切り替え午後5時8分,児頭は依然として高位であったが,鉗子で児頭を挟んで,クリステレル圧出法を併用して出口部分まで牽引し,午後5時10分,児頭に吸引カップを吸着させて吸引した。
担当医師は,児頭が高位にある状態で鉗子分娩を行うことについて,かなり危険が伴う処置であることを認識していたものの,第2子の娩出を急ぐために実行した。午後5時12分,第2子が娩出された。アプガースコアは1分後O点,5分後1点,10分後2点と非常に悪く,新生児仮死の状態であった。第2子は,すぐに小児科医に引き継がれ,新生児集中治療管理室で管理されたが,第2子は,重度の脳性麻痺により,現在まで寝たきりの状態で,常時,鼻や口にチューブがつながれ,酸素や栄養の補給を受けている状態である。
出生した第2子とその両親は,被告病院を設置する法人と担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計8729万3788円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①午後4時25分,午後4時40分の各時点で,担当医師に帝王切開術を決定をする義務があったか否か。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
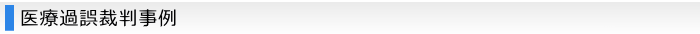
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者の膣内に発見されたガーゼ様のものが,子宮癌検診の際に残置されたガーゼであると断定できないとされ,検診を行った病院の責任が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第9439号 損害賠償請求事件
平成13年7月25日判決
【残置、検査】
<事案の概要>
患者(女性)は,平成9年2月14日,被告健診センターにおける成人病検診(本件検診)の子宮癌検診を受けて陰性と判定された。検診では,細胞診による検査は行ったが組織診による検査は行われなかった。
患者は,同月20日から4日間,月経があり,同月27日,40度の発熱をし,甲胃腸外科クリニックを受診したが,風邪と診断された。その後も症状が回復しなかったため,患者は,同年3月4日,乙クリニックを受診し,丙病院(大学病院)を紹介された。患者は,丙病院を受診し,A医師の診察を受けところ,A医師により,膣内に四角に折り畳まれた3cm立方の異臭を帯びたガーゼ様のものが残置しているため,これが感染源となって,骨盤内感染症,卵管溜膿腫,骨盤腹膜炎に,罹患したと診断された。患者は,同年2月14日から同月27日までの間,婦人科を始め他の病院に通院しておらず,同月27日から同年3月4日までの間は,甲胃腸外科クリニツク,乙クリニック,丙大学病院に通院したのみで,丙病院を受診するまでは何ら膣内の診察を受けていなかった。
患者が,被告健診センターを開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 781万0978円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 患者の膣内に残置されていたガーゼ様のものは,本件検診において残置されたものか否か。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
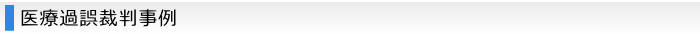
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
帝王切開術後に生じた腹腔内出血について,救急病院への搬送が遅れた責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第28153号 損害賠償請求事件
平成15年10月9日判決
【転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和40年生)は、平成13年6月6日午後零時10分から,被告病院(個人病院)においてA医師及びB医師(いずれも産婦人科医)の執刀で帝王切開術を受け,午後零時11分,男児を娩出した。
患者は,同日午後1時15分に病室へ帰室した直後から,持続的に,めまい,気分不快,体熱感,軽度の呼吸苦等を訴え,午後4時には,患者の血流量の減少が疑われた。午後4時ころ,A医師が,B医師に対し,救急病院への搬送の手配を提案したが,B医師は,搬送の手配は血液検査と腹部エコー検査を行ってからにするよう指示し,午後4時40分ころから救急病院への搬送の手配がなされた。
同日午後5時50分ころ,患者は,甲医療センターに到着したが,高度出血性ショックの状態であった。甲医療センターの医師は,触診と腹部エコー検査を行った後,試験開腹術を行い,子宮切開創より膀胱にかけての巨大な血腫を除去した後,子宮切開創の止血を試みたが困難だったため,子宮を全摘出した。総出血量は5970gであった。その後,患者の意識が回復することはなく,患者は全脳虚血後の遷延性意識障害と診断された。
その後,患者は,他の病院に転院し,低酸素性脳症と診断された。患者は,退院後現在まで,意識が回復することなく,遷延性意識障害(いわゆる植物状態)のまま推移している。
患者及びその夫が,被告医院を開設する法人及び担当医師ら(A医師,B医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2億7024万1672円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計2億2271万0251円) | ||||
| 争 点 | ①患者の救急病院への搬送が遅れた過失の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | 患者の損害 | ①治療費 | 339万0561円 | ||
| ②文書料 | 1万5750円 | ||||
| ③入院雑費 | 13万9500円 | ||||
| ④付添看護費 | 60万4500円 | ||||
| ⑤自宅改造費 | 78万3126円 | ||||
| ⑥床ずれ防止マットレンタル料 | 2万8560円 | ||||
| ⑦将来治療費 | 547万1070円 | ||||
| ⑧将来介護料 | 9947万3632円 | ||||
| ⑨将来介護雑費 | 663万1575円 | ||||
| ⑩休業損害 | 89万1322円 | ||||
| ⑪逸失利益 | 5528万0655円 | ||||
| ⑫入院慰謝料 | 150万0000円 | ||||
| ⑬後遺障害慰謝料 | 2800万0000円 | ||||
| ⑭弁護士費用 | 1500万0000円 | ||||
| 患者の夫の損害 | ①患者の夫固有の慰謝料 | 500万0000円 | |||
| ②弁護士費用 | 50万0000円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
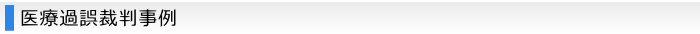
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
帝王切開術及び子宮筋腫核出術の術後,肺塞栓症を発症して死亡したことについて,人工呼吸器の設定に過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25235号 損害賠償請求事件
平成16年5月27日判決 控訴
【手技,適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和43年生,女性)は,平成9年10月11日,被告病院(大学病院)産婦人科を受診し,妊娠及び子宮筋腫と診断された。患者は,被告病院に通院し,平成10年5月25日,被告病院に入院した。担当医師らは,帝王切開術による分娩が望ましいと判断し,患者も,帝王切開による分娩に同意するとともに,子宮筋腫を取ることを希望した。5月27日午後3時ころ,帝王切開術が開始され,児が娩出され,担当医師らは,子宮筋腫が子宮収縮を妨げている可能性があると考え,漿膜下筋腫2個につき,子宮筋腫核出術を施行した。5月28日,担当医師らは,患者がやや肥満であったことから,血栓症予防のへパリン投与を検討した。帝王切開は血栓症の危険因子の一つであったが,患者は,妊娠初期に肥満が見られなかったこと,分娩前の体重増加は娩出した児の体重等を考えると著しい肥満化とはいえないこと,術前に血液濃縮が見られなかったことから,へパリン投与が必要なほどの血栓症の危険性はないと判断され,子宮筋腫核出術を行ったことを考慮し,ヘパリン投与は行わないことになった。患者は,5月28日午前11時30分ころに,嘔気,手のしびれ,軽度の胸痛,軽度の呼吸困難などの症状を呈したが,ビニール袋を使用してゆっくり呼吸をした結果,楽になったと述べるなどしていた。患者は,5月29日午前10時30分ころ,気分不快,冷感を訴え,午前10時50分,血圧が低下し,意識がやや不明確となり,顔色が蒼白で唇にはチアノーゼが認められる状態に至り,午前11時42分,一時的に心停止状態に陥った。患者に対し,抗凝固療法や血栓溶解療法が開始され,心エコー検査,心電図検査により,肺塞栓症と診断された。
患者には,5月29日午後0時5分,人工呼吸器が装着され,CMV(調節機械呼吸),呼吸回数10回/分と設定されたが,午後1時39分,SIMV(同期式間欠的強制換気),呼吸回数12回/分に変更された。設定変更の直前,酸素分圧136.2㎜Hg,炭酸ガス分圧67.9㎜Hg,酸素飽和度97.9であったが,午後3時49分,酸素分圧46.6㎜Hg,炭酸ガス分圧64.6㎜Hg,酸素飽和度70.7となり,午後4時には,酸素分圧46.7㎜Hg,炭酸ガス分圧66.7㎜Hg,酸素飽和度71.5となった。午後4時35分,人工呼吸器の設定がCMV,呼吸回数10回/分に戻され,その結果,午後4時52分には,酸素分圧246.0㎜Hg,炭酸ガス分圧49.5㎜Hg,酸素飽和度99.5となった。患者は,5月30日以降も治療を受けたが,意識が回復することはなく,6月25日,肺塞栓症に続発した多臓器不全で死亡した。
患者の母は,患者が死亡したのは被告病院の担当医師らに過失があったためであると主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1000万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額200万円) | ||||
| 争 点 | ①帝王切開術の際,子宮筋腫核出術を施術したことの適否 ②術後,肺塞栓症発症の予防療法をとらなかったことの適否 ③5月28日時点で ④5月29日午前10時50分時点で ⑤5月29日午後1時39分,人工呼吸器の呼吸条件の設定を変更して以降 | ||||
| 認容額の内訳 | 近親者としての慰謝料 | 200万円 | |||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
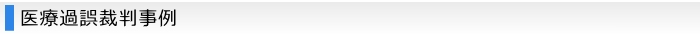
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
帝王切開手術の際,卵巣のう腫を発見しながら摘出しなかったことについて過失が認められなかったが,経過観察で適切な検査を行わず卵巣茎捻転の発見が遅れた過失が認められたケース
大阪地方裁判所
平成15年(ワ)第13022号 損害賠償請求事件,
平成16年(ワ)第5736号 未払治療費等請求反訴事件
平成17年11月30日判決 控訴・控訴棄却
【手技,検査,治療方法時期】
<事案の概要>
患者(女性)は,平成13年10月22日,被告病院(総合病院)のA医師(産婦人科)の診察を受け,右卵巣のう腫が存在すると診断され,同年11月10日及び平成14年2月23日にも,B医師(産婦人科)により,卵巣のう腫と診断されていた。患者は,同年5月25日,被告病院を受診し,B医師により妊娠5週4日であり,右卵巣に34㎜ののう腫が2個存在していると診断された。6月1日,B医師は,超音波検査で胎児の成長具合を確認するとともに,卵巣のう腫の明らかな縮小と変形を認めた。その後,患者は,被告病院を受診し,いずれの診察においても超音波検査を受けていた。平成15年1月17日,患者は児頭骨盤不均衡と診断され,同月22日,執刀医であるB医師と助手であるC院長(外科)により,帝王切開手術を受けた。患者は,1月27日早朝,創部痛ではない腹痛を訴え,坐薬等の処置で排便,排ガスがあったときは,少し楽になるものの,しばらくするとまた腹痛や腹部膨満感を訴えることを繰り返したため,B医師は,イレウスを疑い,腹部単純レントゲン写真を撮影したところ,ニボー像は確認できなかった。患者は,同日以降も程度の差はあるものの,腹痛や腹部膨満感を繰り返し訴えた。同月28日,血液検査で血色素量の低下が認められ,同月30日の血液検査では,白血球数の上昇が認められたため,B医師は感染を疑い,抗生剤を投与した。同年2月1日,B医師は,原告の腹痛が増強し,腹部が膨満しているという所見を認め,同日の血液検査では,血色素量低下,白血球数上昇,CRP値上昇が見られたため,翌2日,B医師は,抗生剤を変更・増量して投与した。同月3日の血液検査でも貧血が認められたため,B医師は血腫を疑い,再開腹手術の必要性を検討したが,経過観察を続けた。同月7日,臍部を中心に腫瘤様のものを触知したため,超音波検査及びCT検査を行ったところ,血腫の存在が確認されたため,再手術が決定された。同月8日,B医師とC院長により,患者に対し,再開腹手術が実施され,患者の右卵巣は血腫化し成人頭大に腫大し,2.5回転の茎捻転を生じた上,腫瘤の左上部が小腸及び大綱に癒着していた。B医師らは,切開創を臍部左方から上方へあげて広げ,癒着部分を剥離した上,右卵巣を切除した。右卵巣血腫について病理組織検査を行った病理学センターは,ムチン性のう胞脱腫及び出血性壊死と診断した。
患者は,被告病院を開設する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計550万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 50万円) | ||||
| 争 点 | ①手術の際,B医師が誤って患者の右卵巣に過大な圧力ないし衝撃を加えたか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 45万円 | |||
| ②弁護士費用 | 5万円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
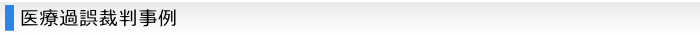
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
妊婦の血液型がRhマイナスであることを見落とし,妊娠中,間接クームステストを行わず,分娩後もグロブリン注射を実施しなかったことについて,医師の過失が認められ,過失と,その後新たに妊娠した第2子を人工妊娠中絶したこと及び抗体価の増加との間の因果関係がいずれも認められたケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第12089号 損害賠償請求事件
平成17年10月12日判決 確定
【治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和48年生,女性)は,平成12年9月25日,被告医院(産婦人科)を受診し,妊娠5週1日目で,分娩予定日は平成13年5月27日であると診断された。患者が作成した産婦人科外来問診表のRh(D)式血液型記入欄は空欄となっており,過去に妊娠したことがない旨記入されていた。患者は,同年10月,血液検査を受け,その結果,患者の血液型が,Rhマイナスであることが判明し,検査結果は,同月31日までには,担当医師に報告されたが,担当医師は,患者の血液型がRhマイナスであることを見落とした。担当医師は,診療の際,患者に対し血液型がRhマイナスであることを伝えず,間接クームステストによる抗体価の検査を実施しなかった。患者は,平成13年5月23日,第1子を出産した。第1子は何ら障害がなく,血液型はRhプラスであった。担当医師は第1子妊娠中から第1子分娩後に至るまで,患者に対し,グロブリン注射を実施しなかった。
患者は,平成15年10月末,第2子を妊娠し甲産婦人科を受診し,同年12月の血液検査でRhマイナスであり,間接クームステストによる抗体価が3倍であることが判明した。その後,患者は,乙医療センターを紹介され,乙医療センターにおける血液検査の結果,間接クームステストによる抗体価は2倍であり,「Rh不適合妊娠の疑い」と診断され,平成16年1月22日,乙医療センターにおいて人工妊娠中絶術を受けた。
患者及びその夫が,被告医院を経営する医療法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 6278万7493円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容紅11137万9355円) | ||||
| 争 点 | ①第1子の妊娠中,間接クームステスト及びグロブリン注射を実施すべき注意義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費 | 28万7639円 | |||
| ②交通費 | 2万1570円 | ||||
| ③埋葬費 | 3万4000円 | ||||
| ④雑費 | 1660円 | ||||
| ⑤慰謝料 | 1000万0000円 | ||||
| ⑥弁護士費用 | 103万4486円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
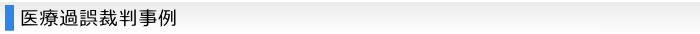
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
死産について,重症妊娠中毒症を前提とする対応を怠った過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第3537号 損害賠償請求事件
平成17年6月24日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和45年生,女性)は平成12年12月25日,近医で妊娠の診断を受け,平成13年1月18日,被告病院を受診した。当初,患者が申告した最終月経開始日を基準に,妊娠週数を9週O日,分娩予定日を8月23日と判断されたが,その後,妊娠週数9週4日,分娩予定日8月19日に訂正された。患者は,7月3日,自宅近くのクリニックで妊娠後初めて尿蛋白「+」と判定され,浮腫も「±)」と診断されたため,同クリニックの医師は,診療情報提供書に,傷病名として「蛋白尿」,治療経過として同月3日に尿蛋白が「+」であったこと,浮腫が「±」で,これに対する漢方薬を処方したことなどを記載した。患者は,同月10日にも上記クリニックを訪れたが,このときも尿蛋白は「+」と判定された。患者は,7月16日(妊娠35週1日),上記診療情報提供書を持参して被告病院を受診し,被告病院での検査の結果,尿蛋白が「++」(100mg/dl)と判定された。超音波検査による胎児の計測値に基づき算定される推定児体重は2302gとなり,平均体重との偏差が-0.6SDと正常範囲内にあると判断され,特に異常があるとの診断はなされなかった。その後,被告病院では,胎児の超音波検査は実施されず,推定児体重が算定されることはなかった。7月24日(妊娠36週2日),患者は,被告病院を受診し,手足の浮腫を訴え,現に浮腫が認められたが,顔面,眼瞼その他全身には浮腫は及んでいなかった。尿蛋白は「+++」で,体重は,同月16日より400g多い68.7㎏,血圧は110/70であった。血液検査の結果,腎機能の指標となる尿酸値が7.5mg/dlと正常値を超え,尿素窒素(BUN)も17mg/dlと正常妊婦の正常上限値(15mg/dl)を超えていたが,電解質(Na,K,Cl)の値は正常であった。検査結果を踏まえ,被告病院は,患者に対し,減塩食を指示した。7月31日(妊娠37週2日),患者は,被告病院を受診し,腹部の緊満感を訴えた。尿蛋白は「「++++」(1000mg/dl)とさらに悪化し,浮腫も認められ,被告病院は,患者に対し,ノンストレステスト(NST)を行い,胎児の状態につきリアクティブと診断したが,24時間蓄尿して尿検査を行うほか,連日NSTを行うなどの検査のため,患者は,8月2日(妊娠37週4日),被告病院に入院した。
患者は,入院時,浮腫「±」であったが,尿蛋白は「+++」で,血中総蛋白量は,正常値の下限である6.5g/dlであった。患者は,入院時から蓄尿し,8月4日に24時間尿量約1800mlのうち400mlが蛋白定量検査に回され,蛋白量は,48mg/dlであった。入院後,試験紙法による尿蛋白検査では,同月3日以降,「++」から「+」へと減少傾向にあったが,同月6日朝の検査で,再び「+++」となった。8月3日以降浮腫は認められず,体重も減少傾向にあったが,入院全期間を通して,尿蛋白定量検査は行われず、腎機能検査は1度も行われなかった。入院期間中の血圧は,収縮期血圧が概ね100〜120程度,拡張期血圧が概ね50〜70程度であったが,同月3日に138/70,同月4日に150/80,同月6日に128/60であった。被告病院は,8月3日から6日にかけて,連日NSTを行い,いずれもリアクティブと判定した。基線細変動については,カルテ上,同月3日から5日までの3日間は「+」と記載されていたが,実際には,少なくとも同月5日の基線細変動は確認されていない。8月6日(妊娠38週1日),担当医師は,患者は妊娠中毒症であるが軽症で,腎機能の悪化も見られず,胎児の状況も良好と判断し,退院を許可し,患者に対し,同月11日に診察を受けに来院するよう指示した。担当医師は,退院の際,患者に対し,尿蛋白を検査するための試験紙を渡し,毎日の尿検査を指示するとともに,安静及び食事に留意することを指示し,異常があれば被告病院に連絡するように伝えたが,包括的な連絡指示にとどまり,どのような所見が認められたときに連絡をするのかについて具体的な指示はしなかった。
退院後,患者が,試験紙を用いて尿蛋白の検査をしたところ,連日,「+++」又は「++++」の結果が出た。しかし,患者は,検査結果について,次回の診察時に報告すれば足りると認識しており,特に被告病院に連絡しなかった。8月9日(妊娠38週4日),患者は,午前6時ころから活発な胎動を感じた後,胎動をほとんど感じなくなり,腹部に痛みや緊満感を感じるようになったが,出血も破水もなかったため,被告病院には連絡をしなかった。同日午後11時過ぎ,患者は,腹部の痛みが強くなってきたことから,被告病院に電話をし,看護師に対し,陣痛が始まったようだとして同日朝からの経緯を説明した。対応した看護師は,直ちに来院する必要はないと判断し,痛みが5分間隔になったら来院するよう答えた。8月10日午前2時10分ころ,患者は,突き上げるような出痛みを感じ,出血量を確認するためトイレに入ったところ,同日午前2時15分ころ,胎児を娩出してしまった。胎児は,救急車で市民病院に搬送され,死産と判断されたが,胎盤や臍帯はほぼ正常で,胎児仮死状態は極めて短時間であったと推測される所見が認められた。胎児の身長は43.5cm,休重は1850gであった。患者は,腎機能も含めて概ね良好であったが,血圧1が76/116と極めて高値を示していた。
患者及びその夫が,被告病院を開設する医療法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3300万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 1100万円) | ||||
| 争 点 | ①被告病院は,重症妊娠中毒症を前提に対応すべきであったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①患者の慰謝料 | 800万円 | |||
| ②患者の夫の慰謝料 | 200万円 | ||||
| ③弁護士費用計 | 100万円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
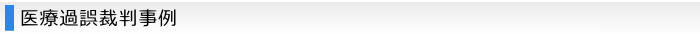
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
出産後に産婦が死亡したことについて,被告の羊水塞栓症の疑いという主張を排斥し,弛緩出血による出血性ショックによる死亡と認め,担当医師に止血,輸血及び転送について適切な措置をとらなかった過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第12643号 損害賠償請求事件
平成17年5月27日判決 確定
【治療・方法時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和48年生,女性)は,平成14年3月25日,被告A医師が開設する産婦人科医院(被告医院)を受診し,妊娠と診断された。患者は,継続的に同医院を受診し,妊娠経過は概ね順調に推移していた。患者は,平成14年11月19日午後4時50分ころ,陣痛が発来したため,被告医院に入院した。担当医師は,当時週1,2回の割合で同医院の当直勤務をしていた被告B医師となり,患者は,同日午後11時53分に男児を出産し,子宮収縮剤(ア卜ニン)1アンプルが投与された。被告B医師は,胎盤娩出後の子宮硬度は良好と判断したが,出血量が通常よりも多く,300-400ml程度あると考え,子宮腔内に卵膜や胎盤片の遺残がないかを調べるためスポンジキューレットを施行し,これがないことを確認した。被告B医師は,患者に対し,膣内へのガーゼ挿入を行い,患者の膣・会陰部の縫合を開始したが,このころ患者の血圧は,131〜134/74〜91で,脈拍数は75ないし90であった。20日午前0時30分ころ,被告B医師は,縫合を終了し,患者の膣内のガーゼを抜去したところ,子宮の収縮はやや良好であった。患者に対し,500mlの電解質液の輸液のほか,止血剤1アンプルや子宮収縮剤(アトニン)1アンプル等が投与された。このころの患者の血圧は99/70,脈拍数は102であった。
患者は,20日午前0時35分ころ,不快を訴え,膣からの流血が多く(少なくとも500ml)認められた。子宮の収縮が不良であったため,同日午前0時37分ころ,患者に対し,子宮収縮剤(メテナリン)1アンプルが投与されるとともに,酸素投与が開始され,膣内に再びガーゼが挿入された。患者は,同日午前0時46分ころ,再び気分の不快を訴え酸素投与量が増加され,血漿剤(サヴィオゾール)500mlが投与された。20日午前0時50分ないし52分ころ,患者の膣内のガーゼを抜去したところ,子宮収縮が不良で,少なくとも500mlの出血が認められたことから,被告B医師は,子宮収縮剤(ア卜ニン)を3アンプル投与した。このころの患者の血圧は90〜92/70,脈拍は70であった。患者は,その後も気分の不快を訴え続け,20日午前1時20分ころ,患者に経皮酸素飽和度を測定するモニターが装着されたが,この時点の飽和度は100%であった。20日午前1時27分ころ,被告B医師が患者の膣内のガーゼを抜去したところ,子宮収縮は不良で,少なくとも500mlの出血が認められた。患者は,痛みを訴えるようになり,被告B医師は,患者に子宮収縮剤(メテナリン)1アンプルを投与したが,同日午前1時37分ころ,患者が,手足の痛みを訴え,助けを求めて叫ぶなど不穏状態となり,被告B医師は,輸血用血液MAP2単位(計400ml)のオーダーを看護師に指示し,患者の夫に対し,輸血の必要性等について説明した。このころ,患者に対し血漿剤(サヴィオゾール)500mlが投与された。20日午前1時50分ころ,被告B医師は,患者に不穏状態が続いたため鎮静剤(セルシン)2分の1単位を投与した。この時点で,経皮酸素飽和度は100%であったが,血圧は85/35に低下し,脈拍数は130に上昇していた。20日午前2時25分ころ,膣内からの出血量がやや減少したが,被告B医師は,患者に対し,右腕の点滴ルートからMAP200mlの輸血を開始し,左腕の点滴ルートから子宮収縮剤や電解質液500ml等が追加投与された。輸血は,20日午前2時40分ころに更新され,計400mlの輸血が午前2時56分ころまでに終了した。このころ,患者の経皮酸素飽和度は88ないし95程度で,呼名反応はあったが,口唇色やや不良,体動著明,背部痛を訴える状態にあった。被告A医師は,20日午前2時30分ころ,被告B医師から患者の出血が継続していることなどについて電話連絡を受け,被告医院を訪れた。被告A医師は,患者の不穏状態が継続しており,膣内に挿入されたガーゼを抜くと500mlには至らないが出血が確認されたことから,患者を緊急に他病院に搬送する必要があると判断した。患者に対し,上記輸血終了後,生理食塩水100mlが投与されていたが,500mlの電解質液の輸液に更新されるとともに,輸血用血液の追加オーダーが行われた。このときの脈拍数は120であり,約5分後の血圧は98/14であった。20日午前3時25分ころ,患者に生理食塩水100mlが投与され,午前3時33分ころ,MAP200mlの輸血が開始された。このころ,患者を甲公立病院に搬送することが決定されたが,この時点で血圧は測定不能の状態で,脈拍数は118であった。20日午前3時40分ころ,左腕の点滴ルートから,電解質液500ml及び子宮収縮剤(アトニン,メテナリン)が投与され,午前3時45分ころ,右腕の点滴ルートから通算4本目の輸血(MAP200ml)が開始された。
20日午前3時53分ころ,到着していた救急車へ患者を搬入する準備中,患者の容態が急変し,心肺停止状態となった。両医師は,直ちに,気管内挿管(ただし,片肺挿管),心臓マッサージ等の蘇生措置を施し,患者を救急車に搬入して甲公立病院に搬送した。患者は,20日午前4時過ぎ,被告医院を出て,午前4時18分ころ,甲公立病院に到着し,蘇生措置が継続されたが,蘇生することなく,同日午前5時34分ころ死亡した。
患者に対し,甲公立病院において病理解剖が実施され,羊水塞栓症の可能性について鑑別されたが,心臓にも肺動脈にも血栓は認められず,羊水塞栓症であれば基準値を超えることが多い母体血清中のSTN値は基準値以下であった。内子宮口に2か所の裂傷が認められ,その部分は,微小血管が破綻し,壊死が認められる状態であったが,著明な血腫は認められなかった。同病院は,患者の死因を弛緩出血を原因とする出血性ショックと診断した。
患者は,分娩後,被告医院で心肺停止状態となるまでの間,羊水込みで少なくとも3100ml出血した。この間の総輸液量は3200ml(分娩前の500mlの輸液を加えると3700ml),総輸血量はMAP4単位(計800ml。4本目の輪血途中で心肺停止状態となった)であった。
患者の夫,子及び両親が,被告A医師及び被告B医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計9214万0242円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額7264万1498円) | ||||
| 争 点 | ①被告医師に,止血及び輸血の各処置並びに他病院への搬送について過失があったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①死亡逸失利益 | 4154万1498円 | |||
| ②死亡慰謝料 | 2000万0000円 | ||||
| ③患者の家族の固有の慰謝料 | 計300万0000円 | ||||
| ④葬儀費用 | 150万0000円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 計660万0000円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
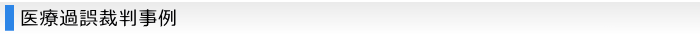
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
陣痛促進剤の使用方法を誤った過失及び分娩監視装置による監視を怠った過失がいずれも認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第8040号 損害賠償請求事件
平成16年3月22日判決
【検査,治療方法,時期,監視義務違反,因果関係】
<事案の概要>
母親は,第3子を妊娠し,平成10年末ころから,被告医院(整形外科・産婦人科を診療科とする病院)で定期的に検診を受けていたが,母親・胎児とも順調で胎児に先天的な疾患等の指摘はなかった。
母親は,妊娠39週2日目の平成11年5月14日午後5時40分ころ,被告医院を受診した。担当医師は,母親に分娩監視装置を装着し,午後5時40分から午後5時50分まで,子宮収縮の状態及び胎児の心拍数を監視したところ,陣痛周期8分,子宮口7.5cm開大,児頭下降度+1,頚管展退70%を認め,既に陣痛が開始しているが,陣痛微弱であると診断して直ちに人工破膜を行うとともに,午後6時母親を入院させ,直ちに陣痛促進剤プロスタルモンEを投与した(1回で2錠服用したか争いあり)。母親が被告医院入院した後,午後7時40分ころまでの問,分娩監視装置による継続的監視はなく,この間,担当医師自ら直接母親を診察したことはなかった。午後7時15分ころ時点で,陣痛周期は5分であった。助産師は,午後7時40分ころ,母親の子宮口開大8cm,陣痛周期が2,3分になったため母親を分娩室に移したが,午後8時25分ころまで,子宮収縮の状態及び胎児心拍数につき,分娩監視装置による継続的監視がなされず,担当医師が直接母親を診察したこともなかった。
助産師が午後8時20分ころドップラーで胎児心拍数を確認したところ,胎児心拍数が不安定であったので担当医師に報告した。担当医師は,内診で子宮口9cm開大,児頭下降度+2を認め子宮収縮の状態及び胎児心拍数を継続的に監視する必要があると考え,午後8時25分ころ,母親に監視装置を装着したところ,胎児心拍数が50から160までの間を繰り返し上下しており,その後も60ないし80程度への低下が繰り返された。
担当医師は,胎児心拍数の所見から,胎児が危険な状態に陥っており,早く娩出する必要があると判断し,午後8時40分ころ,吸引分娩の準備に入り,午後8時45分ころ,陣痛促進剤アトニンの点滴投与を開始し,午後8時48分1回の吸引分娩で,患者(女児)を娩出した。
患者は,出生時体重3096gで,心拍数は問題なかったが,生後1分経っても泣かない等の新生児仮死の状態であった。担当医師は,分娩時の胎児心拍数の低下及び出生後の患者の状態から,一刻も早く小児科医の診療を受けさせる必要があると判断し,午後9時7分,甲病院に電話し,小児科医の同乗するドクターカーの派遣を要請した。甲病院の小児科医は,午後10時に被告医院に到着し,直ちに患者を診察し,筋緊張の強さから,患者が既に痙攣を起こしていると診断し,抗痙攣剤を静脈注射した後,患者をドクターカーで甲病院に搬送した。患者は,搬送中,痙攣を断続的に起こし,セルシンが追加で静脈注射されたが,痙攣を十分に抑えることはできなかった。
患者は,甲病院で診療を受け続けたが,精神運動発達遅滞の後遺障害を負った。
患者が,被告医院を開設する法人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2億円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 1意3477万1733円) | ||||
| 争 点 | ①陣痛促進剤の使用方法を誤った義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①介護費用 | 5743万0560円 | |||
| ②逸失利益 | 4134万1173円 | ||||
| ③後遺障害慰謝料 | 2700万0000円 | ||||
| ④弁護士費用 | 900万0000円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
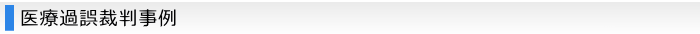
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
産科病室内で生後7日目の乳児に大腿骨骨折が生じたことにつき,病院の不法行為責任が肯定されたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第21750号 損害賠償請求事件
平成15年1月27日判決
【入院管理,看護過失,監視義務違反】
<事案の概要>
患者(母親)は,平成12年1月4日,被告病院(総合病院)の産科において帝王切開術を受け,39週3日で女児を出生した。女児の出生時の体重は3082gであったが,出生後は新生児室に入院となった。
同年1月9日の生後検診で,女児に異常は見られず,同月10日の体温と脈拍数にも異常はなかった。ところが,同月11日早朝,女児の体温が38度2分まで上昇し,昼ころにも,体温が38度,脈拍数が毎分約150回と高い値を示した。
患者の産後の経過は順調であり,1月11日午前11時ころ退院となったが,女児は,発熱のため,同時に退院できなかった。同月12日,女児はいったん解熱したが,左下肢の動きが鈍い状態であった。同月13日朝には,女児の左大腿部に腫脹と発赤が認められ,圧痛も強く認めら,近くの大学病院の小児科を受診したところ,左大腿骨が中央部付近で2つに折れていることが判明した。
女児の発熱状況などから,骨折事故が発生した時間帯は1月10日昼ころから11日早朝までの間と考えられたが,その間に骨折の原因として何が起こったのかは不明であった。女児は,左下肢を固定する措置を受けた後,いったん被告病院に戻り入院を継続し,同月17日,大学病院の整形外科に入院し,骨折に対する治療を受けた。
女児とその両親は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計469万1279円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計223万0240円) | ||||
| 争 点 | 女児が大腿骨を骨折したことについて被告病院の監視義務違反があったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費・交通費・入院雑費 | 21万7740円 | |||
| ②両親の付添看護費用 | 36万2500円 | ||||
| ③女児の慰謝料 | 95万0000円 | ||||
| ④母親の慰謝料 | 50万0000円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 20万0000円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
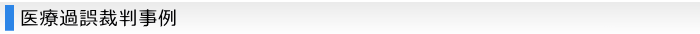
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
妊娠の有無について,問診義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第11299号 損害賠償請求事件
平成14年9月25日判決
【説明義務,問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,女性)は,平成13年6月28日に被告病院(総合病院)を受診し,A医師(消化器内科)に,数日前から吐き気が続いていることを訴えたところ,妊娠の可能性について質問されたことから,同月17日から生理があったが不順であった旨答えた。A医師が,「妊娠は大丈夫ですね。」と質問したところ,患者は否定しなかった。A医師は,問診の結果,生理不順はあるが,月経があったと判断し,妊娠の可能性についての患者の回答等も考慮し,妊娠の可能性はないと判断し,それ以上質問しなかった。A医師は,吐き気が続いていることから,胃腸の病気を疑い,吐き気等に対する処置として胃腸機能調整薬であるナウゼリン等を処方するとともに,鑑別診断をするため採血と腹部レントゲン撮影を指示した。
患者は,同年7月4日,被告病院を受診し,上部消化管内視鏡検査を受けた後,B医師(消化器内科)から問診を受け,薬を服用しないと吐き気が起こると訴えたほか,B医師からの妊娠に関する質問に対し,同年6月17日と18日の2日間に生理があったと答えた。B医師は,生理が2日間という答えであり,吐き気が続いていたことから,生理ではなく妊娠初期の月経様出血の可能性もあると考え,妊娠反応検査を指示し,患者がその指示に従って妊娠反応検査を受けたところ,陽性であった。
患者は,同年7月10日,被告病院から紹介を受けた病院で人工妊娠中絶手術を受けた。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 372万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額80万円) | ||||
| 争 点 | A医師には,患者が妊娠しているか否かを確認するための問診ないし検査をすべきであったにもかかわらず,これを怠った過失があるか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 70万円 | |||
| ②弁護士費用 | 10万円 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
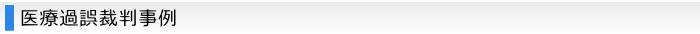
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
子宮全摘術の実施について説明が不十分であったとして自己決定権侵害が認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第5428号 損害賠償請求事件
平成15年8月29日判決
【説明義務,問診義務,損害論,自己決定権侵害】
<事案の概要>
患者(昭和26年生,女性)は,平成12年8月30日に,外陰部のかゆみと不正出血を訴え,被告病院(総合病院)を受診し,子宮頸部細胞診を受けた。同年9月6日,患者は,被告病院を受診し,A医師(産婦人科)から,8月30日に実施した細胞診検査の結果がⅢaであり,異形成上皮であるとの説明を受け,同年9月19日,被告病院において,癌検診の精密検査を受けるよう指示された。
同月19日,患者は,B医師(大学の産婦人科教授)の診察を受け,細胞診の再検及び生検組織診等を受け,同月26日,B医師から,細胞診検査の結果がⅡであると説明され,3か月後の受診を指示された。
同年10月10日,患者は,頻尿・尿漏れがあったことから,被告病院を受診した。その際,C医師(産婦人科)に,細胞診の結果について質問したところ,C医師は,クラスⅢaは軽い異形成のレベルであり,再検査ではクラスⅡで異常ではないので,すぐ手術をする必要はなく,3か月後に再検査したらどうかと説明した。これに対し,患者は,心配しながら検査を受けに来るのは非常に億劫である,子宮を切除すれば心配ないのではないかと手術を希望したので,C医師は,仮に手術をするにしても,子宮頸部を円錐状にレーザーで切除するレーザ一円錐切除術という方法もあることを説明したが,その場合も検査を定期的にする必要があるため,患者は,子宮全摘術を希望した。
C医師は,患者に対し,子宮全摘術を実施することとし,同年11月8日,C医師の執刀で,子宮全摘術及び右卵巣摘出術(本件手術)が行われた。術後の病理組織検査では,子宮腺筋症であり,悪性所見はないと診断された。
患者が,被告病院を開設している地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2000万円及び生存中の生活費等として毎月100万円等 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額80万円) | ||||
| 争 点 | 担当医師が,子宮癌でないことを知りながら,患者に,子宮癌であると偽って宣告し,子宮全摘術をすれば助かると思わせるような説明をし,本件手術を実施したか。 | ||||
| 認容額の内訳 | 慰謝料 | 80万円 | |||
| 判 断 | 否定、虚偽の説明をして手術を実施したとは認められない。患者が正確に理解できるよう十分に説明すべき義務があったにもかかわらず,説明義務を十分に履行しなかった過失があり,自己決定権を侵害した。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
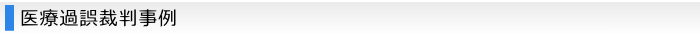
産婦人科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
常位胎盤早期剥離の診断の遅れについて当直医の不法行為責任が肯定されたケース
東京地方裁判所 平成11年(ワ)第18965号 損害賠償請求事件
平成14年5月20日判決
【治療方法,時期,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者は,平成10年5月26日(妊娠35週5日)午前4時ころ,下腹部の胎盤のある辺りに痛みを感じ,痛みが軽減しないので心配になり,午前6時ころ,被告病院(大学病院)産婦人科に1回目の電話をかけた。電話に出た当直医(産婦人科)は,患者の訴えを聞いて,ウテメリンを服用して安静にするように指示した。患者は,ウテメリンを服用したが,下腹部痛が治まらず,気分が悪くなって嘔吐したため,夫の運転する自動車で,午前7時ころ,被告病院を訪れた。
当直医は,午前7時10分ころ,助産師とともに一般的診察を開始した。腹部は非常に硬い状態であったが,当直医は,常位胎盤早期剥離の症例を扱った経験がなく,切迫早産の子宮収縮による硬さであると考えた。患者には性器出血,破水は見られず,子宮口の開大もなかった。当直医は,午前7時20分ころ,助産師に対し分娩監視装置の装着を指示したが,トランスデューサで胎児の心臓の位置を捜し当てることができなかった。当直医が交替して試みたが,心臓の位置を捜し当てることはできなかった。そこで,超音波検査装置による測定に切り替え,午前7時30分ころ,胎児心拍数が毎分80(胎児心拍数の正常値は毎分120から160であり,120を下回ると徐脈,100を下回ると高度徐脈と判定される。)であることを確認した。
午前7時35分ころ,当直医は,医局の助手から,電話で,高度徐脈が一過性のものか継続するものかに注意を払い,徐脈が続くときには母体に酸素を供給するよう指示を受けた。午前7時40分ころになっても,徐脈が回復せず,当直医は,胎児仮死を疑い,助産師に対しウテメリンの点滴と酸素の投与を指示し,午前7時45分ころ,ウテメリンの点滴が開始された。当直医は,超音波検査で胎盤の肥厚を認めず,性器出血もないことなどから,徐脈の原因を,常位胎盤早期剥離よりも,切迫早産の子宮収縮が過強的に起こっているためと考え,胎児の体位変換により徐脈が回復する可能性を考え,触診などをしながら経過を観察した。
午前7時50分ころ,助手が被告病院に到着し,患者の腹部を触診して,常位胎盤早期剥離を疑った。徐脈は毎分60から70に悪化し,ウテメリンの点滴量を増やしても回復しなかったため,助手は,午前8時ころ,常位胎盤早期剥離を強く疑い,点滴を中止して緊急帝王切開術の施行を決断した。
午前8時42分,帝王切開術が開始され,午前8時45分,女児が重症新生児仮死の心停止状態で出生した。体重は1934gで,ぐったりして啼泣もなく,出生1分後のアプガースコアは0で,著しい代謝性アシドーシスになっていた。
出生から3年後,患者(女児)は,重症新生児仮死後の低酸素性虚血性脳症,脳性麻痺(四肢),てんかん(ウエスト症候群),精神発達遅滞,皮質盲(後頭葉にある皮質視中枢が障害され視覚を喪失している状態)と診断され,摂食,排泄,体位交換など全面的に介助を要する状態であった。
出生した患者(女児)とその両親は被告病院を開設している国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億5027万1080円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計660万円) | ||||
| 争 点 | ①患者の来院後,速やかに分娩監視装置等により胎児心拍数の計測を行わなかったことに過失があるか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 600万円 | |||
| ②弁護士費用 | 60万円 | ||||
| 判 断 | ①,②過失肯定、③因果関係否定。 | ||||



| 当法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




