光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
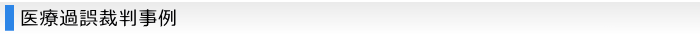
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
初診時のMRl(FLAlR法)検査で出血所見が認められなかったことから,くも膜下出血の鑑別に必要な検査等を行わなかった医師に過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4032号 損害賠償請求事件
平成18年2月10日判決 確定
【説明・問診義務,検査】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,女性)は,平成13年8月17日ころから左眼窩部に針で刺すような痛みを覚えるようになり,同月19日,肩こりを感じてマッサージをしてもらうということがあったが,同日午後9時ころ,突然激しい頭痛を覚えたため夜間緊急医療機関を受診した。患者は,当直の内科医に対し,頭痛及び吐き気を訴え,頸椎の圧痛が認められるとされたが,同医師は,頭痛が続いたときCT検査を行うこととして,鎮痛剤の坐薬等を処方しただけで特に検査を行わずに患者を帰宅させた。患者は,坐薬で頭痛が緩和されたため,8月20日以降,医療機関を受診しないでいたが,同月22日ころまで頭痛は続いており,同月21日ころから左眼瞼の下垂が生じ,同月23日ころから複視も出現し,左眼窩部痛も継続していた。患者は,8月20日から実家に帰り,同月23日夜,自宅に戻ったが,夫と相談し,翌24日,被告病院(大学病院)を訪れ,病院側の指示でまず眼科を受診し,その後,脳神経外科で担当医師の診察を受けた。担当医師は,患者に対する問診で患者が8月17日に針で刺すような左眼窩部痛が生じ,同月19日,肩こりのためマッサージを受けた6時間後,歯磨き中に突然重度の頭痛が生じたことから,救急病院を受診し,坐薬を処方されて頭痛は治まったが,同月22日まで頭位によって頭痛があり,同月21日からは左眼瞼下垂,同月23日からは複視が現れ,眼窩部痛が継続している状態であることを認識した。診察の結果,患者に,左眼瞼下垂・対光反射遅延,瞳孔不同(左が右よりも大きい)等の症状を認めたことから,担当医師は,「卜ローザハント症候群疑い 除外すべきもの・動脈瘤」と診断し,直ちにMRI及びMRA検査を行う必要があると判断し,近接するクリニックで検査ができるように手配した。患者は,同クリニックで,8月24日昼過ぎころから,頭部MRI検査及び頭部MRA検査を受けた。MRI検査では,T1強調,T2強調,FLAIR法で撮影され,軸断,冠状断方向及び造影の有無で計7回撮影が行われたが,FLAIR法で損影されたのは,軸断方向1度のみであった。
患者が,MRIフィルムを持参して同日再度担当医師の診察を受けたところ,担当医師は,フィルムを見て,明らかな海綿静脈洞部の異常はなく,MRAについて特記すべきものはないと診断をした。担当医師は,MRI上は異常がないが,症状から,患者につきトローザハント症候群が強く疑われると考え,同症候群に効果のあるステロイド(リンデロン)を処方して経過を観察することとした。担当医師は,次回外来担当日である8月29日に受診するよう患者に指示するとともに,同月27日にも外来を受診するよう指示し,同日の外来担当医にも,患者が同日に受診予定であること及び症状を見てステロイドの減量を指示することを依頼した。患者は,帰宅後も頭痛が治まらないことから,2人の子どもを夫の両親に預け,患者の母に泊まり込みでの付き添いを頼んだ。患者は,8月25日未明,意識障害を窺わせる言動をし,同日の日中も頭痛を訴え横になっていたが,同日夜,頭痛がこらえられなくなり被告病院に電話をし,頭痛がひどくて我慢ができない,このまま死ぬようなことはないかなどと問い合わせたが,当直の脳神経外科医は,処方された薬を飲んでおくようにとの指示をしただけであった。患者は,電話の際,同日未明の意識障害を窺わせる言動については,特に伝えなかった。患者は,被告病院で処方されたステロイドを指示どおり服用し続けたが頭痛は軽快せず,ほとんど横になった状態で,食欲もない状態であった。8月27日,患者は,被告病院を再診し,初診時とは別の医師の診察を受けた。同医師は,患者の動眼神経麻痺が悪化している上,8月24日に撮影されたMRAに動脈瘤の可能性のある所見を認めたことから,担当医師にその旨を連絡した。担当医師は,直ちに患者を診察し,患者から,週末ずっと寝ており,眼瞼下垂の増悪のほかには症状の変化は自覚していないことなどを確認し,他覚所見として,眼瞼下垂の明らかな増悪,動眼神経麻痺の悪化等を認め,リンデロンがまったく無効であったと認識した。担当医師は,初診時に撮影されたMRAを再確認し,左内頸動脈後交通動脈分岐部付近に,4㎜X8㎜大の動脈瘤の可能性のある所見を認めたため,3D-CTによってこれを確認することとした。
8月27日午前11時前ころから,患者に対する3D-CT撮影が開始されたが,同日午前11時05分ころ,患者はCT台上で突然全身痙攣を起こし,意識レベルが低下した。担当医師は,直ちに挿管の上,単純CT撮影を行ったところ,くも膜下出血が認められ,3D-CTにより左内頸動脈後交通動脈分岐部に動脈瘤が確認された。緊急開頭クリッピング術が実施されたが,患者には,右上肢機能全廃及び両下肢機能全廃,高次脳機能障害等の後遺障害が残った。
患者及びその夫が,被告病院を開設する地方公共団体及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億8786万3549円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 1億5999万7915円) | ||||
| 争 点 | ①初診時に,くも膜下出血を疑いさらに検査すべき義務の有無 ②担当医師に,初診後帰宅した患者から被告病院に症状に関する問い合わせがあった場合に備え,くも膜下出血を疑うべき所見があることを診療録等に記載し,他の医師等に伝えるべき義務を怠った過失があるか。 | ||||
| 認容額の内訳
| 1 患者本人の損害 | (1)治療費等 | 計37万0378円 | ||
| (2)退院時までの付添看護費 | 178万2000円 | ||||
| (3)将来の付添看護費 | 5399万9560円 | ||||
| (4)入院雑費 | 42万1200円 | ||||
| (5)休業損害 | 310万5251円 | ||||
| (6)後遺症逸失利益 | 5727万9526円 | ||||
| (7)入院慰謝料 | 364万0000円 | ||||
| (8)後遺症慰謝料 | 2600万0000円 | ||||
| (9)弁護士費用 | 900万0000円 | ||||
| 2 患者の夫の損害 | (1)慰謝料 | 400万0000円 | |||
| (2)弁護士費用 | 40万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
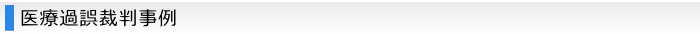
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
未破裂脳動脈瘤の手術について説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第4578号 損害賠償請求事件
平成17年7月29日判決 控訴・和解 判タ1210号227頁
【説明ー問診義務,入院管理,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和6年生,男性)は平成12年7月18日,浮遊感,全身倦怠感,嘔気,軽度の回転性めまいを訴え,被告病院(総合病院)に救急搬送され入院した。同月21日,MRA検査の結果,左内頸動脈頭部分岐部に狭窄,左中大脳動脈水平部に未破裂動脈瘤様所見が認められ,後日精査することにして患者はいったん退院した。
8月24日,脳血管撮影が実施され,左内頸動脈と椎骨動脈の分岐部に約50%の狭窄が認められ,未破裂脳動脈瘤が2個みつかった。同年9月19日,患者は,担当医師の勧めで未破裂脳動脈瘤をラッピングしてコーティングする手術を受けたが,手術直後てんかん重積発作を起こし,遷延性意識障害となって,平成14年3月18日死亡した。
患者の家族(妻及び子2名)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4097万9105円(一部請求) | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計3119万1106円) | ||||
| 争 点 | ①未破裂脳動脈瘤に対する手術の適応の有無 ②手術についての説明義務違反の有無 ③術前・術中・術後における管理に関する過失の有無 ④①ないし③の過失と死亡との因果関係の有無 | ||||
| 認容額の内訳
| ①治療費・入院雑費 | 138万9700円 | |||
| ②逸失利益 | 1465万1008円 | ||||
| ③慰謝料 | 1600万0000円 | ||||
| ④遺族固有の慰謝料 | 合計400万0000円 | ||||
| ⑤葬儀費用 | 120万0000円 | ||||
| ⑥弁護士費用合計 | 280万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
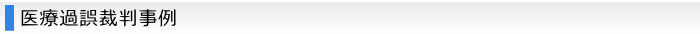
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
入院中,患者が脳動脈瘤の再破裂を起こして死亡したことについて,担当医師の過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第8065号 損害賠償請求事件
平成17年3月24日判決 確定
【検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和7年生,女性)は平成12年2月10日,入浴中,急に頭痛と嘔気が出現したため,被告病院(総合病院)に搬送され入院した。症状の原因は,脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血であり,事後的に見ると,左内頚動脈後交通動脈分岐部と脳底動脈先端部に動脈瘤が存在し脳底動脈瘤が破裂したものであった。翌11日,担当医師により,脳血管撮影検査が行われた後,開頭クリッピング手術が行われたところ,内頚動脈瘤に対してクリッピングされたが,脳底動脈瘤に対しては何らの処置もされなかった。
同年3月10日,患者は,入浴中,脳底動脈瘤が再破裂し,同月16日に死亡した。
患者の遺族が,被告病院を開設している法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6642万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計4007万円) | ||||
| 争 点 | ①開頭クリッピング手術後,早急に,脳血管撮影検査や3次元CT血管撮影検査を実施し,脳底動脈瘤の存在を確認すべきであったか。 ②3月8日,3次元CT血管撮影検査の断層画像で脳底動脈瘤の存在を確認した後,直ちに入浴を禁止すべきであったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 1297万円 | |||
| ②慰謝料 | 2200万円 | ||||
| ③葬儀関係費用 | 150万円 | ||||
| ④弁護士費用 | 360万円 | ||||
| 判 断 | ①血管撮影検査の結果,脳底動脈先端部に動脈瘤様所見を認めていること,クリッピングを行った内頚動脈瘤が破裂脳動脈瘤であるとの確証を得られず,脳底動脈先端部の動脈瘤の存否は高位だったため確認できなかったことから,担当医師は,脳底動脈先端部に動脈瘤が存在する可能性があり,それが破裂脳動脈瘤の可能性があることを認識していた。従って,担当医師は,脳底動脈先端部の動脈瘤の存否確認のため脳血管撮影検査又は3次元CT血管撮影検査を実施し,その存在が確認されたときは破裂した動脈瘤である可能性が小さいと判断できない限り,クリッピング手術又はコイル塞栓術を実施する注意義務を負っていた。 ②担当医師は,3月10日午前9時20分ころ,3次元CT血管撮影検査の断層画像上,脳底動脈瘤が存在し,破裂脳動脈瘤の可能性が高く,大きさが2月11日の時点から増大している可能性があると判断したのであるから,その時点で安静の指示,特に入浴を禁止する措置を講ずべき注意義務があった。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
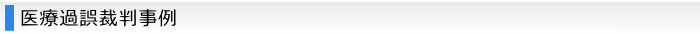
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
くも膜下出血を診断するための十分な問診,検査を行わなかった過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6489号 損害賠償請求事件
平成15年10月29白判決
【説明義務,問診義務,検査,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和20年生,男性)は,平成8年9月5日午後7時45分ころ,車を運転中に激しい頭痛を覚え,直後に嘔吐した。患者は,同月6日,激しい頭痛と嘔気のため,会社を欠勤し終日臥床していたが,同日夕方,担当医師が開設する被告診療所(脳神経外科を標傍する個人病院)を受診した。担当医師は,くも膜下出血を含む病変の可能性を認識していたが,問診の結果,患者の頭痛等は,発症前日にアルコールを多飲した後に激しい運動をしたことによるものであると判断し,CT撮影をなさず(診療所にはCT機器はなかった),CT検査が可能な医療機関に転医させることもせず,くも膜下出血ではないと判断し,鎮痛剤を処方したのみで患者を帰宅させた。
患者の頭痛と嘔気はその後も持続し,担当医師を受診した4日後である同月10日午後11時ころ,意識を消失して救急搬送され,搬送先の病院でくも膜下出血と診断され同月27日に死亡した。
患者の妻及び子2名が,担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7087万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計6965万8969円) | ||||
| 争 点 | ①患者は,担当医師を受診した平成8年9月6日当時,くも膜下出血を発症していたか ②担当医師がくも膜下出血ではないと診断したことに過失があるか,担当医師は,患者の症状を正確に把握するための問診を十分に行ったか,担当医師は,くも膜下出血を否定するのに十分な検査を行ったか ③担当医師が患者のくも膜下出血発症を発見していれば,患者の死亡を回避できたか否か | ||||
| 認容額の内訳 | ①葬儀費用 | 100万0000円 | |||
| ②逸失利益 | 3632万8971円 | ||||
| ③慰謝料 | 2600万0000円 | ||||
| ④弁護士費用 | 633万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
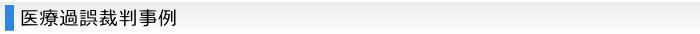
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脳動脈瘤に対するコイル塞栓術につて説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成9年(ワ)第23169号 損害賠償請求事件
平成14年7月18日判決
【説明義務,問診義務,手技,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和9年生,男性)は,被告病院(大学病院)において,左内頸動脈分岐部の未破裂動脈瘤に対し,当初,開頭手術を受ける予定であったが,平成8年2月27日,A医師(放射線科)及びB医師(脳神経外科)の説明を受けて,コイル塞栓術を受けることに同意した。
被告病院において,同月28日午前11時5分ころ,患者に対し,コイル塞栓術(本件手術)が施行された。手術の際,IDCコイルの約半分を脳動脈瘤内に挿入したところ,コイルが脳動脈瘤外に逸脱して内頸動脈内に移動してしまい,中大脳動脈及び前大脳動脈を塞栓する可能性があったため,正午ころまでに,A医師は,コイル塞栓術の中止とコイルの回収を決めた。
A医師は,デリパリーワイヤーを引いてコイルを回収しようとしたが,コイルが伸びる「ほどけ現象」が生じたために功を奏さなかった。午後O時40分ころ,リトリーパーを使ってコイルを回収しようとしたが,全部を回収することができないまま,午後O時50分ころ,患者の左中大脳動脈の血流が悪化し,意識レベルの低下等の症状が現れた。
被告病院の医師らは,開頭手術によりコイルの回収をすることとしたが,午後4時ころまでは手術室に入室できなかったため,A医師は,リトリーパーを用いたコイル回収作業を午後2時50分ころまで継続した。
午後5時15分ころ,B医師の執刀で開頭手術が開始され,午後9時25分ころから,コイルの一部が摘出され,脳動脈瘤クリッピング手術が施行されたが,コイルを全部除去することはできなかった。
患者は,開頭手術後,意識を回復することなく,平成9年3月13日,残存したコイル及びこれによる血流障害で引き起こされた脳梗塞により死亡した。
患者の家族らが,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計 9573万5673円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 合計6636万6688円) | ||||
| 争 点 | ①本件手術を選択したことについて過失があったか否か ②本件手術の手術手技に過失があったか否か ③説明義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 合計4202万6688円 | |||
| ②慰謝料 | 合計1750万0000円 | ||||
| ③葬儀費 | 84万0000円 | ||||
| ④弁護士費用 | 合計600万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
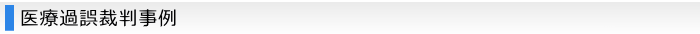
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
神経サルコイドーシスに罹患していた患者について,検査結果及び診察結果からは神経サルコイドーシスを疑わせる所見はなく,医師が当時の臨床所見等から脳腫瘍であると診断したことはやむを得なかったとして,神経サルコイドーシスの確定診断が遅れたことに過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第9818号 損害賠償請求事件
平成14年7月31日判決
【診断,手技,検査】
<事案の概要>
患者(昭和5年生,男性)は,平成8年3月29日,左眼の視力低下等を訴えて被告病院(総合病院)の眼科を受診した。頭部CT上,脳梗塞等の異常所見は認められず,左虚血性視神経症の診断で,患者に対し,ステロイド剤投与による治療が行われた。
患者は,平成9年5月9日,左眼の眼圧が高く,左眼隅角に結節が認められ,左眼虹彩炎も出現したことから,眼科医師は,肉芽腫性ぶどう膜炎とそれを生じる疾患のサルコイドーシスを疑ったが,点眼薬の投与で,同月23日には,虹彩炎及び左眼隅角の結節が消退し,左眼の眼圧も低下した。
患者は,同年6月に頭部CT検査を,同年8月に胸部レントゲン検査を受けたが,サルコイドーシス罹患を疑わせる異常所見は認められなかった。
患者は,同年10月,両側側頭部痛,左動眼神経麻痺を生じ,神経内科に入院したが,検査の結果,異常所見は認められず,左眼球運動も正常化した。
患者は,同年12月,複視を訴えて受診し,検査の結果,30%程度の右外転神経麻痺が認められ,遊走性脳神経麻痺の診断でビタミン剤が処方されたが,平成10年l月には治癒した。
眼科医は,平成10年7月31日,患者の右眼に比較的強い虹彩炎と,左眼に軽度の虹彩炎が出現し,眼圧が上昇し,両眼の隅角にテント状の周辺虹彩前癒着,左眼隅角に結節が認められたため,サルコイドーシスを疑ってアンギオテンシン変換酵素(ACE)の測定を指示し,眼の症状に対しては点眼薬投与を行った。ACE検査値は上昇していたので,胸部レントゲン検査が実施されたが,両側肺門リンパ節腫大(BHL)等のサルコイドーシスを疑う所見は認められず,両眼の虹彩炎も鎮静化したため,サルコイドーシスの確定診断には至らなかった。
患者は,同年10月9日,頭痛を訴えて循環器内科を受診し,同月14日に頭部CT検査を受けたところ,透明中隔部の腫瘍が発見され,同月16日,脳神経外科で神経膠腫が最も疑わしいと診断された。脳神経外科は,患者の頭痛が激しく進行性の症状であったことや治療方針を決めるため開頭手術して組織の病理診断を行う必要があったため,手術適応と判断した。
同年11月4日,患者に対し,開頭手術(本件手術)が実施されたが,術中に実施された迅速診断の結果,組織は上皮性肉芽腫であり,悪性ではないことが判明し,同月10日,術中標本の病理組織検査で,神経サルコイドーシスが最も疑わしいと診断され,本件手術後施行された各検査の結果,同年12月11日,神経サルコイドーシスの確定診断がなされた。
患者は,平成11年2月に退院したが,同年3月から四肢筋力低下と,体幹失調を訴えるようになり,これらの症状は,ステロイド療法により改善した。
患者は,体幹失調による歩行困難,立位保持困難,両大腿部の筋力低下の障害を生じ,身体障害者福祉法別表障害等級2級の認定を受けた。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 4536万6720円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①サルコイドーシスの確定診断が遅れた過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
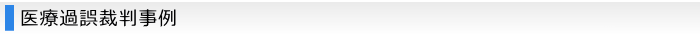
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
定位的血腫吸引術について手術適応の判断や手術手技などに過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第10757号 損害賠償請求事件
平成15年2月19日判決
【手技,手術適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(大正2年生,女性)は,平成11年2月ころから物忘れが酷くなっため,同年3月3日,近医を受診して頭部CT検査を受けたところ,右前頭葉に出血があって記憶障害の原因となっている可能性があると診断された。患者は,精査目的で,同月6日,甲病院(大学病院)脳神経外科を受診した。その際,患者の息子から医師に対し,患者の様子が急におかしくなり,失禁もあると説明され,検査の結果,患者には,近位記憶障害や,日付が分からなかったり,計算ができない等の症状があり,頭部MRI上,右前頭葉に血腫及び側脳室前角の軽度の圧迫が認められた。甲病院の医師は,患者に比較的新しい出血があると考え,入院を勧めたが患者は入院しなかった。
患者は,同月26日,息子に伴われて被告病院を受診し,A医師の診察を受けた。患者の息子は,A医師に対し,患者の物忘れがひどくなったなどと説明した。患者は,日付を答えることができず,軽度の片麻痺があり,頭部MRI上,右前頭葉の脳内出血と左前頭葉の脳挫傷の痕が認められた。A医師は,患者の息子に対し,血腫を除去すれば症状が改善する可能性があると述べ,定位的血腫吸引術の説明をした上で,患者が高齢(当時86歳)で血管が脆くなっていることを考慮し,手術をするか否か検討することとした。
患者は,同月27日,被告病院に入院したが,徘徊が見られた。患者の息子は,患者を大学病院に転院させたいと考え,同月29日,被告病院から退院させて甲病院を受診させたが,甲大学病院の医師は,患者が看護の適応であることを理由に治療及び検査を断った。
患者の息子は,同年4月9日,患者を再び被告病院に受診させ,定位的血腫吸引術を受けることを希望した。患者は,同月12日,被告病院に入院し,B医師の執刀で定位的血腫吸引術が実施された。術後,B医師は,頭部MRI上,吸引した血腫のあった位置より後方に,淡い白い影が映っているのを確認したが,動脈性術後出血ではなく老齢化による血管の変性によるアミロイド性の出血であり,保存的治療で対応できると判断し,ステロイドの点滴を行った。
患者は,翌13日朝,意識障害を生じ,左片麻痺が悪化し,CT上,血腫が拡大しており,脳の変位が認められたことから,動脈性の出血があり,命にかかわるので手術が必要と判断され,開頭手術が実施され,約100ccの血腫が吸引除去された。
その後,患者には,重篤な脳障害が残り,平成12年11月10日,死亡した。
患者の家族が,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3939万3730円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①定位的血腫吸引術に緊急の必要性や有効性があったか否か(手術適応) | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
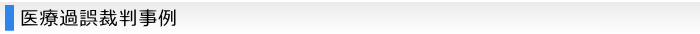
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脳動脈瘤の手術後の経過観察及び再発防止措置等について過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第11968号 損害賠償請求事件
平成15年3月12日判決
【説明義務,問診義務,入院管理,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,女性)は,昭和59年11月5日,被告病院において左内頚動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し,同日,被告病院に入院し,左内頚動脈後交通動脈分岐部にあった動脈瘤に対し,クリッピング術(本件手術)を受けた。
担当医師は,患者に対し,平成3年8月6日,CT検査を,同年9月4日,脳血管造影を各々行ったが,それ以後,CT,MRI,脳血管撮影のいずれも実施しなかった。
被告病院は,平成8年9月2日から,患者に対して,脳代謝改善剤ヘキストール及び脳循環改善剤スプランの投与を行ったが,同年10月5日,担当医師は,これらの投与を中止した。
患者は,平成11年6月10日,本件手術部位付近に生じた左内頚動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し,同月17日死亡した。
患者の夫が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3965万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①担当医師が,脳代謝改善剤及び脳循環改善剤の投与を中止したことが,脳動脈瘤破裂についてのクリッピング術施行後の患者に対する再発又は新生動脈瘤の発生防止のための治療として不適切なであったか否か | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
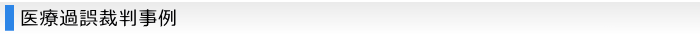
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
CT検査において,頭皮下の金属片の存在を看過したことに過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第695号 損害賠償請求事件
平成15年8月27日判決
【検査,因果関係】
<事案の概要>
患者(男性)は,同僚と喧嘩をしてパイプ椅子で頭部を殴られて怪我をし,頭部痛を訴えて被告病院を受診した。被告病院の脳外科医師は,患者が殴られた左頭頂部付近にたんこぶが1か所あり,若干の出血,擦過傷が認められたが,ほかに創傷が認められず,嘔吐もなく,神経学的な異常所見は認められず,頭部CT及び頭部レントゲンでも異常が認められなかったことから,頭部外傷Ⅰ型(頭部打撲)と診断し,嘔吐の症状などがあればすぐに来院するよう指示して,患者を帰宅させた。その後,患者は,ふらつきや鈍痛の症状を訴えて,数回,被告病院を訪れ,めまいに対する投薬を受けた。
患者に対し,2回頭部CT検査が実施され,その画像上,左前頭側頭部のこめかみと眉毛の境目辺りの皮膚直下に約1.5mm大の金属片が写っていたが,診察を担当した医師は金属片の存在に気付かなかった。
患者が,その後,別の病院で検査を受けたところ,左側頭部皮膚直下に金属片が混入していることが判明した。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 550万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①担当医師に,患者の左側頭部皮膚直下に混入していた金属片に対する適切な処置を怠った注意義務違反ないし過失があるか否か | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
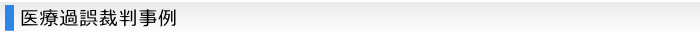
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
くも膜下出血で死亡した患者について,問診・検査義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第28809号 損害賠償請求事件
平成15年11月27日判決
【説明・問診義務,検査義務】
<事案の概要>
患者(昭和40年生,男性)は,平成14年1月5日午前11時過ぎ,職場近くの被告病院(脳神経外科専門病院)を訪れ,受付担当者に症状を話して診察申込用紙に記入した上で,担当医師の診察を受け,担当医師に対し,前日から後頭部痛でよく眠れなかったこと,頭痛薬を飲んで出勤したことを説明した。
担当医師は頭部CT検査(本件CT検査)及び頚椎のレントゲン検査を行ったが,本件CT検査及びレントゲン検査の結果から異常を示す所見は認められなかったため,患者に対し,本件CT検査の結果に異常がないことを説明した。担当医師は,患者の頭痛が片頭痛と緊張性頭痛(筋性頭痛,筋緊張性頭痛,筋収縮性頭痛)の混合型の可能性が高いと考え,片頭痛薬であるジヒルデルゴット,ロキソニン及び緊張性頭痛に有効とされる精神安定剤コンスタンを処方し,患者を帰宅させた。
患者は同月24日夜にくも膜下出血を発症し,翌25日午前6時,搬送先の病院で死亡した。
患者の妻及び子1名が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億2788万4115円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 担当医師が,患者に対して十分な問診をした上で,CT検査だけでなく直ちに髄液検査等のくも膜下出血の診断に必要な検査を行って適切な治療を施すべきであったか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
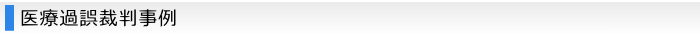
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
医師が患者の小脳出血の発症を見逃したとはいえず,脳梗塞に対する治療の過誤も認められず,小脳出血後の開頭血腫除去術が遅れた過失も認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第2184号 損害賠償反訴請求事件
平成15年12月24日判決
【検査,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和5年生,女性)は,平成9年5月6日,午前8時ころに自宅で転倒しているところを家人に発見され,頭部打撲があったことから,同日午前9時ころ,被告病院に救急搬入された。担当医師は,患者に軽度のせん妄状態,呂律困難,左上肢の脱力が認められ,脳CT検査で陳旧性の小さな脳梗塞が認められたが,脳出血は認められず,患者に脳梗塞の既往歴があったことから,脳血栓性の脳梗塞の疑いと診断した。担当医師は,患者に対し,同日正午ころから,ソルデム3Aを毎時80ml,ソルデム3A200mlにキサンボン4Aを溶解したものを2時間程かけて点滴静注した。
患者は,同日午後6時30分ころ,容態が急変し,嘔吐,全身発汗,四肢の動き緩慢,血圧上昇が見られ,10分後には,意識レベルが低下し,左上肢と両下肢に麻痺が出現し,同日午後7時ころの頭部CTでは,左小脳出血が認められ,同日午後8時ころ緊急脳血管造影検査が実施され,同日午後10時ころから開頭血腫除去術が実施された。
患者は,平成14年5月22日,肺炎により死亡した。
被告病院を経営する法人が,患者の家族に対し,債務不存在確認の訴えを提起したのに対し,患者の家族が,同法人に対し損害賠償請求の反訴を提起した(債務不存在確認の訴えは取下げられた)。
| 請求金額 | 1313万0900円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①担当医師は,患者が当初から小脳出血を発症していたのを見逃したか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
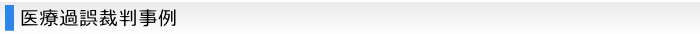
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脳動脈瘤の血管内治療後,大腿部に仮性動脈瘤が生じ,右大腿神経損傷の障害が残ったことについて,血管内治療時の止血手技の過失及び術後の経過観察義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第9228号 損害賠償請求事件
平成18年3月17日判決 控訴
【手技,検査,入院管理】
<事案の概要>
患者(本件当時58歳,女性)は平成15年9月22日,被告病院(総合病院)を受診し,MRA検査等で脳動脈瘤の存在が疑われたため,同月24日,被告病院に入院しA医師(脳神経外科)が主治医となり,脳底動脈先端部の動脈瘤に対し,血管内手術(GDC塞栓術)が施行されることとなった。10月8日,患者に対し,B医師(脳神経外科)の執刀で塞栓術が施行された。午後O時15分ころ塞栓術が終了し,B医師の監督の下,C医師(脳神経外科)によりクローザーによる穿刺部の止血が試みられたが止血できなかったため,直ちに徒手的な圧迫止血が開始されプロタミン2ccの投与,砂嚢及び圧迫帯による圧迫が行われ,午後7時ころ,圧迫が解除された。患者が,午後7時50分ころから,何度も穿刺部周囲から大腿にかけての疼痛を訴えたため,鎮痛剤,眠剤等が投与されたが,患者は,右下肢全体のだるさを訴え,朝方までほとんど眠れない状態であった。この間,穿刺部に新たな出血は認められず,徒手筋力テスト上,異常は認められなかった。同月9日の血液検査の結果,赤血球数366万,ヘモグロビン11.5,ヘモグロビンの割合72%,ヘマトクリット値34.7であった。同月10日,右大腿部の穿刺部痛,皮下出血,硬結及びしびれがあり,同月11日午後3時ころ疼痛が増強し,右大腿から下腿内側にかけて疼痛があったが,徐々に疼痛は改善され,鎮痛剤による疼痛コントロールができていた。
同月14日になって,患者の右下肢痛が増強し,痛み止め投与後も痛みが増強したため,A医師が患者を診察したところ,皮下血腫は治まってきていたので,同医師は,血腫により血流障害が起きていることによるこむら返り様の痛みと考え,患部を温めることなど指示した。同日夜,患者は,再び右大腿部内側の痛みを訴え,痛み止めが投与されたが痛みが治まらず,当直医の指示で鎮痛剤が筋肉注射されたが,右下肢痛を訴えてパニック症状を呈したため,鎮痛剤及び鎮静剤が静脈注射された。その結果,15日未明ころには,下股痛の軽減が認められたものの,明け方ころには,再び右下股痛が増強し,痛み止めを希望したため,再度鎮痛剤及び鎮静剤が静脈注射された。同日に行われた血液検査結果によれば,赤血球数384万,ヘモグロビン12.0,ヘモグロビンの割合75%,ヘマトクリット値36.3%であった。患者は,同月16日も,右大腿部痛を継続して訴え,鎮痛剤が繰り返し投与されたり,局所麻酔剤による疼痛コントロールが行われるなどした。同日,患者を診察したA医師は,こむらがえりは起きていないと診断した。
患者の右大腿部痛は同月17日には落ち着き,その後,間欠的に疼痛の増強を訴え,坐薬等の鎮痛処置がとられることはあったが,全体的には,軽減傾向にあり,患者自身も同様の認識を述べていた。同月27日,休暇中のA医師に代わり,被告病院整形外科のD医師が患者の夫に依頼されて患者を診察し,血腫があるため痛みが持続しているのではないかと考え,患者らに対し,右鼠径部大腿動脈部分の腫瘤が小さくなるにつれて突っ張る感じや痛みは軽快するだろうと説明した。患者は,11月1日,被告病院を退院した。
患者が,同月17日,A医師が作成した診療情報提供書を持参して甲病院整形外科を受診したところ,患者の状態は,右鼠径部に注射痕を中心に直径8cmの硬結があり,下腿以下への放散痛が認められず,下股全体がしびれ,膝の伸展ができず,膝蓋腱反射も認められないというものであった。同月21日,筋電図検査の結果を踏まえ,患者は,大腿神経障害と診断され,12月1日,甲病院に入院して,同月3日に右大腿血腫除去術を受けることとなった。11月29日,患者は被告病院を受診し,A医師に,右大腿部穿刺部痛が持続しており,筋肉痛も時々あると訴えたが,A医師は患者の右大腿部を視診ないし触診しなかった。患者は,12月1日,甲病院整形外科に入院し,同病院の医師から,右鼠径部に腫瘤が認められ,硬く緊満しているが,拍動は認められないと診断された。同月3日午後1時51分ころから,血腫除去術が開始されたところ,術中,血腫と思われたものが,実は拍動を伴う仮性動脈瘤であることが判明し,心臓血管外科医へのコンサルトを要するため手術が中止され,止血,閉創の上,同日午後5時30分ころ,患者は乙病院へ転送された。
乙病院の医師は,右鼠径部から大腿中枢側に20X15㎜大の非拍動性腫瘤を触知し,その内側に大腿動脈の拍動を触知したことから,大腿分岐外側に入り口を有する仮性動脈瘤であると診断し,同日午後8時5分ころから,仮性動脈瘤の修復術が実施された。患者は,同月9日に再び甲病院に転院し,同病院においてリハビリを中心とする治療を受け,同月26日,同病院を退院したが,大腿神経麻痺の症状が残り,右下肢の筋力を要する就労は不可能と診断された。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計5324万1177円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①塞栓術後の止血時における過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
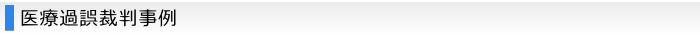
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
小脳出血に対する後頭蓋窩減圧術,硬膜形成術及び術後管理と死亡との間の因果関係が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第4588号 損害賠償請求事件
平成16年5月13日判決 確定
【手技,入院管理,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和3年生,男性)は,平成11年4月3日,小脳出血に対する緊急手術として,被告病院において,血腫(5X4.5X2㎝)を除去する開頭手術を受けることになった。担当医師は,開頭後,小脳の腫脹は認めたが軽度であったため,血腫除去は不要と判断し,後頭蓋窩減圧術(後頭骨を切開し後頭下の減圧を行う手術)及び硬膜形成術を行った。術後,患者の気管内チューブを抜去したところ,気道閉塞が生じたため,緊急気道切開術が行われた。
その後,患者は,被告病院において,術後管理を受けていたが,同月15日から後頭部手術創から髄液漏れが起き,同月19日に髄膜炎と診断され,同年5月5日,中脳脳幹部梗塞を合併した。同月20日,突然,房室ブロックが起き,心室細動,呼吸停止,低酸素脳症を生じ,患者は21日に死亡した。
患者の遺族が,被告病院を開設する法人に対して,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2750万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者の死亡原因 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
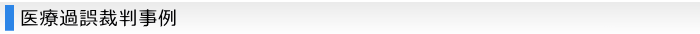
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
くも膜下出血を発症した脳動脈瘤患者に対する開頭クリッピング手術後,脳血管造影検査を行った際,患者に麻痺を生じたことについて,検査の必要性が認められ,検査の手技上の過失も,説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第3351号 損害賠償請求事件
平成16年6月30日判決 控訴 判タ1212号226頁
【説明・問診義務,手技,適応】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は,平成8年10月9日,激しい頭痛があり,様子を見ていたが,同月17日,頭痛を訴えて甲病院を受診した。検査の結果,2つの脳動脈瘤が発見され,そのうち1つが破裂してくも膜下出血を発症していると診断され患者は,被告病院に搬送された。被告病院での検査の結果,前交通動脈に1か所,脳底動脈と上小脳動脈の分岐部に1か所の合計2か所の動脈瘤があり,このうち前交通動脈脳動脈瘤が破裂した可能性が高いと考えられ,開頭クリッピング手術が予定された。担当医であるA,B及びC医師は,いずれも被告病院の脳神経外科医で,A医師は約10年,B医師は約6年の医師経験を有し,C医師は研修医であった。同医師らにより同月29日,開頭クリッピング手術が実施されたが,難易度の高い脳動脈瘤のクリッピングは成功したものの,術後患者に右上下肢の麻痺が生じた。
被告病院では,開頭クリッピング手術後,必ず脳血管造影検査を実施することにしていたところ,_患者に生じた麻痺の原因をさぐる必要性もあったことから,同年11月21日,B医師及びC医師によって,患者に対し脳血管造影検査が実施された。検査では,まず左総頸動脈,右総頸動脈の撮影が行われ,引き続き右椎骨動脈の撮影を行おうとしたが,なかなかカテーテルが入らず,患者から右上肢の動きが悪い,力が入らないとの訴えがあった。B医師らは血流改善作用のあるグリセオールを投与したが,患者の症状が改善しないためいったん検査を中断した。B医師は,患者の右上肢に麻痺が現れたことから,左総頸動脈領域に血栓が飛んだ可能性が高いと考え,血栓溶解作用のあるウロキナーゼを投与しつつ,原因検索のために左総頸動脈の撮影を再度実施したが異常は発見できなかった。その後,頭部CTにより,患者の左頭頂部及び左被殻から左放射冠にかけて脳梗塞が認められ,これが麻痺の原因であると考えられた。
患者は,リハビリを行ったが,麻痺が残存した(麻痺の程度については当事者に争いがある)。
患者が,被告病院を開設している法人に対して,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6765万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①脳血管造影検査の必要性 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
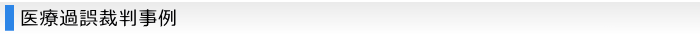
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,微小血管減圧術を受けた後,脳幹梗塞等を原因として死亡したことについて,手術の危険性等についての説明義務違反,手技を誤った過失等がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第6931号 損害賠償請求事件
平成17年5月27日判決 確定
【説明,問診義務,手技,適応,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,男性)は,平成12年5月11日,左顔面けいれんを訴え被告病院(公立病院)を受診し,A医師(脳神経外科)から,微小血管減圧術の説明を受け,8月30日に入院した。被告病院入院後,A医師及びB医師(脳神経外科)は,患者に対し,頭部MRI等の術前検査及び術前説明を実施し,9月8日,手術を実施した。
翌9日午前8時20分,患者に突然意識レベル低下が生じたため,A医師は,午前9時46分ころ,頭部CT最影を実施し,脳幹梗塞が疑われたため,患者に対し,低分子デキストラン投与による保存的治療を行った。同月10日午前9時40分ころ頭部CT検査を実施したところ,脳幹梗塞の拡大が認められたため,A医師は,患者に対し,呼吸器の合併症の危険性を減少させるため,気管切開を実施した。
患者は,同月11日,家族の希望で甲病院(総合病院)に転院し,脳幹梗塞等に対する保存的治療を受けていたが,同月13日死亡した。
患者の家族(妻及び子ら)が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①微小血管減圧術の手術適応の有無
②手術の危険性や合併症の有無等について説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
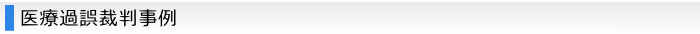
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
左篩骨洞から左眼窩内壁にかけての占拠性病変(粘膜嚢腫)を摘出するための開頭手術後,患者の両限に視力障害が現れたことについて,担当医師らの過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17326号 損害賠償請求事件
平成17年7月28日判決 控訴
【手技】
<事案の概要>
患者(昭和26年生,男性)は,平成11年9月ころから,左眼に痛みや見えにくさ覚え,9月24日から10月15日まで,4回にわたって被告病院(大学病院)眼科を受診した。各種検査が実施されたが原因は判明しなかった。患者は,平成12年5月ころ,左眼に曇りを感じたため,5月2日,被告病院限科を再受診し,頭部CT検査を受けたところ,患者の頭部CT画像を読影したA医師(脳神経外科)により,患者の左篩骨洞から左眼窩内壁にかけて占拠性病変があり,これが視神経を圧迫していると診断された。
患者は,5月8日,被告病院脳神経外科に入院し,5月17日に占拠性病変を摘出するための開頭手術を受けた。手術では,仰臥位で下顎部が水平より低くなるように頭部を三点で固定された患者の前頭部の頭皮に,左側頭部から右側頭部にかけて冠状切開が入れられ,切開部から眼窩上縁まで頭皮が剥離され,眼窩上縁で薄いガーゼを挟み込むように折り曲げられ,釣針様の器具によって顔上に向けて翻転された。釣針様の器具は,弾力性のあるゴムによって,術野周囲を覆う清潔覆布に固定され,これにより,患者の頭皮弁は,翻転された状態で維持された。患者の頭皮の下に現れた前頭骨の骨欠損部位を取り囲むように開頭を施したところ,占拠性病変によって左眼窩上壁の一部が欠損していることが認められ,左眼窩上壁を剥離摘除し,ナビゲータ(手術用顕微鏡)を用いながら,占拠性病変が摘出された。その後,人工骨によって前頭骨の骨欠損部位の形成が行われ,手術は終了した。
患者は,術前である5月12日時点では矯正視力が右眼1.5,左眼1.2で,眼底所見は,黄斑部,視神経乳頭ともに正常と診断されていたが,手術翌日の5月18日には,右眼の視力は光覚弁(瞳孔に光を入れた場合に明暗が弁別できる程度の視力)すら測定できず,左眼は眼前30cmの距離にある手の動きを弁別できる程度の視力で,両眼について眼球運動障害が認められる状態であった。その後,若干の改善はみられたが,重篤な後遺障害が残った。
患者は,6月12日に糖尿病との診断を受けた。
患者は,本件手術後に両眼に後遺障害が現れたことについて,担当医師らが手術時に翻転した頭皮弁で両眼球を圧迫したことに原因があるなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億2784万6477円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 担当医師らが,手術の際,翻転した頭皮弁で両眼球を圧迫しないように注意すべきであったにもかかわらず,これを怠ったため,患者に視力障害が生じたか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
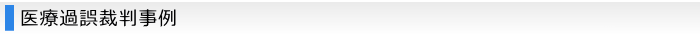
脳神経外科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
右内頸動脈-後交通動脈分岐部に生じた未破裂脳動脈瘤治療のための脳動脈瘤塞栓術の後,患者に左上下肢の機能障害及び知的機能障害が現れたことについて,担当医師らの過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第26967号 損害賠償請求事件
平成17年8月29日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,検査】
<事案の概要>
患者(大正12年生,女性)は,平成12年12月初旬ころから右眼の瞼が下がって見えにくくなったため平成13年1月31日,被告病院(大学病院)脳神経外科を受診した。頭部MRl検査の結果,右内頸動脈-後交通動脈分岐部に脳動脈瘤が指摘され,患者は担当医師より直ちに入院して手術を受ける必要がある旨を告げられた。
患者は,被告病院に入院し,2月1日午後1時30分ころに血管撮影室に入室し,午後1時45分ころから脳血管撮影検査を受けた。脳血管撮影検査では,右鼠径部からカテーテルが挿入され,午後2時14分ころ右内頸動脈の正側像が,午後2時19分ころ右内頸動脈の斜位像が,午後2時32分ころに右椎骨動脈が,午後2時52分ころ左内頸動脈がそれぞれ撮影された。患者は,2月1日午後5時30分ころ,血管撮影室に再入室し,脳動脈瘤塞栓術(コイル塞栓術)を受けた。手術では,午後6時05分ころから午後6時15分ころにかけて,右大腿動脈に挿入されたシースを通じてガイディングカテーテルが右内頸動脈へと誘導され,午後7時00分ころ,ガイディングカテーテルを通じてマイクロカテーテルが脳動脈瘤内に誘導され,午後7時03分ころと午後7時09分ころ,マイクロカテーテルを通じて脳動脈瘤内にコイルが挿入され,2本のコイルによって脳動脈瘤内にフレームが形成され,午後7時20分ころから,へパリン(抗凝固剤)3000単位の静脈注射が開始された。午後7時30分ころ,午後7時40分ころ,午後7時43分ころ,順次コイルが本件脳動脈瘤内に挿入され,午後7時43分ころに挿入されたコイルが留置されるのと同時にマイクロカテーテルが脳動脈瘤から押し出されてきたため,A医師,B医師らは,午後8時00分ころ,マイクロカテーテル及びガイディングカテーテルを抜去して手術を終了した。なお,手術中,随時,脳血管撮影検査が実施されていた。
同日午後8時30分ころ,患者の左上下肢の動きが悪いため,午後8時46分ころ頭部CT検査が,午後8時59分ころ,脳血管撮影検査がそれぞれ実施され,検査の結果,患者の右中大脳動脈の運動野に向かう末梢動脈の描出が悪いことが確認され,動脈瘤内に形成された血栓が飛んだ可能性が考えられた。そのため,患者に対し,午後9時25分ころ及び午後9時40分ころ,ウロキナーゼ(血栓溶解剤)が12万単位ずつ静脈注射され,その結果,患者の右中大脳動脈の運動野に向かう末梢動脈の一部に血流の再開が認められた。2月2日午後2時53分ころ,頭部MRI検査が実施され患者の左前頭葉の一部(左下前頭回)に脳梗塞の発症を示す所見が認められた。
患者は,6月5日に身体障害者手帳(左上肢機能障害〔2級〕,左下肢機能障害〔4級〕)の交付を受け,6月23日に被告病院を退院した。その後,患者は,平成14年1月4日,本件脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症し,甲病院(総合病院)医療センターに入院して,脳動脈瘤塞栓術による治療を受けた。
患者は,担当医師らに手技上の過失や説明義務違反があったなどと主張して,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億1857万3503円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①手術の際,担当医師らが全身へパリン化を怠ったために,患者は右脳梗塞を発症し,左上下肢の機能障害を生じたか否か。 ②手術の際,担当医師らが,右脳動脈の閉塞に対して直ちにウロキナーゼを投与する措置を怠ったために,患者は右脳梗塞を発症し,左上下肢の機能障害を生じたか否か。 ③患者の左脳動脈に対する脳血管撮影検査が,患者に左脳梗塞を発症させ,知的機能障害を生じたか否か。 ④左脳に対する脳血管撮影検査の際,担当医師らが,患者に生じた左脳動脈の閉塞に対し直ちにウロキナーゼを投与する措置を怠ったために,患者に左脳梗塞を発症させ,知的機能障害を生じたか否か。 ⑤担当医師らが,本件脳動脈瘤を完全に塞栓することを怠ったために,患者にくも膜下出血が起こり,後遺障害を生じたか否か ⑥説明義務違反の有無 | ||||
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




