光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
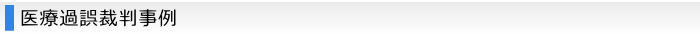
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,急性喉頭蓋炎で死亡したことについて,担当医師に,患者に対する監視措置の過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第5893号 損害賠償請求事件
平成17年10月24日判決 控訴
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,男性)は,喉の痛みを訴えて,平成15年9月16日,近医を受診し,抗生物質等を投与されたが,症状が改善しなかったため,同日午後7時24分ころ,被告病院(公立病院)の救急外来を受診した。同病院の当直医であったA医師(耳鼻咽喉科)が患者を診察し,喉頭ファイパースコープによる検査を実施したところ,喉頭蓋に浮腫状の腫脹が認められた(披裂部の腫脹はなく,気道は3分の1程度狭窄していた。)ため,急性喉頭蓋炎と診断し,緊急入院を指示した。A医師は,患者に,ステロイド剤及び抗生物質を点滴投与し,看護師に対し,患者に酸素飽和度モニターを装着すること,ギャッチアップ30度の姿勢で安静とすること等を指示し,指示箋に,酸素飽和度が85%未満になったら,酸素投与を開始し,ドクターコールをするとの指示事項を記載した。午後8時30分ころ,患者は処置室から病室に移動し,点滴投与が開始された。患者は,午後9時ころ,入院時に37.6度であった体温が39.3度に上昇し,午後9時30分ころには咽頭の痛みを訴え,左側頸部に腫脹が認められたが,看護師は,酸素飽和度の数値を確認したのみで,体温や血圧・脈拍の計測をせず,A医師に患者の状況を報告しなかった。午後10時10分ころ,看護師が訪室した時には,点滴は終了し,患者は左側臥位の姿勢で眠っており,吸気性喘鳴はなかった。患者の酸素飽和度は,90%台の後半で安定していた。午後10時30分ころ,患者からナースコールがあり,看護師が訪室したところ,患者は,ベッドに座って唾液や痰を出そうとしており,吐きながら苦しそうに呼吸しており,酸素飽和度は,92%であった。看護師は,痰を喀出しやすいよう患者の背中をタッピングしながら,応援の看護師を呼ぶためナースコールをした後,廊下にいた看護師に酸素投与と吸引の準備を依頼した。患者の酸素飽和度は,その間に,87%に低下し,応援の看護師が到着したときには,65%から57%に急激に低下したため,看護師はA医師の来室を要請したが,午後10時35分ころ,A医師が病室に到着した時には,患者の意識は既に消失し,体動が全くない状態で,酸素飽和度モニターの数値は読み取れない状況であった。A医師は,気管内挿管を実施するため,喉頭鏡で喉頭蓋を観察しながら気管内挿管を試みたが,喉頭蓋が高度に腫脹して挿管困難であったため,A医師は,挿管を断念し,気道を確保するためトラへルパーを挿入しようとしたが,これも失敗した。そこで,患者の気管に18ゲージ注射針を穿刺し,緊急に気道を確保した上,新たなトラヘルパーを挿入し,頸部外切開による緊急気管切開術を施行し,切開部に小児用気管チューブを挿入し,アンビューバッグによる酸素投与・換気を開始した。患者の自発呼吸は再開せず,脈拍も触知不能であったため,心臓マッサージが施行され,看護師に昇圧剤の静脈注射が指示された。午後10時50分,緊急気管切開術施行の事態に備えて自宅待機していたB医師(耳鼻咽喉科)及び当直医であったC医師(内科)が病室に到着し,この時点で心電図モニター上,心拍波形は徐脈を示していたが,B医師が右橈骨動脈と右鼠径部で脈拍を確認すると,微弱な脈拍を触知することができた。午後11時ころ,患者に対し,人工呼吸器が装着され,心臓マッサージ,昇圧剤の静脈注射,強心剤の投与等がされたが,患者の意識は回復せず,午後11時30分ころ,心停止に至り,患者は,9月17日午前1時33分に死亡した。
患者の家族(妻及び子2名)が,被告病院を開設する地方公共団体及びA医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億4027万7859円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額合計8154万4787円) | ||||
| 争 点 | ①A医師に,患者を常時医師及び看護師の十分な監視下に置き,不測の事態を回避すべき義務違反があったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 4701万4787円 | |||
| ②死亡慰謝料 | 1500万0000円 | ||||
| ③治療関係費 | 3万0000円 | ||||
| ④葬儀費用 | 150万0000円 | ||||
| ⑤患者の家族固有の慰謝料 | 各500万0000円 | ||||
| ⑥弁護士費用 | 300万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
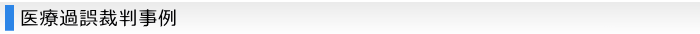
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
扁桃摘出術,アデノイド切除術後,呼吸停止し低酸素脳症に陥った患者について,担当医師らに,高次医療機関への転送義務違反が認められたたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第2092号 損害賠償請求事件
平成17年2月17日判決 控訴
【入院管理,治療方法・時期,転医義務,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(平成4年生,女性)は,ダウン症と診断され,甲クリニックのA医師から育児指導を受けていた。患者の両親が,A医師に,患者がいびきをかくことや言葉が遅れていることなどを相談したところ,被告診療所のB医師を紹介された。患者は,平成9年10月14日,被告診療所において,B医師(被告診療所院長)執刀,C医師(乙病院〔大学病院〕麻酔科)麻酔担当による扁桃摘出術,アデノイド切除術等を受けた。手術は,同日午前9時55分ころC医師が麻酔を開始した上で,同日午前10時05分ころ開始され,午前10時36分ころ終了し,午前10時45分ころ,気管内チューブが抜去された。術後,患者は,病室に戻され,D看護助手が患者の経過観察を担当した。D看護助手は患者の口腔内出血を発見し,圧迫止血しようとしたが,患者が嫌がって動き,圧迫止血できなかった。その後,何らかの原因で,患者が呼吸停止に至り,病室で付き添っていた患者の母が患者を抱き上げた。D看護助手は,一度手術室に患者の呼吸停止を告げに行った後,手術室に患者を運び,C医師に引き継いだ。患者は,手術室に運ばれた時点で,全身にチアノーゼが見られ,C医師は,患者の呼吸状態を確認した上で気管内挿管を実施し,パルスオキシメーターを装着したが,脈が微弱だったため心臓マッサージを数回実施したとごろ,患者の自発呼吸が回復した。心肺蘇生の際,C医師は,アシドーシスの補正等のために,メイロン,ラクテック,プレドニンを点滴投与した。患者が手術室に運ばれてから自発呼吸を回復するまでの時間は2分程度であった。パルスオキシメーターを装着した時点の動脈血酸素飽和度(Sa02)は70%台で自発呼吸回復後,酸素投与をした段階では,100%近くまで回復し,全身のチアノーゼも改善されていた。患者の意識は回復しないままであったが,時折体動が見られ,同日午後2時30分ころには,激しい体動が見られ,C医師は抜管し,B医師が気道確保のためエアウェイを入れた。C医師は,患者の意識が戻らず,出血も続くため,出血点確認のために,同日午後8時35分,麻酔導入をし,B医師の執刀で,出血点の確認と出血しそうな部位の結紮を行い,同日午後9時55分,麻酔を終了したが,実際には出血はなかった。同日の夜から翌朝まで,准看譜師が患者の母と一緒に,患者に付き添ったが,患者は自発呼吸は見られたが意識が回復せず,翌15日朝,C医師が被告診療所に行った際も,患者の意識が戻っていなかったため,集中管理が必要であると判断し,午前10時ころに乙病院に転送した。
患者は,乙病院で低酸素脳症と診断された。乙病院入院後2週間の時点で,患者の意識レベルは,GCS(Glasgow Coma Scale)でE4(自発的に開眼する),V2(理解不明な音声),M3(異常屈曲)で固定し,症状も固定して中心静脈栄養から経管栄養へ移行したことから,平成10年2月9日,リハビリテーション目的で,丙病院へ転院となり,同年5月8日まで入院した。患者は,丙病院入院時点で,頸定なく,自力移動や座位の保持ができず,痙直型四肢麻痺の状態であった。
患者及び患者の両親が,B医師及び被告診療所を経営する法人(代表者B医師)に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億4958万8130円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額合計5518万1167円) | ||||
| 争 点 | ①患者の低酸素脳症の原因 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 598万7372円 | |||
| ②介護費用 | 2919万3795円 | ||||
| ③患者の慰謝料 | 1500万0000円 | ||||
| ④弁護士費用 | 500万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
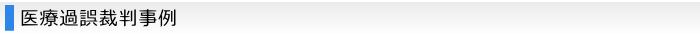
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
慢性中耳炎による鼓膜穿孔に対する鼓膜形成術において,味覚障害の発生の可能性及び有意な聴力回復の可能性が低いことについて,説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第9527号 損害賠償請求事件
平成16年11月11日判決 確定
【説明・問診義務,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(手術時55歳,女性)は,小学生のころ,右中耳炎に罹患して右鼓膜穿孔を生じ,右耳が難聴となっていたが,耳漏はなかった。平成12年5月2日,患者は,被告病院において,声帯嚢胞に対する咽頭微細手術を受けることになったが,被告病院のA医師の勧めで,B医師による右鼓膜穿孔に対する鼓膜形成術も受けた。なお,術中,手術器具が右鼓索神経に触れた。被告病院における,聴力検査で,患者は感音性難聴に近い混合性難聴と判断されており,鼓膜形成術によって有意な聴力改善は認めにくい状況であった。患者の聴力は,鼓膜形成術後も改善せず,平成12年7月24日以降,甘くないものも甘く感じるなどの味覚障害を訴えるようになった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1929万6687円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額766万1480円) | ||||
| 争 点 | ①鼓膜形成術において味覚障害が発生する可能性は,説明義務の対象となるか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費 | 6万9743円 | |||
| ②傷害慰謝料 | 120万0000円 | ||||
| ③逸失利益 | 389万1737円 | ||||
| ④後遺障害慰謝料 | 180万0000円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 70万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
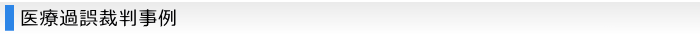
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
アレルギー性鼻炎に対するレーザ一手術について,医師にレーザーを過剰照射した過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第12910号 損害賠償請求事件
平成16年2月18日判決
【説明義務,問診義務,手技,適応,治療方法,時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和20年生,女性)は,花粉が飛散する時期にくしゃみ,鼻汁,鼻閉などのアレルギー性鼻炎症状がでるため,平成9年4月,アレルギー性鼻炎に対するレーザー手術を行っていた被告病院(国立病院)の耳鼻咽喉科を受診し,A医師の診察を受けた。A医師は,患者に対して症状の問診,鼻内所見の視診,アレルゲン検査のための採血などを行った。
平成9年10月,患者は,被告病院のレーザー外来にて,B医師の診察を受けた。
B医師は,アレルゲン検査の結果,患者がスギ花粉やヨモギ花粉に強い陽性反応を示し,ハウスダストやダニなど通年性の抗原にも若干反応があり,患者が鼻閉で点鼻薬を使用することがあると述べていたことなどから,KTPレーザーを用いたレーザー手術の適応があると考えた。
アレルギー性鼻炎に対するレーザー手術には,アレルギー反応を起こす粘膜にレーザーを非接触的に照射して粘膜を蒸散させその変性と減量を行う蒸散法と,レーザーを接触的に照射して粘膜を切除し,その変性や減量とともに鼻腔の開大を図る切除法があり,被告病院では主に切除法を実施していた。
平成10年6月,患者は,A医師の執刀で,両鼻腔に対しレーザー手術(KTPレーザーにより下鼻甲介粘膜総鼻道側を切除する手術)を受けた。術後,A医師は,患者に止血剤や抗生物質を処方し,2か月後に術後状況の確認のため来院するよう指示するとともに,気になる症状があれば一般外来を受診すること,出血が止まらないなどの異常があれば直ちに来院することを告げた。
患者は,術後,鼻内からの出血や排膿が続き,他の医療機関を受診していたが,同年9月ころには排膿や出血はなくなり,粘膜切除部位の痂皮もとれ上皮化が完了した。この時点で,原告の右下鼻甲介は,前方から約3分の2が欠損した状態になっており,欠損部分に対応して,右下鼻甲介骨も欠損していた。
患者は,右下鼻甲介に欠損が生じた後,鼻や喉の乾燥感,膿性鼻汁,後鼻漏,喉への痰の張り付き,喉の痛みなどの症状を訴えるようになった。
患者が,被告病院を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1396万7742円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額116万9590円) | ||||
| 争 点 | ①患者のアレルギー性鼻炎に対し,切除法によるレーザ一手術の適応があったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費・通院交通費 | 6万9590円 | |||
| ②慰謝料 | 100万0000円 | ||||
| ③弁護士費用 | 10万0000円 | ||||
| 判 断 | ①適応あり | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
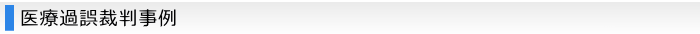
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
甲状腺癌摘出手術について,その必要性及び危険性に関し,説明義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第5782号 損害賠償請求事件
平成16年1月26日判決
【説明義務,問診義務,手技,検査,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和19年生,女性)は,平成11年11月,甲病院(大学病院)において甲状腺癌摘出手術(前回手術)を受けたが,頸部左側リンパ節の郭清は行われなかった。患者は,平成12年2月,下頸部中央に腫瘤が発見され,不安を感じており,前回手術創のケロイドを気にしていたため,手術がうまいと聞いていた被告病院(甲状腺の専門病院)を,平成12年11月7日,受診した。
同月20日,エコー下での左鎖骨状のリンパ節及び右総頸動脈背側リンパ節から穿刺吸引細胞診が行われ,その結果,本件左側リンパ節から癌細胞が発見され,甲状腺乳頭癌の転移であると診断されたが,本件右側腫瘤からは癌細胞は認められず、癌と診断するには不十分であるとされた。
患者は,手術を受けることとし,平成13年3月7日,被告病院に入院し,同月9日A医師の執刀により甲状腺癌摘出手術(本件手術)が実施された。午後2時45分,A医師は,鎖骨上2横指頭側(前回手術の手術創と同位置)に襟状切開を置き,皮下を剥離した後,癒着の強度を確認し,本件右側腫瘤の摘出を行うかどうかを判断するべく,同腫瘤を検索するため,右頸動脈の拍動を確認した後,ケリー鉗子を使用し,本件右側腫瘤の1.5〜2cm頭側から,鉗子の彎曲部分を下に向けて入れて開き,上から下へ向かつて繊維性癒着と頸動脈の剥離操作を開始した。本件右側腫瘤に至る以前の剥離操作開始後5分後から10分後(午後2時55分ころ),右総頸動脈の右鎖骨下動脈との分岐部の損傷(本件頸動脈損傷)が確認された。損傷部位を縫合したが,癒着がひどく,動脈硬化が強かったため,クランプするのに手間取り,出血が多かった。A医師は,本件右側腫瘤の摘出を断念し,全身状態が落ち着いたところで,左頸部の郭清を行い,午後5時7分,本件手術を終了した。
本件手術後,患者に,左半身の動作が見られない状況が続き頭部MRIによって右大脳に多発性の梗塞を認めた。
患者は,同月19日,被告病院を退院し,丙病院に入院し,その後,丁病院に転院したが,同年10月28日,丁病院を退院し,現在は自宅で介護を受けている。
患者は,同年7月19日,脳梗塞による体幹機能障害及び左上肢機能障害により,身体障害程度等級1級の認定を受けた。
患者及びその家族(夫及び子2人)は,被告病院を開設するB医師及び担当医師であったA医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億0654万6681円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額合計170万円) | ||||
| 争 点 | ①本件手術前に説明を怠った注意義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①患者本人の慰謝料 | 150万円 | |||
| ②弁護士費用 | 20万円 | ||||
| 判 断 | 頸動脈損傷の原因 | 頸動脈損傷が癒着剥離操作中に発生したことから,癒着剥離操作が原因となったことは推認されるが,頸動脈損傷からの出血の態様から,A医師の癒着剥離操作が,直接頸動脈損傷部位に及んだとは認めがたく,他の可能性も推論の域を出ず、剥離操作から頸動脈損傷が発生した具体的な機序は明らかでない。 ①右側腫瘤は癌の確定診断が得られおらず手術の必要性が低い一方,右総頸動脈背面に接して存在することが判明しており,再手術で癒着が生じていることが予測され,左側リンパ節の郭清より難度・危険性が高いことが予測された。頸動脈損傷発生の具体的機序が明らかでなく,A医師がその具体的危険性を説明することは不可能であるが,患者が手術を受けるかどうか判断する要素となる本件手術の必要性,特に右側腫瘤摘出の必要性とともに、それに伴う危険性についても十分説明すべき義務があったにもかかわらずこれを怠った。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
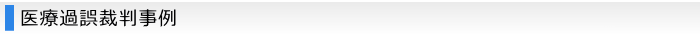
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
急性喉頭蓋炎の患者に対する経過観察を怠った過失,及び,気道確保の手技を誤った過失がいずれも認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第6038号 損害賠償請求事件
平成16年1月21日判決
【手技,入院管理,治療方法,時期,術後管理,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和42年生,男性)は,平成11年8月13日午後6時30分ころ,身体の震え,咽頭部痛等を訴えて,被告甲病院(胃腸肛門科病院)を受診した。同病院の医師は,感冒,咽頭炎,扁桃炎と診断し,患者に抗生物質等を投与した。患者は,いったん帰宅したが,呼吸困難を覚えて,同日午後9時20分ころ,再度被告甲病院を受診した。当直医であったA医師(消化器外科)が診察したところ,38度の発熱と中等度の呼吸困難があり,扁桃に軽度の腫脹を認めたが,パイタルサイン,肺の聴診音,呼吸音が正常だったため,両側の扁桃腺腫大による呼吸困難と診断し,ステロイド剤を点滴した上,経過観察をするために患者を入院させた。
患者には,入院直後から,ヒューヒューという狭窄様の呼吸音を伴う強い呼吸困難と咽頭痛が認められ,翌14日午前0時ころ,午前1時45分ころ,午前2時30分ころ,午前6時ころ,ナースコールで看護師を呼んで呼吸困難を訴えた。看護師がA医師に患者の状況を報告したが,A医師は,診察せず,看護師にステロイド剤やボルタレン坐薬の投与を指示した。患者は,すぐに呼吸困難の状態に戻り,息苦しさの余り,飛び起きたりしていた。
午前7時,呼吸状態に変化はなく,午前8時30分,患者が呼吸困難を訴えてナースコールで看護師を呼んだ。患者は,痰を飲み込めず,軽度のチアノーゼが認められた。被告甲病院の医師が,患者を診察し,扁桃炎,上気道閉塞と診断し,上気道閉塞の解除と扁桃炎の根治のため,被告乙病院(大学病院)に連絡をして,患者の受入れを求め,了承を得た。
午前8時50分ころ,救急車が到着して,被告甲病院の医師が同乗して患者は搬送され,午前9時20分ころ,被告乙病院へ到着した。救急車内で患者は,頻脈が認められたが,酸素マスクによる酸素投与で意識状態は清明で意思疎通も可能だった。
患者は,直ちに救急処置室に搬入され,B医師(救急外来の当直医)が診察したところ,かなりの呼吸困難(起座呼吸)があり,聴診で気道の狭窄音を聴取したが,酸素飽和度は,98-100%で安定していた。B医師は,患者は一刻を争って直ちに緊急気道確保をしなければならないような差し迫った状態ではないと判断し,胸部・腹部単純レントゲン撮影を指示した。
午前9時40分ころ,C医師(耳鼻咽喉科)は,B医師から,患者について,上気道の閉塞が疑われると説明されたことから,患者の口腔内を額帯鏡で診察したが,扁桃には異常がなかったため,喉頭病変を疑い,午前9時45分ころ,喉頭ファイパーで喉頭を観察したところ,喉頭蓋の著明な発赤と腫脹があり,声帯が確認できないほど声門を閉塞していたので,急性喉頭蓋炎と診断した。
C医師は,午前9時55分ころ,喉頭蓋の炎症を軽減させるため,ステロイド剤の点滴内投与及び声門下や下気道の状況を調べるために頸部レントゲン撮影の指示をした。C医師は,気道確保の必要性があると判断したが,患者の状態から,経口挿管は困難と考え,ミニトラックセルジンガーキットを用いた気道確保(ミニトラックによる気道確保)を選択した。
患者に対し,午前10時6分ころから午前10時13分ころにかけて,胸部・腹部単純レントゲン撮影及び頸部正面・側面レントゲン撮影が実施され,頸部側面レントゲン写真では,喉頭蓋の著明な腫脹と声門上部完全閉塞が認められた。
午前10時15分ころ,C医師は,B医師の介助で,患者に対し,気道確保を行う説明をした後,ミニトラックによる緊急気道確保を開始した。半座位にある患者の頸部を局所麻酔をして,スカルペルで,輪状軟骨の下方の皮膚に約2,3cm横切開を入れ,患者が半座位で皮膚によって視野が取れなかったので,C医師は,皮膚の上方と下方をモスキート鉗子でつまみ,これをB医師が上下に引っ張った上で,筋肉を剥離して,視野を確保し,気管前壁を指先で確認した。ガイドワイヤーが喉頭へ向かないよう,皮膚切開部分からやや斜め下方に向けて,穿刺針で第2・3気管輪間の輪状靭帯を穿刺し,気管内へ穿刺されていることを確認した。ガイドワイヤーに沿って,ダイレーターを気管内へ挿入して,穿刺孔を拡大し,ダイレーターだけを抜き取り,カニューレをガイドワイヤーに沿わせながら,気管内へ挿入しようとした時,患者が突然暴れ出し,自身でガイドワイヤーを抜去した。
ミニトラック穿刺箇所から,出血が始まり,押さえないとあふれるほどの激しい出血があったため,c医師は,穿刺部位の視野を確保できず,出血している皮膚切開部をガーゼで押さえながら,カニューレの再挿入を試みたが,ダイレーターで広げた穿刺孔がすぼみ,出血で視認できず,カニューレを再挿入できなかった。他の医師が,気管内挿管を実施することにしたが,声門はおろか喉頭蓋も十分観察することができなかったため,盲目的気管内挿管を試みたが,患者の激しい体動で挿管できなかった。気道確保のため,18ゲージの注射針5本を穿刺し,そこから酸素を流し入れる処置を行いながら,引き続き盲目的気管内挿管を試みたが,挿管操作中に,患者は呼吸停止及び心停止となり,蘇生薬の点滴投与や心マッサージをしながら,盲目的気管内挿管を試みた結果,午前10時35分,気管内挿管が成功し患者の心拍動が再開し,心肺とも蘇生した。午前10時45分ころ,B医師及びC医師は第2〜第4気管軟骨間に気管切開術を行った。
患者は,心肺・呼吸停止により,低酸素脳症となり,植物状態で症状固定となった。
患者及びその両親が,被告甲病院を開設する同病院の院長及び被告乙病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 一時金1億6970万6237円,定期金1か月88万5000円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額一時金1億4981万8175円,定期金1か月30万円) | ||||
| 争 点 | ①A医師は,8月13日午後9時20分ころの外来受診時に急性喉頭蓋炎と診断し,耳鼻咽喉科専門医のいる病院へ転送すべきだったか。 | ||||
| 認容額の内訳 | ①治療費 | 80万9900円 | |||
| ②入院看護費及び雑費 | 766万2950円 | ||||
| ③自宅介護費及び雑費 | 868万0000円 | ||||
| ④自宅改装費 | 645万8980円 | ||||
| ⑤交通費等 | 157万8970円 | ||||
| ⑥文書料 | 2万8035円 | ||||
| ⑦逸失利益 | 8659万9340円 | ||||
| ⑧慰謝料 | 3000万0000円 | ||||
| ⑨弁護士費用 | 800万0000円 | ||||
| ⑩定期金賠償(自宅介護費) | 1か月30万円 | ||||
| 判 断 | ①この段階で,転送すべき緊急性があったとまでいえない。 ②14日午前6時の時点で被告乙病院へ等搬送すべき義務があったにもかかわらずこれを怠った過失がある。 ③検査の必要性と患者の状態から,B医師及びC医師が,レントゲン検査後に気道確保を試みたことは医師の裁量の範囲内。 ④鎮静剤・筋弛緩剤は呼吸抑制が強く,使用しなかったことは適切。 ⑤C医師は,緊急気道確保のため,ミニトラックを輪状甲状間膜に穿刺すべき注意義務があるのに、特段の合理的理由がないにもかかわらず第2・3気管輪間へ穿刺し,しかも,その手技は不適切であるから過失がある。 ⑥C医師の過失がなければ,ミニトラック穿刺による孔を確認できないような出血が生じることはなく,その結果,早期にミニトラックによる気道確保を行うことができ,心肺停止に至らなかったか,心肺停止になったとしても,より早期に心肺を蘇生することができ,低酸素脳症が生じることはなかったといえる。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
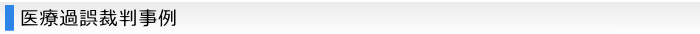
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
扁桃摘出手術の6日後に手術部位からの出血で死亡したことについて執刀医の債務不履行責任,不法行為責任が肯定されたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第1455号 損害賠償請求事件
平成15年2月24日判決
【手技,術後管理,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和30年生,男性)は,平成10年8月4日,被告病院(総合病院)の耳鼻咽喉科において,扁桃摘出手術を受けた。患者の扁桃肥大は第2度(前口蓋弓より強く突出している状態)で,習慣性扁桃炎の影響で扁桃床との癒着が非常に強く,埋没していた。執刀医は、平成8年4月に医師免許を取得し,平成10年8月までに3件の扁桃摘出手術の執刀経験があったが,本件のような扁桃と扁桃床の癒着が非常に強い症例は初めてであった。
執刀医は,午前10時10分,右扁桃を摘出し,次いで,左扁桃を摘出したが,左扁桃の剥離の際,扁桃床の筋層を一部切除してしまった。その切除部位は,肉眼で見てもへこみが判別できた。左扁桃の摘出を終えたのは,午前10時30分であった。摘出後に見た扁桃の埋没部分は,執刀医が予想していた大きさを上回っていた。執刀医は,ボスミン綿球で圧迫止血をした上で,ウージングに対し,モノポーラ(単極)型の電気凝固器である吸引コアギュレーターを使用して,出血を吸引しながら,両側の扁桃床を広範囲にわたり焼灼止血した。執刀医はバイポーラ(双極)型の電気凝固器の使用は想定しておらず,準備をしていなかった執刀医55分かけて止血し,午前11時25分に手術を終了した。執刀医の指導医が,最後に止血状態を確認した。扁桃と扁桃床の癒着が非常に強かったこともあり,出血量は多く,術中に吸引した血液量は約300mlに達した。
扁桃摘出手術中,扁桃床周辺に血管の拍動は見られなかった。指導医は,術後カルテに「型通りの術式,特に問題なし」と記載した。執刀医は,翌8月5日,患者を診察した際,指導医から指摘を受けて,左扁桃床に扁桃組織の遺残が疑われるものを発見した。術後,患者は,咽頭痛や嚥下時痛を訴え,時々茶色痰を吐出したが,同月10日午前9時の診察時には,出血は認められず,扁桃を摘出後の扁桃床には白苔の形成が認められた。
患者は,同日午前10時15分,突然,咽頭から噴水状の大量出血をし,圧迫止血が試みられたが効果なく,間もなく意識レベルが低下して呼吸停止となり,午前10時20分,人工呼吸や心臓マッサージなどの蘇生措置が開始されたが心停止となり,午後O時57分,死亡した。出血原因は,扁桃床の背後を走行している内頚動脈が破綻したものと考えられている。
患者の妻子は,被告病院を設置する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億4499万8662円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額合計1億3142万1572円) | ||||
| 争 点 | ①扁桃摘出手術について担当医師の手技上の過失の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 9000万0594円 | |||
| ②患者の慰謝料 | 2800万0000円 | ||||
| ③葬儀費用 | 142万0978円 | ||||
| ④弁護士費用 | 1200万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
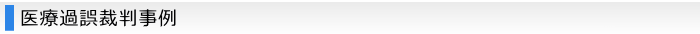
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
扁桃摘出手術後の措置について過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第15886号 損害賠償請求事件
平成14年4月11日判決
【治療方法,時期,術後管理】
<事案の概要>
患者(女性)は,平成11年7月ころ,習慣性扁桃炎と診断され,同年9月13日,被告病院(総合病院)で,扁桃摘出手術を受けた。担当医師(耳鼻咽喉科)は,扁桃摘出後,圧迫止血し,止血を視認してから手術を終了した。
患者は、同日午後2時50分病室に戻り,遅くとも同日午後5時ころ以降,術創からの出血をティッシュペーパーに吐き出す行為を繰り返していたが,間に合わず血を飲み込んでしまい,同日午後10時ころ,巡回した看護師に不快感を訴えた。同月14日午前O時15分ころ,下血が始まり,午前3時ころにはレパ一様の血塊を吐き出したためにナースコールをし,同日午前5時45分ころには血塊の混じった嘔吐をし,同日午前7時ころには貧血のために歩行困難をきたしていた。
担当医師は,午前9時ころ患者を診察し,患者はヘルパーに付き添われて車椅子で移動しなければならないほどの貧血状態で,ヘモグロビン量が術前の14g/dlから11.7g/dlに減少していたが,止血のための特別な措置をとらなかった。
同日午後3時ころ,患者は,出血が止まらなかったため,担当医師の診察を受けたが,担当医師は止血のための処置を特に施さなかった。その後も患者の吐血,下血は続き,同日午後9時30分ころ,縫合止血の処置が施された。
患者が,被告病院を開設する法人及び担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1000万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額200万円) | ||||
| 争 点 | ①扇桃摘出手術の際,縫合止血を行うべきであったか否か。 | ||||
| 認容額の内訳 | 慰謝料 | 200万円 | |||
| 判 断 | ①縫合止血を採用すべき義務が担当医師に課されていたとはいえない。 ②平成11年9月14日午前9時時点で患者は軽度の出血性ショックに陥っていたから,患者の出血性ショックの悪化を防止するために,縫合止血により出血を止める必要があった。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
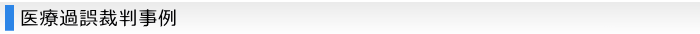
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
咽頭部の横紋筋肉腫に罹患していた患者に対し,ユーイング肉腫疑いと診断して,腫瘍摘出術等を行ったことについて,担当医師に,確定診断のための十分な量の検体を採取したり各種の検査をすべき義務違反,及び,化学療法等を行ってから摘出術を行うべき義務違反がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第29713号 損害賠償請求事件
平成17年11月17日判決 控訴
【検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和59年生,男性)は,平成14年4月27日,喉の痛み,食事や呼吸がしづらいことなどを訴えて,被告病院(大学附属病院)の耳鼻咽喉科を受診した。A医師が内視鏡で患者の咽喉部を観察したところ,中下咽頭部に5,6cm大の巨大な腫瘍塊があり,喉頭を見通すことができな状態で,診断のため腫瘍組織の生検と血液検査が実施された。患者は,同月30日,被告病院に入院し,術前検査として,血液検査,尿検査,胸部レントゲン検査,心電図検査等を受け,気管切開され,5月2日頸部MRI検査,同月8日頸部CT検査が実施された。生検については,同月9日,悪性小児腫瘍である骨外性ユーイング肉腫の疑いと診断された。5月17日以降,血液検査,胸部レントゲン検査が行われ,同月22日胸部CT検査,同月25日頸部MRI検査が行われ,腫瘍サイズは6.5×4.5×8cm大と診断された。
5月30日,患者に対し,下顎離段による中下咽頭腫瘍摘出術・両側頸部郭清術・遊離空腸皮弁による咽頭再建術が実施され,6月3日,大胸筋皮弁による再建術が行われた。同月15日,摘出腫瘍の病理組織検査の結果,骨外性ユーイング肉腫ではなく,小児性悪性腫瘍である横紋筋肉腫であると診断された。被告病院において化学療法が行われたが,同月後半から血小板の減少,肝機能の悪化,DIC(播種性血管内凝固症候群)を併発し,7月9日,骨髄穿刺検査で骨髄内に横紋筋肉腫細胞の浸潤が,同月15日には左頸部にリンパ節転移が見つかり,同日から抗腫瘍化学療法(VAC療法)が開始された。患者は,その後,全身状態に改善が見られ,10月と11月にそれぞれ一時退院をしたものの再入院となり,11月25日の腰椎穿刺(髄液)検査の結果,髄液細胞に横紋筋肉腫の細胞が確認され,放射線治療などが施されたが12月23日に死亡した。
患者の両親は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億1295万1982円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①腫瘍の組織診断のために十分な量の検体を採取したり,必要な諸検査を行うべき義務を怠った過失があったか。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
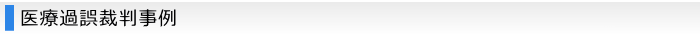
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
耳鼻咽喉科に通院していた患者が,通院を約1年間中断していた間に喉頭癌を発症したことについて,担当医師に,通院中断前に生検を実施しなかった過失,及び,経過観察の必要性の説明を怠った過失がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第23416号 損害賠償請求事件
平成17年10月14日判決 確定
【説明・問診義務,検査】
<事案の概要>
患者(昭和6年生,男性)は平成13年1月25日,嗄声を主訴として被告病院耳鼻咽喉科を受診した。視診にて,患者の右声帯に発赤が認められたが,その他特に異常所見は見当たらなかった。その後,患者は,平成13年の間に,2月1日,同月15日,3月15日,5月24日の合計5回,被告病院耳鼻咽喉科を受診し,抗炎症剤の投与を受けたが,患者の右声帯の発赤は完全に消失することはなかった。担当医師は嗄声は加齢現象によるものだが発赤については経過観察の必要があると考え,毎回の受診日に,次回受診すべき期間を指定し,同年5月24日にも,2か月後の受診を指示した。しかし,患者は,嗄声が加齢現象で治療し難い以上,被告病院に通院する必要はないと判断し,被告病院の受診を取りやめた。平成14年6月6日,患者は,嗄声が悪化したため,再び被告病院耳鼻咽喉科を受診したところ,担当医師は,患者の嗄声の程度が平成13年段階に比べ悪化し,右声帯が麻痺し,腫れも確認されたことから,喉頭癌の可能性が高いと考え,生検目的で甲病院を紹介した。甲病院における検査の結果,喉頭癌(病期Ⅲ期)と診断され,患者は甲病院において放射線治療及び抗癌剤の投与を受け,その後,喉頭癌は治癒した。
患者は,平成13年の受診段階で生検を行うべきだった,経過観察の必要性を説明すべきだったなどと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3343万9110円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①検査義務ないし検査のための転院義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
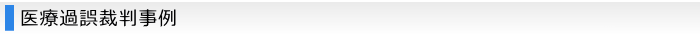
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
甲状腺腫瘍摘出術について,他の検査等により手術適応が認められた以上,さらに穿刺吸引細胞診をすべき注意義務はないとされ,患者に対する説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17363号 損害賠償請求事件
平成17年8月31日判決 控訴
【説明・問診義務,検査,適応】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,女性)は,平成11年7月5日,声の出しづらさを訴え,被告病院(当時国立病院)を受診した。担当医師(耳鼻咽喉科)は,甲状腺腫瘍が疑われたため,血液検査,生化学検査,免疫血清検査,尿検査,聴力検査,頸部超音波検査及びX線検査を施行し,CT,MRI及び甲状腺シンチグラムの検査予約をした。平成11年8月30日,患者は,被告病院に入院し,翌31日,甲状腺亜全摘出術を受け,甲状腺左葉全体(15g),右葉から嚢胞性腫瘍1個が甲状腺実質をつけて摘出され(5g),硬い腫瘤2つが周囲の組織ごと(1g)切除された。患者は,被告病院を退院後も,体調不良を訴えて被告病院を外来受診し,その後,他院に通院し,「腺腫様甲状腺腫・甲状腺右葉切除後」の診断の下,甲状腺ホルモン剤を服用している。
患者は,本件手術後に上記症状が発生したことにより,甲状腺機能低下等の後遺症を発症したと主張するとともに,担当医師には,穿刺l吸引細胞診を実施して手術適応を判断することを怠り手術適応を誤った過失又は患者に対して十分な説明をしなかった過失があると主張して,被告病院を管理していた国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。独立行政法人国立病院機構法が発足したことにより,被告たる地位は独立行政法人国立病院機構が当然に承継した。
| 請求金額 | 合計1557万9493円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者に対する甲状腺腫瘍摘出手術の適応の有無(その前提としての穿刺吸引細胞診の必要性) | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
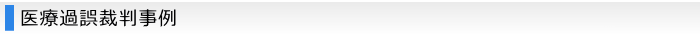
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が,咽頭痛を訴えて複数の医療機関を受診した後,自宅で呼吸困難に陥って死亡したことについて,医師らに急性喉頭蓋炎の徴候を見落とし適切な診療を怠った過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第10041号 損害賠償請求事件
平成16年11月29日判決 控訴
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,男性)は,喉の痛みを訴え,被告病院(総合病院)救急外来A医師,被告医院(耳鼻咽喉科)B医師の診察を受け,帰宅後しばらくして呼吸困難に陥り,救急搬送中,急性喉頭蓋炎により死亡した。
患者の両親は,被告病院を開設する法人及び被告医院の開設者であるB医師に対し,死因となった急性喉頭蓋炎の徴候を見落とし適切な診療を怠った過失があると主張して,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計9109万7600円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①A医師について,入院指示,又は,経過観察を怠った過失の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
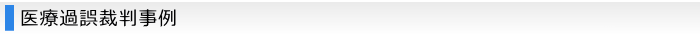
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
いびきのレーザ一治療を実施するに当たり,口蓋垂を切除したことが不必要だったとはいえず,説明義務違反があったとも認められないとされたケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第7894号 損害賠償請求事件
平成16年1月21日判決
【説明義務,問診義務,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(昭和28年生,女性)は,いびき治療のためレーザ一治療を受けることを希望し,平成12年11月8日,担当医師が開設する被告診療所(レーザ一治療科,皮膚科,形成外科,耳鼻科)を受診し,同日,担当医師によりレーザー口蓋弓口蓋垂形成術(LAUP)を受け,その手技において口蓋垂を切除された。
患者は,平成13年5月になって初めて口蓋垂がないことに気付いたと主張し,担当医師が,口蓋垂切除を事前に説明しないでLAUPを行ったこと,手術前と比べ低い声が出にくいことなどを理由に,担当医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者に対するLAUPの術式として口蓋垂切除が不必要であったか。 | ||||
| 判 断 | ①LAUPは,口蓋垂切除を含む手術であり,不必要とはいえない。 ②患者は,口蓋垂切除について説明を受けたことが認められる。 | ||||



| 当堀法律事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
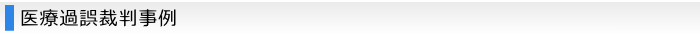
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が呼吸困難を生じ,低酸素脳症を発症して死亡したことについて,医師の気道確保開始の判断及び措置に注意義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第28167号 損害賠償請求事件
平成15年2月27日判決
【入院管理,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,女性)は,くも膜下出血のため被告病院に入院し,脳神経外科医であるA医師により下気管切開され,気管カニューレによる呼吸管理を必要とする状態で甲病院に転院していた。平成11年11月16日,気管カニューレが外れ,翌17日に呼吸状態が悪化したが,開窓部がふさがってしまったため,被告病院に再転送され,同日午後4時ころ被告病院に到着した。
A医師は,同日午後4時10分ころから,患者について約20分程度診察等を行っていたところ,患者の酸素飽和度が90%前半に低下したため,従前の開窓部を再切開して気管カニューレを挿入しよう考え,約10分間で気管切開の準備をした上,再切開(第1次切開)して気管カニューレを挿入しようとしたが,従前の開窓部の下方に肉芽が生じていて挿入できなかった。A医師は,耳鼻咽喉科のB医師も呼び,肉芽を圧排しようと繰り返したが,患者の酸素飽和度が低下し,午後5時ころには呼吸停止も生じたため,患者に対し,通常行われる下気管切開の部位のさらに下側まで切開を行い(第2次切開),カニューレを挿入し,同日午後5時過ぎころ患者の気道を確保したが,患者は低酸素脳症を発症して死亡した。
患者の父が,被告病院を開設している地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3501万7967円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | 患者が被告病院に到着した時に,直ちに気管カニューレの装着を試み,気管切開術その他の気道確保法を施行することにより,遅くとも午後5時の患者の呼吸停止以前に患者の気道を確保すべきであったにもかかわらず,これを怠ったのか否か。 | ||||
| 判 断 | 患者が,被告病院に到着した時点で,酸素飽和度は90%台後半を維持しており,A師は,酸素飽和度が90%台前半に低下した時点で気管切開術を決断したのであるから過失は認められない。気管切開の準備に10分要したのは気管切開の準備に要する時間を逸脱していない。本件肉芽のような,圧排不可能な硬い肉芽が生じていることは予測困難であり,A医師にこれを予見して対処すべき義務があったとはいえない。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
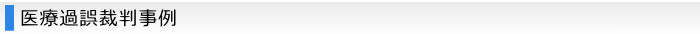
耳鼻咽喉科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
慢性中耳炎を外耳炎と診断して治療を継続したことに過失は認められるが,そのことと患者の聴力障害との間の因果関係や患者の聴力喪失・低下の事実は認められないとされたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第5997号 損害賠償請求事件
平成14年10月28日判決
【検査,診断ミス,治療方法,時期,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(外国人)は,平成9年4月30日に日本へ入国し,日本国内で就労していたが,同年5月26日,入国管理局に収容された。患者は,同年6月上旬から,入国管理センターに移収され,平成11年6月9日に仮放免が許可されるまで,入国管理センターに収容されていた。
患者は,収容直後から,耳痛等を訴え,入国管理センタ一所属のA医師(内科)の診療を受けていた。入国管理センターでは,鼓膜を視診する耳鏡等は備え付けられていなかったが,A医師は,問診,視診等の所見から,患者は外耳炎に罹患しているものと診断し,外耳炎を前提にた薬剤の処方等を行った。
患者は,その後も耳痛をたびたび繰り返し,入国管理センター外部の耳鼻科専門医による診療を求めたが,A医師は,耳鼻科専門医の診療を受けさせなかった。患者は,平成10年6月30日,入国管理センター宛の上申書を提出し,外部の耳鼻科専門医による精密な診断を受けたい旨要請した。A医師の後任医師であるB医師は,耳鼻科専門医による診療を受けさせる必要があるかを判断するため,同年7月3日,患者を診察した。B医師は,患者の右耳痛の訴えが継続し,視診で右耳から浸出液状のものが認められたことから,耳鼻科専門医による診療を受けさせたほうがよいと判断しその手配をした。
患者は,同月9日,入国管理センター外部の耳鼻科専門医C医師の診療を受けたところ,患者の疾患は,外耳炎ではなく,慢性中耳炎であることが判明した。その際に行われた純音聴力検査では,患者の右耳はどの周波数でもまったく反応がなかったが,平成12年2月に行われた他覚的聴力検査であるABR検査の結果では患者の右耳は60デシベル以上の音を与えると脳波が反応を示しており,40ないし50デシベルの音を聴取できる程度に保たれていると診断された。
患者が,入国管理センターの設置者である国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3625万0403円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者の右耳が聴力を喪失しているか,喪失していないとして一定の低下が認められるか。 | ||||
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




