光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
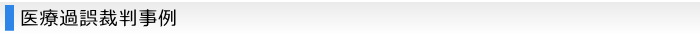
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が急性膵炎,糖尿病性ケ卜アシドーシスのいずれか,ないし併発により死亡したことについて,診断を誤った過失及び転医義務を怠った過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第9561号 損害賠償請求事件
平成18年3月15日判決 確定
【説明・問診義務,転医義務】
<事案の概要>
患者(昭和53年生,男性)は平成13年12月末ごろから腰痛を覚え,年明けからは,腰痛に加え咳,口渇,嘔吐,腹部膨隆等の症状が生じたことから平成14年1月7日午前9時過ぎころ,被告病院(個人病院)を初めて受診し,被告医師(被告病院院長,内科)の診察を受けた。患者は,被告医師に対し,2日前から口渇,嘔気,嘔吐,咳,全身の倦怠感,排便停止等の症状があるが,腹痛や空腹感はないこと,関節痛・咽頭痛があり,前日体温が37.5度あったこと,咳は発作的に出て夜間に多く,喀痰はないこと等を訴えた。患者を診察した被告医師は,腹部膨張,鼓音,腸蠕動音の消失等の所見から麻痺性イレウスを疑った。患者は,診察中,吐き気をもよおしたような動作をしたことがあったが,嘔吐はなく,体温,血圧,脈拍は正常であった。
被告医師は,患者に対し,水を飲むことは危険であるから控えるよう注意するとともに,麻痺性イレウスの機序及び危険性について平易な表現で説明し,設備の整った大きな病院へ行って検査を受けるよう説得した。しかし,患者が,帰宅後,家族と相談してから決めることに固執したため,被告医師は,患者に対し,帰宅後,家族と相談し,できるだけ早く大きな病院へ行くこと,容態が悪化したときは,救急車を呼んで大きな病院へ行くよう指示した。
患者は,同日午後3時ころ,自宅で意識不明となっているところを発見され,同日午後4時10分ごろ,死亡が確認された。患者の死因ないし死因に至る機序は,明確ではないが,急性膵炎,糖尿病性ケトアシドーシスのいずれか,あるいは,併発が考えられた。
患者の両親が,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計8140万円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①被告医師は,患者が麻痺性イレウス,急性膵炎,糖尿病性ケ卜アシドーシスのいずれか,ないし,これらの併発を疑うべきであったか ②患者を直ちに他の病院へ転送すべきであったか | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
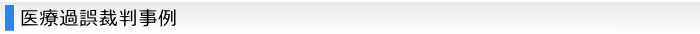
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝不全により死亡した患者について,検査義務違反,輸血における注意義務違反,説明義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第14470号 損害賠償請求事件
平成18年3月8日判決 控訴
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(女性)は,他院に入院していたところ,平成9年7月12日,被告病院に転院した。患者は,肝臓癌であり,被告病院入院した時点で既に手術や化学療法による治療が功を奏さず,積極的な治療ができない末期癌の状態であった。被告病院は,患者に対し,同年12月6日,同月7日,濃厚赤血球(MAP)2単位,新鮮凍結血漿(FFP)2単位をそれぞれ輸血し,同月8日にMAP1単位,FFP1単位を輸血し同月29日,同月30日にFFP3単位をそれぞれ輸血した。患者は,平成10年1月7日,肝不全及び肺炎により死亡した。
患者の家族は,患者が死亡したのは,検査義務違反,不必要な輸血をした注意義務違反,説明義務違反があったからであるとして,被告病院を開設する医療法
人に対し損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2082万円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①総ビリルビン値が上昇した原因 ②白血球数が上昇した原因 ③検査義務違反等の有無 ④輸血における注意義務違反の有無 ⑤説明義務違反の有無 | |||
| 判 断 | ①総ビリルビン値の上昇原因が本件各輸血とは認められない。 ②白血球数上昇の原因が本件各輸血とは認められない。 ③被告病院に入院した目的は褥瘡治療であり,肝臓癌は末期で治療不能な状態であったから注意義務違反は認められない。 ④輸血により症状に改善が見られており不必要な輸血とはいえない。MAPやFFPによる輸血は相当である。 ⑤必要性,合併症等について説明されており説明義務違反は認められない。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
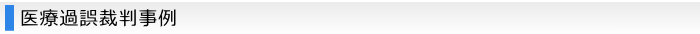
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
イレウスを発症し入院3日後に死亡した患者の治療について,イレウス管の挿入時期・方法,挿入後の監視等につき,担当医師の過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第7721号 損害賠償請求事件
平成17年7月20日判決 控訴後和解
【治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(昭和3年生,男性)は,平成15年9月14日昼ころ心窩部痛を覚え,翌15日午前11時10分,被告病院(総合病院)へ緊急搬送され,単純性イレウスと診断され,入院となった。絶飲食,点滴治療,投薬が開始され,16日午前中,主治医であるA医師が患者を診察したところ右側下腹部の圧痛と腹部の膨満が認められ,腹部CT検査では,小腸内に多量の腸液貯留が認められた。B医師は,同日午後2時15分ころ,X線透視下でイレウス管を挿入したが,十二指腸まで挿入できず,イレウス管を胃内に留置した上で120㎝まで挿入し,同日午後7時35分ころ,C医師がX線透視下でイレウス管を再挿入した。その際、患者が多量に嘔吐したため,C医師は,イレウス管をトライツ靭帯より肛門側へ20㎝挿入したところで中止した。患者は,同日,3度自己抜去し,その都度C医師が再挿入した。患者は,9月17日午前3時15分ころ,心拍数下降,呼吸停止,瞳孔散大し,同日午前3時16分ころ,心停止した。C医師は,蘇生措置を講じたが状態は改善せず,同日午前9時52分ころ,患者の死亡が確認された。
患者の子2人が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計4648万1124円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①初診時,胃管挿入をしなかった注意義務違反ないし過失の有無 ②9月16日午後2時15分までの間に,イレウス管の挿入や開腹手術を行わなかった注意義務違反ないし過失の有無 ③イレウス管の初回挿入時の手技を誤った注意義務違反・過失の有無 ④初回挿入時の失敗後,直ちに再挿入あるいは開腹手術を行わなかった注意義務違反ないし過失の有無 ⑤9月16日午後8時ないしその数時間以内に開腹手術を行わなかった注意義務違反・過失の有無 ⑥9月16日夜から同月17日未明にかけて,患者の監視を怠った注意義務違反・過失の有無 | |||
| 判 断 | ①初診時,患者は,腹部レントゲン所見でガス量が少なく,筋性防御所見,ブルンベルグ徴候・電解質異常は認められず,腹部膨満は認められたが元気な状態でショック症状はなく,担当医師が過去に胃癌で開腹手術した点を考慮し胃管挿入を行わず身体への侵襲性の低い絶飲食・輸液の実施という保存的治療方法を採用した判断は相当である。 ②患者には,腸管穿孔,腸管壊死などの腹膜炎や絞扼性イレウスを疑う徴候は認められず,患者の胃癌摘出の既往や高齢であること,開腹手術に予測される危険性を考慮すれば注意義務違反があるとは認められない。 ③胃癌で胃の3分の2を切除しており,通常の患者に比べイレウス管んぼ挿入が困難であったことに照らせば,担当医師が十二指腸ないし小腸まで挿入できなかったことに注意義務違反があるとはいえない。 ④9月16日時点で患者は元気な状態であり,B医師が癒着性イレウスを想定し開腹後の癒着によりイレウスを繰り返す危険を考え減圧処置による改善を期待したことを考慮すれば注意義務違反は認められない。 ⑤2回目のイレウス管挿入で排出量が増量し,減圧効果が認められていたこと,高齢で胃癌摘出の既往で開腹手術に危険を伴ったことを考慮すれば,注意義務違反は認められない。 ⑥患者がイレウス管を自己抜去した後,医師・看護師らはイレウス管の必要性を患者に説明した後,繰り返し管を挿入するなどイレウス管が適切に機能するよう監視管理していたのであるから,注意義務違反は認められない。患者が,嘔吐した胃液を気管に誤嚥して窒息した可能性があるとは認めるに足りない。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
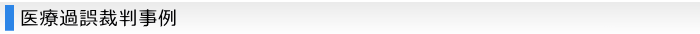
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
未決勾留中の患者が刑務所外部の医療機関に転送されイレウス(腸閉塞)の開腹手術を受けたことについて,刑務所の看守に適切な処置をなさず外部の医療機関への転送が遅れた注意義務違反が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第18285号 損害賠償請求事件
平成16年8月30日判決 確定
【治療方法時期,転医義務】
<事案の概要>
患者(昭和3年生,男性,医師)は,平成13年1月9日に逮捕され,2月1日刑務所に移監され,未決勾留(有罪が確定しない者に対する身柄拘束)中であった。
患者は,4月15日未明に胃痛を訴え,胃痛散の投与がされ,同日午前6時30分ころ,准看護師が患者の様子を見に行き,同日午前7時前ごろ,担当医師に連絡された。担当医師は,午前7時30分ころ非常登庁し,午前8時ころ患者を診察し,経過観察とした。担当医師は,翌16日午後1時ころ,同日午前9時前に採血した血液検査の結果を確認後,患者の診察を行ったところ,圧痛,腹部痛,筋性防御が認められ,腸音も低下し,腹部立位エックス線上,腹部に著明な大腸ガス像が認められたことから,「腸閉塞,腹膜炎,胸膜炎」と診断し,患者を同じ県内にある甲病院へ転送した。患者は,甲病院において,急性汎発性腹膜炎,絞扼性イレウスの疑いで緊急開腹手術を受け,大腸等が切除された。
患者は,刑務所を設置する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3178万7660円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①4月12日以降,患者が腹痛を訴えたにもかかわらず,刑務所の看守が適切な処置をしなかったか否か。 ②担当医師は,4月15日,患者の検査結果や訴え等から,直ちに外部の医療機関に患者を転送すべきであったか否か。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
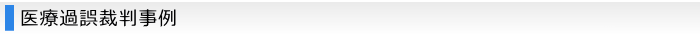
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
大腸癌を発見できなかったことについて,その時々の患者の症状に応じて最も疑われる疾患について必要な検査を行い,その検査結果に基づき適切な処置をとっていたとして過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第18909号 損害賠償請求事件
平成15年12月26日判決
【検査】
<事案の概要>
患者(昭和5年生,女性)は,平成4年4月から平成12年8月にかけて,高血圧及び糖尿病の治療のため,定期的に,被告病院(総合病院)内科へかかり,主にA医師の診察を受け,便秘を訴えて下剤を処方されることも時折あった。
患者は,平成12年7月21日から同年8月21日にかけて,被告病院消化器科のB医師らの診察も受けるようになり,胃潰瘍及び腸炎について治療・検査等を受けていた。
患者は,同年8月22日,下腹部痛を訴え,救急車で被告病院に搬送され,腸閉塞が疑われ,血圧低下による前ショック状態にあったため,入院となり,同日中に回腸痩造設術の緊急手術が実施された。同年9月,注腸検査で,上行結腸に全周性の癌(後にグループ5の腺癌,ステージⅣと判明)と両肺及ぴ肝臓に多発性転移が認められ,その後,右半結腸切除術,人工肛門閉鎖の手術,吻合不全部切除,胃空腸吻合,腹腔内ドレナージの手術が実施されたが,患者は,同年11月21日,上行結腸癌により死亡した。
患者の子は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1000万円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | A医師及びB医師らが,平成12年7月末までに大腸癌を疑って必要な検査等を実施しなかった過失の有無 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
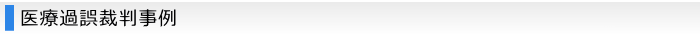
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
高齢患者に対して膵臓癌の切除手術時期を延期したことや,抗癌剤の動注療法を実施しなかったことに過失はなく,患者がMRSAに感染したことについても過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第16051号 損害賠償請求事件
平成14年10月30日判決
【説明・問診義務,入院管理,治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(大正4年生,男性)は,甲病院(総合病院)において膵臓癌と診断され平成11年2月23日,癌専門病院である被告病院の内科外来を受診した。A医師(内科)が主治医となり,同日から同年3月3日まで検査が行われ,膵臓癌と診断されし,手術の適応があったため,B医師(外科)が紹介された。B医師は,同月9日,患者を診察し,手術内容について説明し,患者の入院手続を行い,同月11日,被告病院内科と外科のカンファレンスによって患者に対し手術を行うことが決定された。患者が,乙大学により開発された治験薬である丸山ワクチンの投与を希望したところ,A医師はこれを許可し,患者の手術は延期された。
同年4月28日,患者に対し,CT検査が行われ,検査の結果,同年5月6日,患者の腹腔動脈及び上腸間膜静脈に癌の浸潤が認められた。A医師は,手術が不可能と判断し,同月17日,患者に対し,抗癌剤を動脈から注射する「動注療法」を施行したが、それ以後は動注療法を実施せず,疼痛対策主体の治療方針を立て,同年8月5日からその一環として放射線治療を開始し,同月11日,患者を被告病院放射線科に入院させた後,同年9月2日内科に転科させた。
患者は,本人の希望で同月20日に丙病院へ転院予定であったが,同月10日,MRSAに感染していたことが判明したため,MRSAが陰性となる同月27日まで丙病院へ転院できなかった。
患者は同年11月5日に死亡した。
患者の家族(妻及び子)が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計8800万円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①患者に対する膵臓癌に関する治療は違法か。 ②被告病院は,患者及びその妻に対し,膵臓癌の手術が手遅れになること,膵臓癌の手術ができなくなったこと,その後治療方法がないことなどについて説明したか。 ③患者を平成11年9月2日,放射線科から内科病室へ移したのは違法か。 ④同月10日の院内感染は,被告病院の過失に基づくものか。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
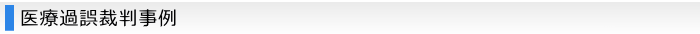
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
C型肝炎に対するインターフェロン治療の実施方法等に過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4050号 損害賠償請求事件
平成14年5月27日判決
【治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(平成12年5月当時46歳,男性)は,平成10年6月C型肝炎の診断を受け,ウルソサン錠や強力ネオミノファーゲンCなどの投与を受けていたが,平成11年12月,肝機能が急に悪化し,倦怠感がひどくなったため,平成12年1月11日,インターフェロン治療を受けるため被告病院(市民病院)内科に入院した。
担当医師は,フェロン(インターフェロンベータ型)600万単位を6週間で静脈注射後,イントロン(インターフェロンアルファ型)1000万単位を18週間で筋肉注射し,イントロン注射は,開始後1週間様子を見た後,外来で実施する治療計画を立てた。
インターフェロン治療開始後1週間程度及び同年2月末にインターフェロンの種類を切り替えた直後,微熱が認められたほか,治療継続中不眠などの精神症状は認められたが,担当医師は,インターフェロン治療に伴う副作用であるが,インターフェロン治療を中止しなければならないほど重大ではないと判断し,治療を継続した。
同年2月末,インターフェロンの種類を切り替えた後,インターフェロン治療は他院の外来で行われた。同年5月末,患者が,被告病院内科を受診し,うつ等の精神的症状を訴えたため,担当医師は,インターフェロン治療を一時中止するよう上記他院に連絡するとともに,被告病院精神科を受診させたが,同年6月末には復調したため,被告病院外来において,インターフェロン治療を再開した。同年7月末まで患者に対し外来でインターフェロン治療が行われたが,患者からうつ等の精神的症状を訴えられることはなかった。
インターフェロン治療によって患者のC型肝炎は治癒したが,患者は,治療終了後3週間ほど経てから,不眠・不安感等の精神的症状や手の震えなどの機能的症状を訴えるようになり,平成13年1月には,大阪府より精神障害1級の認定を受けた。
患者が被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2億1151万5953円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①患者の精神的症状及び機能的症状の有無 ②副作用と思われる症状が現れた時点でインターフェロン治療を中止したり入院期間を延長すべきであったか,インターフェロン治療一時中止後再開するに当たって副作用の再発を念頭に置いた対応がとられていたか。 ③患者の精神的症状等は,インターフェロン治療によって生じたものか。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
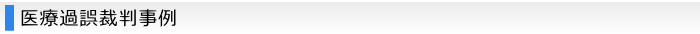
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
膵臓癌の診断に関する検査を怠った過失があるが,結果との間の因果関係がないとして責任が否定されたケース
大阪地方裁判所 平成11年(ワ)第1722号 損害賠償請求事件
平成13年10月31日判決
【検査,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,女)は,平成5年9月,被告病院において,慢性膵炎と診断され,入院加療後,いったん退院したが,同年10月17日,総胆管末端の狭窄による胆嚢炎,胆管炎等と診断されて入院し,同月22日,胆嚢摘出術及び総胆管十二指腸吻合術を受け,同年11月13日退院した。
患者は,退院後,慢性膵炎等により定期的に被告病院に通院していたところ,平成6年7月26日のCT検査で,膵頭部腫大,内部密度濃度の乱れ,膵内のう胞性低吸収域が認められ,形状から膵臓の悪性腫瘍も否定できないとされたが,主治医A(外科,消化器外科)は,慢性膵炎と診断した上で経過観察を行い,6か月後に再度CT検査をすることとした。
同年10月22日の外来受診時,患者は,入院当初体重が59kgであったのが,54kgに減少し心配していると訴え,同年12月19日には,51.5kgに減少していたがA医師は慢性膵炎の影響と考え,経過観察を続けた。
平成7年3月7日及び同月31日の腹部CT検査の結果,B医師(消化器外科)は膵臓癌を疑い,同年4月11日,患者に対し手術が実施されたが腫場を摘出することができず,患者は,平成8年9月4日,膵臓癌により死亡した。
患者の夫及び2人の子が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計 2008万7823円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①A医師は,平成5年10月22日の時点で,膵臓癌を疑い,細胞診・膵液検査等の検査を行うべきであったか。 ②A医師は,平成6年7月26日の時点で膵臓癌であることを疑い,適切な治療を開始すべきであったか。 ③A医師は,平成6年12月19日の時点で,膵臓癌であることを疑い,適切な治療を開始すべきであったか。 ④上記①〜③の過失と患者の死亡との間の因果関係 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
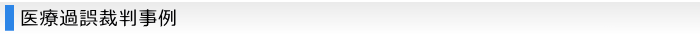
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
自己免疫性肝炎の患者に対してステロイド療法を行わなかった注意義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第23035号
平成17年12月8日判決 控訴
【治療方法時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(大正14年生,女性)は,昭和53年ころから,被告A医師の診察を受けるようになり,昭和61年ころ,A医師から肝炎と診断され,以後,定期的に血清アミラーゼ値の検査を受けるとともに、漢方薬である小柴胡湯等の処方を受けた。
患者は,平成4年ころから,被告A医師に代わって,被告A医師の息子である被告B医師の診察を受けるようになった。被告B医師は,平成5年ころ,自己免疫性肝炎に罹患しているのではないかと診断した(確定診断ではない。)ものの,肝炎に対する治療の第1選択とされるステロイド療法を実施せず,小柴胡湯による治療を継続した。
患者の肝炎は,平成9年ころには肝硬変に移行し,平成11年ころ,食道静脈瘤が破裂し,別の病院に入通院していたが,平成13年3月ころ,3度目の食道静脈瘤破裂が生じ,同年6月15日,死亡した。
患者の家族(子ら)が,被告A医師及び被告B医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1億1417万1702円 | |||
| 結 論 | 一部認容(認容額 3995万9882円) | |||
| 争 点 | ①自己免疫性肝炎に対する適切な治療を怠った注意義務違反の有無被告医師らは,遅くとも自己免疫性肝炎と診断した平成5年5月27日ころまでに,ステロイド療法を実施すべきだったか否か ②①の注意義務違反と患者の死亡との因果関係の有無 | |||
| 認容額の内訳 | ①死亡慰謝料 | 2200万0000円 | ||
| ②入通院慰謝料 | 300万0000円 | |||
| ③介護費用 | 652万5341円 | |||
| ④葬儀費用 | 150万0000円 | |||
| ⑤証拠保全謄写等費用 | 33万4541円 | |||
| ⑥患者の家族の慰謝料 | 各100万0000円 | |||
| ⑦弁護士費用 | 360万0000円 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
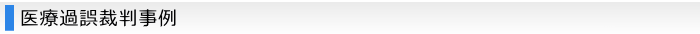
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
C型肝炎患者に対し,①インターフェロン療法の適応を検査し,適応があれば自ら実施するか,他の実施可能な医療機関に転院させる義務を怠った過失,②肝細胞癌の早期発見のための検査をする義務を怠った過失が認められたが,死亡との因果関係は,①は否定され,②は肯定されたケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第1996号 損害賠償請求事件
平成17年11月30日判決 控訴
【検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和12年生,男性)は,平成4年2月10日,被告医師の開設する被告医院を受診し,検査の結果,被告医師からC型ウイルス性肝炎と診断されたが,インターフェロン投与の適応を判断するためのHCV-RNA定量検査及びHCVセロタイプ測定検査は行われなかった。
患者は,その後約10年間被告医院を通院したが,被告医師は,その間,肝細胞癌早期発見に必要な検査のうち,血小板数検査をまったく行わず,腫瘍マーカー検査を4回,腹部超音波検査を2回,CT検査を1回行ったのみであった。
患者は,平成13年3月8日,被告医院が休診であったため,甲外科を受診した。CT検査で,肝臓に多発性腫瘤が認められ,甲外科のA医師は,多発性肝癌を疑ったが,患者は甲外科に通院しなかった。
患者は,平成13年12月3日,腹部に激痛を覚え,被告医師が不在であったため,甲外科に搬送され,A医師により多発性肝癌と診断された。患者は,平成14年1月8日,乙病院を受診し,多発性肝細胞癌と診断された。担当医師は,患者の妻子に対し,患者の癌は治療が困難なほどの末期である旨説明した。患者は,同年6月23日,肝細胞癌により死亡した。
患者の家族(妻及び子)が,被告医院及び被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計6872万1332円 | |||
| 結 論 | 一部認容(認容額3924万5390円) | |||
| 争 点 | ①インターフェロン療法を行わなかった過失の有無 ②肝細胞癌の早期発見のための検査を怠った過失の有無 ③因果関係の有無 ④損害額 | |||
| 認容額の内訳 | ①治療関係費 | 194万8520円 | ||
| ②自宅療養関係費 | 37万0543円 | |||
| ③入院維費 | 15万6000円 | |||
| ④交通費 | 10万1180円 | |||
| ⑤葬儀費用 | 150万0000円 | |||
| ⑥逸失利益 | 400万0000円 | |||
| ⑦慰謝料合計 | 2800万0000円 | |||
| ⑧損害の填補 | △33万0853円 | |||
| ⑨弁護士費用 | 350万0000円 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
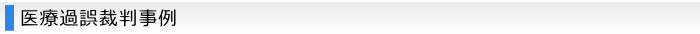
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
レントゲン検査において,胃の悪性病変を疑わせる部分を見落とした点に過失があり,死亡時になお生存していた高度の蓋然性は認められないが,相当程度の可能性が認められるとされたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第10921号 損害賠償請求事件
平成17年8月31日判決 確定
【検査,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和31年生,女性)は,食欲不振,食後のむかつきなどを訴え,平成5年4月27日,被告診療所のA医師の診察を受け,胃のレントゲン検査を受けた。仰臥位で撮影されレントゲン写真(以下「本件写真」という。)には,胃体中部後壁にバリウムの溜まりが映し出されており,潰瘍があり,周辺部に潰瘍によるむくみが生じて盛り上がっていることを示唆する悪性の病変を疑わせる所見であった。しかし,A医師は,本件写真で胃の下部に黒く抽出された部分から胃炎と診断し,胃体中部後壁のバリウムの溜まりの存在を認識しながら,再度のレントゲン検査や胃内視鏡検査の受診を指示しなかった。患者は,同年5月ころ,A医師とは別の医師の診断を受けようと考え,被告診療所のB医師の診察を受けたが,B医師も,胃潰瘍ないし胃癌の可能性を疑わず,精査を指示しなかった。
患者は,平成6年11月3日,自宅で気を失って倒れたため,翌4日,被告診療所を受診し,被告病院においてレントゲン検査及び胃内視鏡検査を受けた。患者は,病理組織学的検査の結果,悪性度Ⅴの中等度分化型腺管状腺癌であると診断された。
患者は,同月21日,甲病院(総合病院)に入院し,C医師が主治医となって,同年12月1日,胃全摘除,脾摘除,膵体尾部切除,胆嚢切開及び左副腎摘除の手術を受けた。病理組織検査の結果,患者の胃癌は肉眼視的には中部後壁にあるボールマンⅢ型の進行癌であり,原発巣の胃壁深達の程度は,癌の浸潤が漿膜下組織を越えて漿膜面に達している(S2,SE)が,他臓器への浸潤はなく(T3),リンパ節への転移の程度は,第2群リンパ節への転移を認めるが,第3・4群リンパ節への転移は認められず(N2),播種性の転移及び肝転移は認められなかった(P0,H0)。胃癌の進行度はステージⅢbであり,根治手術は成功し,根治度Bであった。患者は,平成12年2月,左右卵巣腫瘍のため開腹手術を受け,右卵巣は摘出されたが,左卵巣は摘出されることなく手術が終了した。この卵巣腫瘍は,病理組織検査の結果,低分化腺癌であり,胃癌からの転移と診断された。患者は,平成14年3月29日,癌性腹膜炎により死亡した。
患者の家族(夫及び子)は,被告診療所及び被告病院を開設する法人,A医師及びB医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1.合計8103万円 | |||
| 結 論 | 一部認容(認容額 4名合計878万9999円) | |||
| 争 点 | ①本件写真における異常陰影の有無及び胃癌発見の可能性 ②本件検査において癌が疑われていた場合の患者の延命可能性 | |||
| 認容額の内訳 | ①患者の慰謝料 | 800万円 | ||
| ②弁護士費用 | 合計 79万円 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
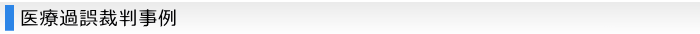
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
免疫療法を末期癌患者に実施するにつき,担当医師に説明義務違反があり,患者が自らの意思で治療方法を決定する機会を奪われたことについての精神的損害を賠償する責任が認められたケース
東京地方裁判所 平成16年(ワ)第2952号 損害賠償請求事件
平成17年6月23日判決 控訴
【説明・問診義務,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和21年生,女性)は,平成13年5月11日,甲病院(総合病院)において緊急手術を受け,卵巣・肝転移・腹膜播種を伴った回盲部大腸癌である術中診断され,卵巣・子宮切除及び大腸回盲部切除術を受けたが,肝転移については処置がなされなかった。患者は,その後,甲病院外科に外来通院し抗癌剤である5-FU,アイソボリンの点滴投与を受け,同年9月時点では肝転移は縮小し,腫瘍マーカー(CEA)も低下した。患者が,抗癌剤の副作用がつらいと訴えたため,抗癌剤を内服薬フルツロンに変更したところ,腫瘍マーカー(CEA)が上昇したため,同年11月から,再び5-FU,アイソボリンの点滴投与が開始されたが,肝転移は増大した。平成14年1月28日,甲病院で肝臓部分切除・胆嚢摘出手術が実施されたが,取りきれない肝転移があったので,5-FU,アイソボリンの点滴投与が続けられたが,同年5月15日には肝転移・肺転移の増大が確認され,翌16日から,抗癌剤CPT-11(カンプ卜)を追加投与したが,副作用が生じ始めた。
患者は,被告診療所から取り寄せた資料やA医師の書籍等を読み,同年5月31日にA医師の診察を希望して被告診療所を受診した。同日時点で患者には大腸癌(結腸癌)の遠隔転移があり,病期(ステージ)はⅣであった。患者は,同年10月30日まで,被告診療所等で新免疫療法を受けたが,同日,被告診療所で患者の診療を担当したB医師は,自ら勤務する乙病院(総合病院)に患者を紹介した。患者は以後,乙病院においてB医師から種々の抗癌剤の投与を受けたが,平成15年9月3日に死亡した。
A医師は免疫学の専門医であり,平成7年には大学医学部助教授に就任,平成10年5月から平成16年8月まで、大学研究所教授として研究・診療に従事し,平成9年9月からは被告診療所を開設して診療をするようになった。A医師は,癌患者に対し,新免疫療法と称する治療を実施し,一般向けに新免疫療法に関する書籍を出版し,講演等を行っていたほか,新免疫療法の実績等を示すウェブサイトを公開し,被告診療所を受診する患者等に「新免疫療法(NITC)のご案内」と題するパンフレット等を手渡していた。パンフレットには,新免疫療法の内容・メカニズムの説明のほか,新免疫療法の特徴として,患者によっては劇的な治療効果が得られていることや癌の種類に関係なくどんな癌にも対応できること,抗癌剤と異なり副作用がほとんどないこと,QOL(生活の質)が高まること,抗癌剤や放射線治療の副作用も軽減できること等が記載され,驚異的な治療効果と題し,CR(著効。4週間以上癌が消失している状態)やPR(有効。癌が半分以下に縮小し4週間以上保てた場合)等の用語を用い,数値を挙げて画期的な奏効率の実績が記され,大腸癌を含む各種癌に新免疫療法又は新免疫療法とイレッサを組み合わせた治療で効果があったとの記載もあった。被告診療所におけるA医師の新免疫療法は,診察,腫瘍マーカーの測定等の検査,SPG(ソニフィラン),OK-432(ピシバニール),PSK(クレスチン),ビタミンD3(活性型ビタミンD),ウルソデオキシコール酸等の処方であり,被告薬局において,健康食品であるILX,ILY,ベターシャークMC・LO,OG1・3A(ニゲロオリゴ糖),SIA,イミュトール,総合ビタミン等が処方されていた。患者も同様の診療・処方を受けた。
患者の夫が,A医師及び被告薬局に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | A医師に対し合計2133万1799円 | |||
| 結 論 | 一部認容(認容額A医師に対し200万円) | |||
| 争 点 | ①A医師が,新免疫療法の効果が乏しいことを容易に知り得たにもかかわらず,化学療法や放射線療法の説明をせずに新免疫療法を選択させ,患者の延命利益を奪ったか。 ②A医師は,イレッサの適応や副作用について説明を怠ったか。 ③被告薬局が,患者に対し,自ら販売する健康食品等が,医薬品ではなく癌の治療効果をもつものでないことを告知すべきところ,これを怠り,新免疫療法の効果について患者が誤信しているのに乗じて高額の健康食品等の販売を行ったのか否か。 | |||
| 認容額の内訳 | 慰謝料 | (A医師が賠償すべき損害)200万円 | ||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
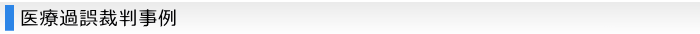
消化器内科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
肝不全で死亡した患者について,適切な治療を怠り,適切な治療を施すことのできる医療機関に転院させなかった過失が認められたケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第9525号 損害賠償請求事件
平成16年5月26日判決 確定
【治療方法・時期,転医義務,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和14年生,女性)は,平成13年6月18日,被告診療所を受診し,被告被告医師から,肝炎,胆嚢炎等の疑いがあるとして,その後,薬剤の点滴投与等を続けていた。患者は,平成14年4月30日,転院し,同年5月2日,肝不全により死亡した。
患者の家族は,被告医師が平成13年6月18日時点で、肝機能障害の原因を解明せず、適切な治療を怠った,又,平成14年4月18日時点で重篤な肝機能障害を疑い,肝障害の劇症化及び肝腎不全の発症を予測し直ちに劇症化に対処し得る医療機関に転医させるべき注意義務に違反したとして,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計7797万8720円 | |||
| 結 論 | 全部認容(認容額7797万8720円) | |||
| 争 点 | ①肝機能障害の原因を解明せず適切な治療を怠った過失及び因果関係の有無 ②肝炎の劇症化に対処し得る医療機関に転医させなかった過失及び因果関係の有無 | |||
| 認容額の内訳 | ①葬儀費用 | 150万0000円 | ||
| ②逸失利益 | 4447万8720円 | |||
| ③死亡慰謝料 | 2500万0000円 | |||
| ④弁護士費用 | 700万0000円 | |||
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




