光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
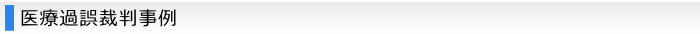
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
レーシック手術において,施術の危険性についての説明義務違反が認められず,レーザー発生装置の動作不良も認められず,手術適応を欠くとも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第14522号 損害賠償請求事件
平成17年3月4日判決 控訴
【説明・問診義務,適応】
<事案の概要>
患者(昭和52年生,男性)は強度の近視(裸眼視力:右0.03,左0.03)があり,視力矯正手術に関心があったため,平成13年6月27日,被告病院を受診し,同年8月10日,両眼にレーシック手術を受けた。術後,裸眼視力は,右0.5,左0.9であったが,患者は右眼が見えにくくなったとして,右眼に再度のレーシック手術を希望した。平成14年8月25日,被告病院において,右眼に対する再度のレーシック手術が施行された。再手術で,裸眼視力は,右0.5,左1.0であり,右眼の視力が改善しなかったため,患者は,3度目の手術を受けることを希望した。そこで,同年12月20日,被告病院において,患者に対し,右眼に対するウェーブ・フロント・レーシック手術(レーシック手術の一種で,コンピューターによる角膜の解析結果に基づきレーザーが照射される。)が施行された。術後,裸眼視力は,右0.3,左1.5で,患者の右眼にセントラルアイランド(レーザー角膜屈折矯正手術の合併症で,照射領域の中央に,照射部位周辺に比べて高い屈折力の領域が島状に残存する状態)が生じ,患者は平成15年1月14日を最後に被告病院への通院を終了した。
患者は,再手術又は,再々手術によって右眼にセントラルアイランドが生じたとして,レーザーの照射方法を誤った,患者に対する手術方法が医学的に確立していない,手術の合併症について説明がなされなかったなどと主張し,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3293万9163円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①再々手術における説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
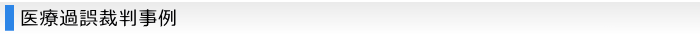
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
汎網膜光凝固法について,手術適応の過失,手技上の過失,説明義務違反がいずれも認められず,施術後の視力低下等との間の因果関係も否定されたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第3174号 損害賠償請求事件
平成16年10月27日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,適応,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,男性)は,平成7年1月21日,脳内出血で被告病院(総合病院)脳神経外科に入院し,内科医師により糖尿病と診断された。同年2月2日,飛蚊症の症状が見られたため,患者は,同月3日,眼科に紹介された。その時点の患者の視力は,右0.8,左0.6であった。担当医師A(眼科)は,同月10日,眼底撮影及び蛍光眼底造影撮影を行い,同月17日,患者の右眼につき増殖前糖尿病網膜症(BⅠ),左眼につき増殖性糖尿病網膜症(BⅡ)と診断した。同医師は,患者に対し,眼底写真を示し,糖尿病が進行し,放っておけば失明する可能性が高く,すぐ治療を開始しないと症状が悪化し,早晩視力を失う可能性があり,すぐ治療をしましょうと告げ,その際,レーザー光凝固治療が唯一の選択であるが,同治療により,一過性に黄斑浮腫が増強して視力低下を起こす可能性がある旨説明した。患者に対し,同日から同年4月27日までの間に,右眼4回,左眼5回のレーザー光凝固治療(網膜全領域を凝固する汎網膜光凝固法。本件では,各回網膜の4分の1ずつ実施された)が実施された。同年5月12日時点で患者の視力は,右0.8,左0.4であった。患者は,その後,同年12月までの間に硝子体出血を生じたため,同月18日,被告病院に入院し,平成8年2月5日及び同年4月15日に担当医師B(眼科)により硝子体切除術を受けたが,同月22日の患者の視力は右0.1,左0.08であった。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2200万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者に汎網膜光凝固法の適応があったか | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
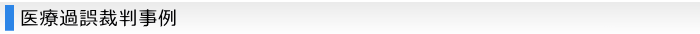
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
近視矯正のためのPRK手術後,角膜不正乱視による矯正視力の低下等を生じたことについて,適応のない手術を行った過失,説明義務違反,手技上の過失がいずれも認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第14372号 損害賠償請求事件
平成16年6月30日判決 控訴
【説明・問診義務,手技,適応,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和32年生,男性)は,左眼が乱視を伴う強度の近視(裸眼視力0.01.矯正視力1.2,球面度数-9.87D,円柱度数−1.87D)であった。患者は,平成11年7月,被告医師の開設する眼科診療所を受診し,被告医師の執刀により,裸眼視力を向上させる屈折矯正手術の一種のPRK手術(レーザー光線を角膜に照射し,角膜の一部を蒸散させて扁平化することにより,角膜の屈折率を変化させて裸眼視力を向上させる手術)を左眼に受けた。患者の裸眼視力は一時0.6程度まで改善したが,角膜上皮下の混濁(へイズ)や角膜の再生に起因する屈折力変化による視力低下などが生じたため,被告医師の勧めで,平成12年1月,左眼に2回目のPRK手術を受けた。その後も左眼の裸眼視力は回復せず,眼鏡等で矯正しても0.4〜0.6程度しか矯正視力が得られない状態になり,他の医療機関を受診したところ,角膜上皮下の混濁(へイズ)が残存し,角膜不正乱視(角膜形状の不整に起因して生じる乱視で,眼鏡やソフトコンタクトレンズで視力を十分に矯正できない)を生じていると診断された。
患者は,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計1505万0580円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①被告医師のPRK手術によって患者の視機能に障害が生じたか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
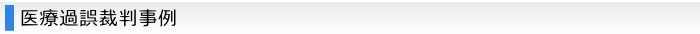
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
前増殖期糖尿病網膜症に対する光凝固療法の具体的方法に不適切な点があるとはいえないとして過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第1451号 損害賠償請求事件
平成15年10月8日判決
【説明義務,問診義務,手術適応,治療方法,時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和17年生,男性)は,平成11年9月13日,甲眼科において,両眼とも前増殖期糖尿病網膜症と診断され,被告病院(総合病院)を紹介された。
被告病院の担当医師は,患者に対し,蛍光眼底造影検査,眼底検査,眼底カラー撮影等の検査を行った結果,両眼とも前増殖期糖尿病網膜症と診断した。担当医師は,糖尿病網膜症が今後急激に悪化し,右眼視力も比較的早期に低下する可能性があると考え,内服薬の投与よりは,前増殖期糖尿病網膜症の進行・悪化の防止等のため,両眼に光凝固療法の適応があり,その治療目的を達成するため,病変部位だけでなく,一定の広範囲を凝固する必要があると判断した。
担当医師は,被告病院において,患者に対し,10月20日から11月4日にかけて,左眼網膜光凝固治療を実施し,10月27日から11月10日にかけて右眼網膜光凝固治療(本件光凝固)を実施し,以後経過観察とした。
その後,患者は,担当医師との間で,視力低下の原因等をめぐって意見が合わなかったことから,平成12年4月10日,被告病院の受診を中止した。
患者は,大学病院で硝子体手術を勧められ,5月20日及び7月20日,乙病院で両眼の硝子体手術を受けた。
その後,被告病院の担当医師は,甲眼科に対し,被告病院における診療情報提供書を送付した。
患者の矯正視力は,被告病院初診時に右眼1.0,左眼0.4であったところ,本件光凝固後の平成12年4月6日には右眼0.3,左眼0.2に低下し,硝子体手術の後の平成13年12月7日時点で,右眼0.5,左眼0.3程度に回復した。
患者は,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3000万円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①患者の右眼について,光凝固の適応にあり,かつ,患者の病態に照らし,適切な方法(凝固部位,凝固密度,後極部への凝固,凝固回数・凝固の時間的間隔など)での光凝固が行われたか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
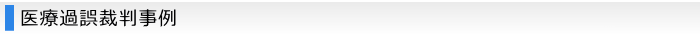
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
同ーのドナーから角膜移植手術を受けた2名の患者が共に失明をしたが,角膜移植手術の手技,及び,その後発症した緑内障の管理等につき,いずれも過失が認められなかったケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第14572号 損害賠償請求事件
平成15年8月29日判決
【手技,入院管理,術後管理,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者A(昭和48年生,女性)は,昭和63年8月10日,被告病院(大学病院)を受診し,円錐角膜との診断を受け,平成2年に左眼表層角膜剥離術を受けた後,平成3年7月16日,左眼に対して全層角膜移植手術(本件A第1手術)を受け,同月28日,被告病院を退院した。患者Aは,その後,角膜融解等の症状を生じたことから再度被告病院に入院し,同年8月9日,緑内障手術及び表層角膜移植手術(本件A第2手術)を受けたが,術後も左眼の状態は改善せず,白内障の発症も認められたため,同月28日,全層角膜移植手術及び白内障手術を受けた。
患者Aは,退院後も被告病院に通院していたが,眼圧が高くなり,再度の緑内障手術が必要となり,平成4年1月16日,再度緑内障手術を受け,その後も緑内障手術等を繰り返し受けたが,左眼の状態は改善しなかった。患者Aは,度々の入院や手術が大きな負担となったため,同年4月9日,被告病院を退院して同病院での治療をやめ,自宅近所の病院で経過観察をすることにしたが,平成10年9月ころ,左眼は失明するに至った。
患者B(昭和52年生,男性)は,平成2年4月23日,被告病院を受診し,円錐角膜であるとの診断を受け,被告病院において,平成3年7月16日,左眼に対して全層角膜移植手術(本件B手術)を受け,同月22日,被告病院を退院したが,その後,角膜内皮及び角膜上皮に損傷を生じ,角膜移植片の状態が悪化し,頭痛や吐き気等の症状が生じたことから,同年10月14日,再度被告病院に入院し,緑内障手術を受けた。患者Bは,その後も,角膜の融解が引き続き認められ,白内障も疑われたことから,同月21日,全層角膜移植手術及び白内障手術を受けた。その後,数度の縫合手術等を経て退院したが,平成4年2月以降,高眼圧状態が続き,被告病院において薬物による治療を試みられたが,平成5年3月23日,再び緑内障手術を受けた。患者Bは,その後も被告病院で表層角膜移植手術を受けたが,左眼の状態に大幅な改善はなく,左眼は失明するに至った。
本件A第1手術及び本件B手術において使用された角膜は,同ーのドナーから提供されたもので,ドナーの年齢は69歳,死因は脳梗塞,梅毒陰性,Hb抗体陰性で角膜移植可と判断されており,角膜保存液の細菌培養検査も陰性であった。
患者両名が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 患者Aにつき7632万7280円 | ||||
| 結 論 | 患者A,Bともに請求棄却 | ||||
| 争 点 | 患者A | ①本件A第1手術の際,虹彩や水晶体を損傷させるなどして緑内障を発生させた過失の有無 ②緑内障の術後管理及び治療の誤りの有無 | |||
| 患者B | ③本件B手術の際,虹彩や水晶体を損傷させるなどして緑内障を発生させた過失の有無 ④緑内障の術後管理及び治療の誤りの有無 | ||||
| 判 断 | ①③本件A第1手術の際に虹彩や水晶体を損傷させたとは認められない。 ②④医師の措置に過失は認められない。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
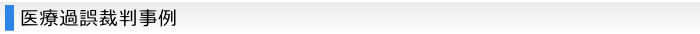
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
糖尿病網膜症の治療に関し,診断義務違反,及び,説明義務違反はないとされたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第2533号 損害賠償請求事件
平成15年2月27日判決
【説明義務,問診義務,診断義務,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,男性)は,30年以上にわたって糖尿病を患っていたところ右眼が1週間前からかすんで視力が低下し,左眼も5,6年前からぼやけて見づらかったことから,平成11年に近所の眼科を受診し,左老人性白内障,糖尿病性網膜症等と診断され,左眼については白内障手術が必要で,右眼は光凝固療法を受け手術しないと失明するとの説明を受けたが,通院しなくなっってしまった。
患者は,約8か月後の平成12年7月,被告病院を受診し,両眼とも1年くらい前から見づらいが,前日から特に見えなくなった,近所の眼科で右眼は手術をしないと失明すると言われていたなどと担当医師に訴え,被告病院へ入院となった。
患者は,被告病院入院2週間後に左眼白内障手術を受け,その20日後に右眼硝子体手術を受けた。右眼硝子体手術において,右眼に長期滞留ガスが注入され,患者は,医師から下を向いて安静にするよう指示されたが,指示を守らなかった。
患者が無断外泊をするようになったため,被告病院は患者の退院を決定した。
患者は,右眼硝子体手術1か月後に他の病院を受診し,両硝子体出血,左続発性緑内障等と診断され,視力は両眼ともOで,その約1年後,両増殖性糖尿病網膜症及び両血管新生緑内障により両眼失明と診断された。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 2178万8250円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①右眼硝子体手術を行うまでの間に,左眼の糖尿病網膜症の診断を行い,適切な治療を行うべきであったか否か。 ②糖尿病網膜症の病状及び治療方法について説明すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠ったか否か。 ③右眼硝子体手術前の患者の右眼の状態は,増殖性糖尿病網膜症の末期であり,光凝固療法がとれない理由,硝子体手術の目的危険性の程度・成功の見通し・視力回復の見通し,右眼の手術が左眼に与える影響,手術を受けない場合の予後などについて,説明すべきであったのに,これを怠ったか否か。 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
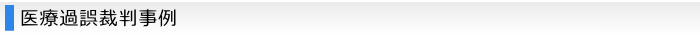
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
アルカリ物質であるモルタルセメントが右眼に入り,失明状態となった患者の治療について,担当医師に,洗眼・モルタルセメント除去義務違反が認められたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第16042号 損害賠償請求事件
平成16年1月29日判決
【治療方法,時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和44年生,男性)は,平成9年6月9日,工事現場で作業中,右眼にモルタルセメントが入ったため,直ちに,モルタルセメントを練るための水を入れたタンクに顔を突っ込んで、,2〜3分程度,眼を開いたり閉じたりして洗った。その後,患者は,約8分かけて手洗い場まで行き,ホースを眼に向け4〜5分程度流水で洗浄し,約10分後,被告病院を受診した。被告病院では,麻酔薬が2,3回点眼され,担当医師は,他の2,3人の患者の診察を終えてから患者の診察をしたが,患者の右眼前眼部は,角膜表面に混濁があったものの,虹彩紋理はよく見える状態で,モルタルセメントが球結膜表面に散在し,上下の結膜嚢内に多量に充満していた。担当医師は,左眼前眼部に異常がないことを確認した後,両眼の眼圧を測定したが,正常であり,両眼の眼底検査では,右眼底がよく見えなかった。担当医師が,助手に,患者の両眼について,フラクトメーター及び検眼レンズによる視力検査を行わせたところ,裸眼視力(右0.1,左0.04),矯正視力(右0.8,左1.0)であった。その後,担当医師は,患者をベッドに寝かせ,洗眼瓶で生理食塩水をかけ,ガーゼでモルタルセメントをこすりながら,患者の右眼の洗浄を行い,点眼薬を患者の右眼に滴下した。担当医師は,患者に対し「眼の中のモルタルセメントはほとんど取れたし,この程度なら1週間くらいで治る。角膜が再生するのに1週間くらいかかる。」などと説明した後,点眼薬,内服薬,座薬を処方し,翌日も来院するよう指示した。
患者は,6月10,11日と被告病院を訪れ、担当医師の治療を受けたが,右眼の回復が思わしくなかったため,同月12日,甲病院を受診し,右眼洗浄後,乙病院(大学病院)を紹介され,同日,乙病院で診察を受けた。診察の結果,患者は,右眼にモルタルセメントの粒が残っている状態で,持続洗眼により,モルタルセメントの除去がなされたが,モルタルセメントを全部は取りきれず,角膜の状態は悪かった。患者は,同月13日,乙病院に入院し,同月16,19日にもモルタルセメントの除去が行われた。同月27日には,丙病院(大学病院)において通院診療が開始され,右眼の矯正視力は上下には変動しながらも,8月9日ころには,0.9になり,患者は,同日,乙病院を退院した。その後,状態が悪化し,患者は,角膜表層移植術を受け,一時は,裸眼視力0.5,矯正視力0.6程度にはなったが,拒絶反応が出るなどして,表層角膜移植術,結膜被覆術,羊膜移植術,結膜縫合術を受けたものの,平成13年12月28日,角膜混濁(瘢痕性角結膜症)と診断され,失明状態となった。
患者が,被告病院を開設する法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 7509万6257円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額1146万3929円) | ||||
| 争 点 | ①洗眼義務違反の過失の有無 ②因果関係 | ||||
| 認容額の内訳 | ①後遺障害による逸失利益 | 343万0429円 | |||
| ②入通院慰謝料 | 400万0000円 | ||||
| ③後遺障害慰謝料 | 260万0000円 | ||||
| ④入院雑費 | 43万3500円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 100万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
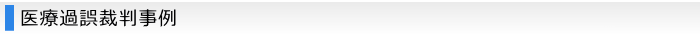
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
白内障手術中に毛様体を損傷した過失,及び,術後の経過観察において,網膜剥離を見逃した過失はいずれも認められなかったが,網膜剥離を発見した後,担当医師が,剥離が黄斑部に達したことを認識しながら,直ちに緊急手術を実施しなかった過失が認められたケース
東京地方裁判所 平成12年(ワ)第11649号 損害賠償請求事件
平成15年5月7日判決
【手技,治療方法,時期】
<事案の概要>
患者(大正9年生,男性)は,平成10年6月2日,被告病院(大学病院)において,右眼の白内障が少しずつ進行しているとの診断され,同年8月18日,右眼の白内障手術を受けるため,被告病院に入院した。入院時の右眼視力は0.6で,視野は正常だった。
患者は,同月20日,担当医師(眼科教授)の執刀で白内障手術を受け,8月30日に退院した。手術中,毛様体上皮が剥離し,硝子体出血による硝子体混濁が生じたが,眼底後極部の網膜剥離には至らなかった。
患者は同年9月2日と9日に被告病院を受診した。2日の診察において,患者から飛蚊症と多重複視の訴えがあり,視力の低下(0.1),周辺部に膜様物の立ち上りが認められたが,膜様物に対する検査は実施されなかった。
9日の診察では,患者の右眼に網膜剥離(裂孔原性網膜剥離。網膜に孔が生じ,この孔から眼球内の水(液化した硝子体)が網膜の下へ入り込んで,網膜が剥離する疾患で,いったん剥離が進行し始めると,自然治癒の可能性は極めて小さく,全網膜が剥離して失明に至る。剥離が黄斑部に達すると視力が著しく低下する。陳旧化すると剥離した網膜に線維膜が形成され,網膜が剥離したままの形で器質化するおそれもある)が発見された。右眼視力は2日が0.1,9日が0.2であった。患者には,視野欠損などの網膜剥離の自覚症状はなかった。
患者は,9月14日に再手術する予定で,9月11日に被告病院に再入院した。11日の診断では,剥離はまだ黄斑部に達しておらず,患者の右眼視力は0.4であったが,12日には,患者の網膜剥離が悪化し剥離が黄斑部に及んび,右眼のほぼ全視野に欠損が生じた。しかし,担当医師は,手術を早める必要はないと判断し,予定どおり14日,右眼の網膜剥離に対する手術が実施された。
患者は,同年10月2日に被告病院を退院したが,右眼視力は,退院後の10月7日の検査で0.1であった。
患者は,平成11年1月13日まで被告病院に通院したが,右眼視力は0.1のままで回復せず,甲病院(大学病院)へ転院した。同病院において,同年4月15日の検査で右眼にも視野狭窄が認められ,平成12年5月22日には,右眼視力は0.04で矯正不能,網膜剥離後の網膜変性により視力回復は不能と診断された。
患者は,平成14年11月21日,視野障害により身体障害程度等級2級の認定を受けた。
患者は,被告病院を開設する国に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 9769万7805円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額2734万2179円) | ||||
| 争 点 | ①白内障手術中に毛様体を損傷した過失の有無 ②9月2日の外来診療時に網膜剥離を見逃した過失の有無 ③9月9日に網膜剥離を発見した後,緊急手術を実施しなかった過失の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 1684万2179円 | |||
| ②慰謝料 | 800万0000円 | ||||
| ③弁護士費用 | 250万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
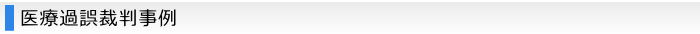
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
他院でレーシック手術を受けた患者に対し,再度レーシック手術を行ったことについて,再手術に適応が認められ,説明義務違反も認められなかったケース
東京地方裁判所 平成15年(ワ)第4569号 損害賠償請求事件
平成16年11月24日判決 控訴
【説明・問診義務,適応】
<事案の概要>
患者(昭和54年生,男性)は近視でコンタクトレンズを使用していたが,結膜炎を起こしたため眼鏡を使用していた。患者は,できれば眼鏡をかけたくないと思っていたところ,インターネットで知ったレーシック手術に関心を持ち,甲眼科医院を受診し,手術のリスク等について詳細な説明を受けた上で,平成13年2月23日,レーシック手術を受けた。手術によって患者の視力は右眼0.04が1.5弱,左眼0.04が1.5に改善したが,右眼に若干の近視(屈折度数-0.75D)がり,右眼が左眼に比べ見えにくいと感じたことから,患者は,同年4月19日,被告クリニックを受診し,被告医師の診察を受け,再度レーシック手術を受けることとした。その際,「エキシマレーザー屈折矯正手術について」と題する書面が交付され,同書面には,レーシック手術についての問題点・合併症が詳細に記載され,被告医師はそのうち,矯正視力低下,ドライアイ,サンド・オブ・サハラ及び乱視発生(不正乱視を含む)について,マーカーを引きながら患者に説明し,同書面を読んだ上で,手術までに書面下部にある手術承諾書に署名押印して提出するよう指示した。患者は,同年5月4日,手術承諾書に署名押印して被告クリニックに提出し,右眼に再度レーシック手術を受けた。再手術後,患者の右眼視力は,裸眼視力が1.0前後,矯正視力が1.2前後であったため,患者は,右眼が再手術前よりも見えにくくなったとして,同年5月31日の受診時,被告医師に対し,同年6月8日に再々手術をしてほしい旨申し入れたが,被告医師は,術後3か月程度経過しないと不完全な手術になるとしてこれを断った。患者は,本件再手術が失敗であるとして,何らかの処置をするようその後も被告医師に求めたが,被告医師は,現在の状態で手術等を行うことはできないと断ったため,同年7月5日を最後に患者は被告クリニックへ通院するのをやめた。患者は,同年9月2日,乙病院角膜移植部の医師を受診し,検査の結果,右眼の視力は,5m試視力表(万国式平仮名試視力表)を用いて患者の応答に基づいて計測する方法を採用し,裸眼視力0.3,矯正視力0.6で,調節力についても患者の応答に基づいて計測する方法を採用し,右眼は左眼と比較して概ね40ないし50%程度であった。前房,水晶体,硝子体,網膜及び視神経に異常所見はなく,右眼矯正視力低下の因子としては,角膜不正乱視が考えられたが,角膜不正乱視の増加のみで矯正視力の低下のすべてを説明できるとは断言できなかった。
患者が,被告医師に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計2125万6540円 | ||||
| 結 論 | 請求棄却 | ||||
| 争 点 | ①本件再手術の適応の有無 ②説明義務違反の有無 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
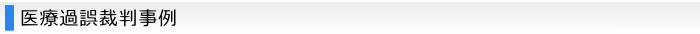
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
近視矯正手術(RK手術)において手技上の過失ないし説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第4809号 損害賠償請求事件
平成14年8月28日判決
【説明義務,問診義務,手技,因果関係】
<事案の概要>
患者ら5名(いずれも30歳代以下の男女)は,各々平成4年,被告眼科を受診し,被告眼科開設者であるA医師の執刀で近視矯正手術(RK手術)を受けたが,矯正視力が逆に悪化した上,コントラスト感度の低下,グレア等の合併症を生じた。
被告眼科は,A医師が開設者となっていたものの,実態としては,医師ではないBと同人が代表取締役を務めるC株式会社等の法人が経営主体であった。
A医師は,平成4年1月14日から被告眼科にてRK手術を行っていたが,それ以前は,Bが経営する他院において,美容外科の医師として勤務していた。
患者らが,C株式会社等に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 1億2659万5665円(5名合計) | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 5名合計1億0760万3594円) | ||||
| 争 点 | ①RK手術実施時にオプテイカルゾーンを3mm以上確保しなかった等,手術手技上の過失が認められるか。 ②RK手術実施時の説明義務違反の有無 ③手術手技上の過失と患者らの後遺障害との間の因果関係 ④説明義務違反と患者の後遺障害との間の因果関係 | ||||
| 認容額の内訳 | ①逸失利益 | 1368万5289円 | |||
| ②後遺障害慰謝料 | 330万0000円 | ||||
| ③手術費用 | 70万0000円 | ||||
| ④既払金(控除額) | -95万0000円 | ||||
| ⑤弁護士費用 | 170万0000円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
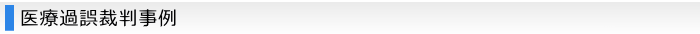
眼科における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脈絡膜新生血管に対する検査義務違反,先進的な治療法についての治療義務及び説明義務違反はいずれも認められなかったが,病名及び視力予後についての説明義務違反が認められたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第3765号 損害賠償請求事件
平成17年1月26日判決 控訴・控訴棄却
【説明・問診義務,検査,治療方法・時期,因果関係,損害論】
<事案の概要>
患者(昭和25年生,男性)は平成12年5月初めころ,甲眼科で被告病院(総合病院)を紹介され,同月22日,被告病院を受診した。担当医師は,細隙灯顕微鏡検査,倒像鏡眼底検査を実施し,近視性黄斑変性症と診断し,右眼には,中心窩の位置そのものに変性があり,左眼には,中心窩から視神経乳頭に向かう側に新生血管の血管増殖膜があることを認め,経過観察とした。担当医師は,患者に対し,患者の眼は非常に強い近視眼で,近視眼に伴った合併症が起こること,光凝固治療は視力障害を進める可能性があって実施できないこと,白内障があること,治療方針として経過観察することを説明した。このころの原告の視力は,右眼0.05〜0.06p,左眼0.04〜0.05pであった。担当医師は,中心窩移動術の内容や実施例を認識しており,同手術に関する情報を収集できる状態にあったが,中心窩移動術は実験的医療の段階にあり,合併症により医学的失明に至る危険性が高い手術であるとして否定的に評価していたため,患者の右眼に中心窩移動術の適応はないと判断し,同手術の説明はしなかった。患者は,その後,被告病院に通院し,平成13年4月5日の診察で,屈折検査,矯正視力検査,細隙灯顕微鏡検査,眼底検査,散瞳が実施されるとともに,新生血管の状況把握のため両眼に蛍光眼底造影検査が実施され,左眼に中心窩を含む広い領域の新生血管が認められた。同年7月5日の診察では,矯正視力検査,細隙灯顕微鏡検査,眼底検査,散瞳が実施され,右黄斑部に小出血が認められた。同年8月9日の診察では,患者の視力は右眼0.07pXS-14.0D,左眼0.05pXS-12.0Dに低下し,患者は,両眼がかなり霧がかかったようになってきた,朝とタで見え方が違うなどと訴えていた。同年9月13日及び同年10月4日の診療では,蛍光眼底造影検査は実施されていない。患者は,平成13年10月23日,乙眼科を受診し,両眼強度近視,黄斑変性と診断され,丙病院(大学病院)眼科を紹介された。患者は,11月2日,丙病院眼科に入院し,近視性新生血管黄斑症と診断され,同月6日,同科A医師により,患者の右眼に対し,網膜360度切開中心窩移動術が実施された。患者は,その後も丙病院を受診し,患者の視力は平成15年3月19日の測定で右眼1.5pXS+2.50D:C-0.75DAX140°に回復したが,左眼の視力は0.07pXS-13.0Dであった。その後,新生血管からの出血が見られるなどし,平成16年3月5日の右眼視力は,0.7pXS+2.00D:C-1.00DAX135°となった。
患者は,被告病院を設置する株式会社に対し,担当医師が必要な検査をせず,病状に適した治療を行わず,病状や治療方針等の説明もしなかったために視力を回復する機会を失ったなどとして,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計3727万8216円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額55万円) | ||||
| 争 点 | ①検査義務違反の有無 ②治療義務違反の有無 ③説明義務違反の有無 ④因果関係の有無 ⑤損害 | ||||
| 認容額の内訳 | ①慰謝料 | 50万円 | |||
| ②弁護士費用 | 5万円 | ||||
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




