光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
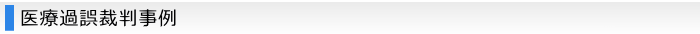
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
パーキンソン病の確定診断に至らなかった医師について,パーキンソン病であるとの説明義務が否定されたケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第8694号 損害賠償請求事件
平成17年2月23日判決 確定
【説明・問診義務】
<事案の概要>
患者(昭和11年生,男性)は,平成11年,被告病院(総合病院)において,脳梗塞,頚椎脊柱管狭窄症と診断され,頚椎椎弓拡大形成手術を受け,歩行障害は改善したが,平成12年2月22日,歩行障害等を生じ再度被告病院に入院した。
担当医師A(脳神経外科)が,脳梗塞の後遺症としてパーキンソン症状がでていると判断し,脳梗塞及び変形性頚維症の病名で,抗パーキンソン薬を投与したところ,患者の歩行障害は改善した。A医師は,入院時,病名として脳梗塞,変形性脊維症,症状として歩行障害と記載した入院診療計画書を患者に交付していた。患者は,同年9月4日,再び歩行障害が現れたため,同日,被告病院に入院した。A医師は,病名として脳梗塞疑い,症状として左半身痺れ,食思不振と記載した入院診療計画書を患者に交付した。
担当医師B(内科)は,同年11月27日,MRI上,同年9月と比べて脳萎縮が進行していること認めたが,その原因は不明であった。B医師は,患者に抗パーキンソン薬を投与し,患者とその妻に対し,脳萎縮が進行し言語障害,嚥下障害が悪化しており,言語リハビリも開始するが,将来は寝たきりになると説明した。
A医師は,患者に対し,脳梗塞のー症状としてのパーキンソン症状がでていると説明した。又,平成13年5月15日,患者が保存的治療目的で被告病院に入院した際には,A医師は,病名として脳梗塞後遺症と記載した入院診療計画書を患者に交付した。
患者は,退院したが,歩行障害等の症状で自宅療養が難しくなったことから,平成14年2月12日から28日まで,リハビリ目的で被告病院に入院した。A医師は,以前はパーキンソン病に特徴的な症状が不明確であったため,パーキンソン病と断定できず,脳梗塞が徐々に進行したことによると考えていたが,脳梗塞及びパーキンソニズムと判断するに至り,病名として脳梗塞後遺症と記載した入院診療計画書を作成し,患者に交付した。
A医師は,異動の際,患者の担当となった医師Cへ投薬加療を依頼した際,患者の病名として頚部脊柱管狭窄症,脳梗塞,脳萎縮とともにパーキンソン病を挙げた。C医師は,同年4月16日,患者を被告病院に入院させ,患者の病態を観察したが,典型的なパーキンソン病と判断できなかったため,同月23日,病名としてパーキンソン病(症候群),症状を最近流涎,血圧変動,以前より筋強剛,姿勢調節反射障害,起居動作困難,小刻み歩行と記載した入院診療計画書を患者に交付した。患者は,同年5月26日,死亡した。病理解剖の結果,死因は肺炎,脳に梗塞の所見があるとされ,黒質の淡明化,メラニン含有細胞の減少と神経細胞の脱落が見られ,レビー小体は見当たらなかったものの,パーキンソン病と診断された。
患者の家族(妻及び子)は,被告病院を開設する個人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計8430万0835円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | 説明義務違反の有無 | |||
| 判 断 | 典型的なパーキンソン所見ではなく鑑別診断出来なかったとしてもやむを得ず,又,パーキンソン病の確定診断をしていなかったのであるから医師は,患者にパーキンソン病であると説明すべき義務を負わない。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
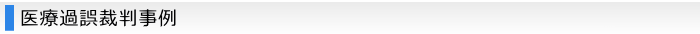
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
患者が入院中にカンジダ菌を起因菌とする敗血症を原因とする多臓器不全で死亡したことについて,担当医師に必要な検査や尿道カテーテルの管理等を怠った注意義務違反が認められず,また,入院中に徴収された差額ベッド代についての返還請求が否定されたケース
東京地方裁判所 平成14年(ワ)第17439号 損害賠償請求事件
平成16年9月30日判決 控訴・控訴棄却,上告・上告棄却
【入院管理,因果関係,その他】
<事案の概要>
患者(大正8年生,女性)は,脳梗塞の既往があり,歩行困難な状況であった。平成10年6月,患者は,経口摂取が難しくなり胃瘻が造設され,ほとんど失語状態であった。患者は,平成12年5月13日,経管栄養注入中に転倒し,同月16日に呼吸窮迫及び意識レベルの低下を起こし,被告病院神経内科外来を受診し,翌17日に入院した。患者には入院当時から不整脈や意識低下が見られ,尿道カテーテルが留置され,循環動態及び呼吸状態が悪化したため,同月19日から気管内挿管,6月2日には気管切開が行われ,昇圧剤(イノパン)の持続点滴がなされ同月20日には肺うっ血から利尿剤(ラシックス)の投与も行われた。
5月18日に採取した尿道カテーテルの培養からは菌の発育は認められなかったが,6月1日に混濁が強い膿様尿が観察され,同日の尿道カテーテルの培養からグラム陰性桿菌とカンジダ菌(真菌)が少量培養された。7月5日に採取した尿からも酵母様真菌が培養され,同月10日には尿混濁が観察され,同月11日に採取した尿の細菌検査でセラチア菌,腸球菌,酔母様真菌が培養され,同日の尿検査の結果からも,尿中に多数の真菌と白血球が含まれていることが判明した。
5月24日,胃瘻部の膿からも酵母様真菌が検出されており,5月29日に採取した喀痰及び咽頭粘液からも酵母様真菌が多数検出されており,6月9日及び7月17日に採取した鼻腔粘液から酔母様真菌が少数ながら検出されていた。
患者に対し,抗菌薬(抗生物質)であるカルベニンが6月11日から同月13日まで,及び6月30日から7月6日まで投与され,7月14日から15日まで抗菌薬アミカシンが投与された。
患者の体温は,5月中は37度前後,同月31日ころから6月10日までの間,37.0度以上になることはほとんどなかった。6月11日ころから体温が上昇したが,6月13日午後6時に36.8度に下がり,以後,同月24日まで,37.0度を超えることはなく,同月30日までは概ね37度前後で,7月2日から同月7日まではほぼ37.0度以下,7月8日から同月12日まで37度前半,同月13日から同月16日まで36度後半で,同月17日以降,37度前後で推移した。血中の白血球数及びCRP値は5月下旬以降基準値を上回っていた。
患者は,7月24日,家族の希望で退院し,IVHカテーテル,胃瘻カテーテル,尿道カテーテル,人工呼吸器を装着した状態で自宅療養をしていたが,同月30日に高熱を出し,往診した在宅医療を担当する医師が,被告病院に患者の受入れを打診したが,個室がないために受入れは無理である旨回答されたため,甲病院(総合病院)に入院することになった。
患者は,7月30日,甲病院に入院したがこの時点で敗血症を発症しており,同日の尿に少し混濁が見られ,翌31日に採取された留置カテーテル尿からカンジダ菌が検出され,甲病院入院時及び入院中,IVHカテーテル及び胃瘻カテーテルからもカンジダ菌が検出された。
患者は,8月15日,患者の子の強い希望により被告病院に転院したが,同月23日,カンジダ菌を起因菌とする敗血症を原因とする多臓器不全により死亡した。
患者の子が,被合病院を開設する法人及び担当医師に対し訴訟を提起し,両者に対し損害賠償請求とともに,患者入院中の差額ベッド代の徴収に法律上の原因がないとして,被告病院を開設する法人に対し,差額ベッド代の返還を請求した。
| 請求金額 | 法人に対し,合計4181万8877円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①カンジダ菌の感染経路・カンジダ症の発症時期 ②培養検査・カンジダ菌対策を怠った注意義務違反の有無 ③不適切な尿道カテーテルの使用・残置を行った注意義務違反の有無 ④緊急入院の拒絶についての注意義務違反の有無 ⑤甲病院に対する引継きを遅延させた注意義務違反の有無 ⑥差額ベッド代の徴収に法律上の原因があるか否か | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
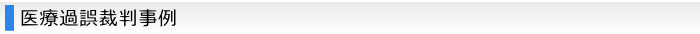
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脳梗塞で死亡した患者について,適切な治療を怠った注意義務違反,経過観察義務違反がいずれも認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第7号 損害賠償請求事件
平成16年4月28日判決 控訴,控訴棄却
【入院管理,治療方法・時期,因果関係】
<事案の概要>
患者(昭和16年生,男性)は,平成12年3月16日,被告病院を受診し,同日入院した。同月19日午後10時10分ころ,患者は,点滴を自己抜去するなど不穏状態となり,当直のC医師の判断で,翌20日午前9時30分ころまで,点滴ルートを抜いたまま経過観察とされた。患者は,同月21日午前O時10分ころにも,点滴を自己抜去し,同日午前10時ころまでの間,点滴ルートを抜いたまま経過観察とされた。その結果,3月19日午後10時10分ごろから翌20日午前9時30分ころまでの約11時間及び3月21日午前O時10分ころから同日午前10時ころまでの約10時間,へパリンの持続点滴が中断されることとなった。
B医師及びA医師は,3月21日,点滴ルートが患者に夜間せん妄を招来するため,へパリンの持続点滴投与は困難であると判断し,早期に経口剤であるワーファリンに切り替えることとし,同月22日朝食時にワーファリン10mg錠を1錠投与し,ヘパリンの持続点滴投与との併用投与をしたが,同日夕食時に患者のせん妄が増悪したため,ワーファリン単独投与に切り替える間にへパリンの持続点滴投与を実施できないと判断し,抗凝固療法から抗血小板療法であるパナルジンの投与に変更するとととし,同日午後6時ころへパリンの持続点滴投与を中止した。患者は3月31日,脳梗塞により死亡した。
患者の家族は,患者が死亡したのは,被告病院において,抗血栓療法を実施しなかったこと,3月23日午前3時の時点では,脳梗塞の増悪ないし再発による舌根沈下からいびき様呼吸や無呼吸が起こっている可能性を疑い,緊急に血栓溶解療法,抗血栓療法等の強力な治療を開始するとともに,脳に低酸素状態を生じないよう,気道確保等の処置をとるべきであったにもかかわらず,経過観察義務を怠り,同日午前8時まで脳梗塞の増悪ないし再発に気付かず,治療をしなかったことによるとして,被告病院を開設する独立行政法人に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計5620万9339円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①十分な抗血栓療法を実施しなかった注意義務違反があったか ②経過観察義務違反の有無 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
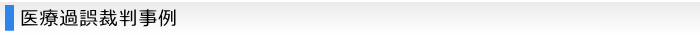
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
高齢の患者に対する経管栄養管理方法についての過失が認められなかったケース
大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第13040号 損害賠償請求事件
平成15年10月29日判決
【検査,入院管理】
<事案の概要>
患者(大正3年生,女性)は,平成14年1月17日ころから,全身状態が悪化し,同月24日夕方,意識レベルが低下したため,被告病院(総合病院)に搬送され入院となった。患者の意識レベル低下原因は明らかではなかったが,脳波検査でてんかんも疑われたことから,被告病院神経内科の医師が担当となった。
担当医師は,当初,中心静脈栄養によって患者の栄養管理をしていたが,同年2月中旬ころ,39度を超える発熱があり,血液培養検査でメチシリン耐性表皮ブドウ球菌(MRSE)が検出されたことから,中心静脈カテーテルからMRSEに感染している可能性が高いと判断し,同月21日,中心静脈カテーテルを抜去した。
担当医師は,患者の栄養状態を改善する必要を考えていたが,嚥下テストの結果,経口投与による栄養管理は困難な状態であったことから,中心静脈栄養に代わる栄養管理方法として,経鼻チューブを留置して流動食を投与する経管栄養を行うこととした。
このころ患者の意識レベルは,JCSⅠ群とⅡ群の間で変動していた。担当医師は,同月25日から27日までの間,経鼻カテーテルによって1日750mlの流動食を3回に分け,1回当たり250m1を2時間かけて投与したが,3日間で発熱等の全身状態の悪化はなく,むせや流動食の嘔吐なども認められなかったことから,同月28日,流動食の投与量を1日当たり1500mlとし,これを3回に分け,1回当たり500m1を2時聞かけて投与することとした。
ところが,患者が,昼間の流動食投与後に多量の流動食を嘔吐し,夕方の流動食投与時にも多量に嘔吐したことから,この日の流動食投与は中止された。
担当医師は,同年3月1日,誤嚥性肺炎を発症する可能性があることを念頭に置き,患者に抗生物質を投与した。同月3日朝方,患者の呼吸状態が悪化したため,当直医であったA医師が,経鼻カニューレによる酸素投与,エアウェイの挿入を行った。呼吸状態はいったん改善したものの,再び悪化が認められたことから,同日夕方,担当医師が胸部レントゲン検査を行ったところ,誤嚥性肺炎と診断された。担当医師は,同月6日,培養検査にて,MRSEとエンテロコッカスが検出されたことを受け,抗生物質をパンコマイシン及びミノマイシンへと変更した。
患者の誤嚥性肺炎は,次第に改善し,同月18日には胸部レントゲン検査上,肺の透過性も改善したが,同月21日には微熱が認められ,同月25日には,培養検査でメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が検出されたため,担当医師は,パンコマイシンを投与しつつ経過観察をしていたが,微熱,肺雑音などの症状が続き,同月28日には,胸部レントゲン検査上,左肺野の透過性低下が認められ,MRSAを原因菌とした誤嚥性肺炎と診断された。
患者に対し,抗生物質の継続投与等が行われたが,患者の肺炎は次第に悪化し,同年4月6日死亡した。
患者の家族(次女)が,被告病院を開設する地方公共団体に対し,損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 4130万9367円 | |||
| 結 論 | 請求棄却 | |||
| 争 点 | ①栄養管理方法として経鼻チューブによる流動食投与を選択したことの適否,及び,流動食の量を平成14年2月28日に従来の2倍にしたことの適否 ②胸部レントゲン検査を誤嚥直後に行うべきであったか,平成14年3月2日深夜の時点で,診察・胸部レントゲン検査によって肺の異常の有無を確認すべきであったか。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
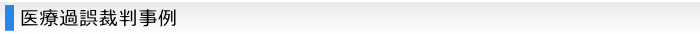
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
脳梗塞を発症して入院していた患者が,肺塞栓も発症して死亡したことについて,被告病院担当医師のへパリン投与が遅れた過失を否定したケース
東京地方裁判所
平成13年(ワ)第27368号 債務不存在確認議求事件(本訴)
平成14年(ワ)第23209号 反訴請求事件
平成15年4月24日判決
【治療方法・時期】
<事案の概要>
患者(大正14年生,男性)は,平成13年1月20日,被告病院(大学病院)神経内科に,脳梗塞のため入院し,パナルジンの投与等による治療を受けていた。
患者は,同年2月7日午前9時前ころまで話をすることができていたが,翌8日午前6時15分,呼吸困難が生じている状態で発見され,同7時30分ころ,患者に対し,ヘパリン投与が開始されたが,以後,患者はしゃべることができるまで回復することなく,同年3月24日に死亡した。
本訴において,被告病院を開設する法人は,患者の妻(相続人)に対し,損害賠償債務を負っていないと主張して債務不存在確認請求訴訟を提起し,反訴において,患者の妻が,被告病院を開設する法人に対し,ヘパリンを早期に投与すべきであったと主張して損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 3445万7482円(反訴請求額) | |||
| 結 論 | 本訴請求認容,反訴請求棄却 | |||
| 主な争点 | 担当医師(神経内科医)は,遅くとも平成13年2月8日午前8時30分までにヘパリンを投与すべきであったか否か。 | |||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
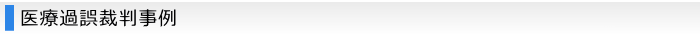
神経内科における過去の医療事故・医療過誤(医療ミス)の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。
未決勾留中に脳梗塞を発症した患者の治療につき,国に転医義務違反があり,期待権を侵害したとして,患者の損害賠償請求が一部認容されたケース
東京地方裁判所 平成13年(ワ)第22501号 損害賠償請求事件
平成16年1月22日判決
【説明・問診義務,適応,転医義務,損害論,その他】
<事案の概要>
患者(昭和24年生,男性)は,東京拘置所に未決勾留中の平成13年4月1日午前7時30分ころ脳梗塞を起こして布団の上に半身を起こしているところを発見された。
同日午前7時50分ころ,東京拘置所職員である准看護師が,患者の独房に赴き,診察したところ,その症状から脳内出血等も考えられたため患者を直ちにストレッチャーで医務部へ搬送した。患者は,同日午前8時O分ころ,東京拘置所医務部外科医Aの診察を受け,脳内出血又は脳梗塞の疑いがあったため,午前8時10分ころ,同拘置所のICU(医師や看護師が常時勤務するなどの要件を満たしていない)に収容された。A医師は,救命措置を行い,同日午前8時30分ころ,中心静脈栄養(IVH)を施行した。
東京拘置所精神科医Bは,同日午前8時30分ころ,A医師から引継を受けて患者を診察したが,「問いかけに答えず。痛み刺激で手足を動かす。右半身麻揮。発語不能。瞳孔は正円。両眼の対光反射は迅速。」という状態であった。
B医師は,患者の症状から,脳内出血又は脳梗塞のいずれかと考え,午前10時7分,診断のため患者の頭部CT検査を実施した(「第1回CT」)。同CTの画像は,患者が動いたため,アーチファクトが写るなど画質は悪かったが,低吸収域が写っており,B医師は,東京拘置所医務部放射線技師Cに登庁を依頼した。B医師は,准看護師に対し,呼吸,心拍,血圧に注意して患者を観察するように指示し,第l回CTの画像に高吸収域がなかったことから,患者が脳梗塞であると判断し,グリセオールの投与を開始するように指示をした。
同日午後0時19分ころ,C技師により頭部CT撮影が行われ,B医師は,その画像所見でも低吸収域が認められたことから,脳梗塞の可能性が高いとの判断を確認した。
それ以後,B医師や准看護師が患者を頻繁に診ることはなく,同日午後11時30分ころ,東京拘置所医務部職員が事務室内のモニターの電源を切り,同時点以後翌2日朝まで,准看護師や医師による巡回はなくなった。
医務部長であるD医師は,4月2日午前7時50分ころに患者を診察し,同日午前9時27分ころ,頭部CT撮影を行ったところ,左,中大脳動脈,後大脳動脈に広範な脳梗塞があり,一部出血性梗塞となっているなどの結果が得られたため,東京拘置所で保存的治療を継続することは不適当であると判断した。
D医師は,同日午前11時5分ころ,患者を重症指定とし,11時55分ころ気管切開を終了した。同日午後O時23分ころ,看守長が患者の父に対し,電話で,患者の状態について連絡した。D医師は,同日午後O時ころ,甲病院に対して患者の受入の可否を照会したが同日午後2時ころに拒否する旨の回答があり,すぐ乙病院に連絡したが拒否された。そこで,D医師は,丙病院(大学病院)に連絡をしたところ,受入が可能との回答があったので,同病院へ転医させることとし,同日午後3時20分ころ救急車で出発し,3時41分に丙病院に到着した。到着時点での患者の状態は,意識レベルJCS-100(GCS-E4VTM5)で,同日午後4時30分の頭部CT上,左中大脳動脈領域に広範な脳浮腫が出現し,左半球は脳溝は狭小化し,脳室は拡大するなど増悪傾向にあった。付添った刑事弁護人等に対して病状説明がされ,患者に対し,同日午後10時15分ころから前側頭部の緊急開頭減圧手術が行われたが,失語,失読,失書,右半身完全運動麻痺等の後遺障害が生じた。
患者が,患者には血栓溶解療法の適応があった可能性があり,東京拘置所の担当医師らは,4月1日午前8時ころ,患者が脳卒中であるとの疑いをもった後,速やかに専門病院へ転医させるべきであり,仮に血栓溶解療法の適応の可能性がなかったとしても,患者に適切な治療を受ける機会を与えるために,速やかに専門病院へ転医させるべきであったのに,これを怠ったと主張して,期待権が侵害されたことによる慰謝料の支払を,患者の父が説明義務違反に基づく慰謝料の支払を,国に対して求める損害賠償請求訴訟を提起した。
| 請求金額 | 合計 3750万円 | ||||
| 結 論 | 一部認容(認容額 120万円) | ||||
| 争 点 | ①血栓溶解療法の適応の可能性の有無 ②転医義務違反の有無 ③未決勾留中の者が最高水準の医療を受けることの期待権の有無 ④本件における期待権侵害の有無及び損害額 ⑤患者の父に対する説明義務違反の有無 | ||||
| 認容額の内訳 | 患者本人分 | ①慰謝料 | 100万円 | ||
| ②弁護士費用相当損害額 | 20万円 | ||||



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です。
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




