光樹(こうき)法律会計事務所 医療事故・医療過誤の法律相談 全 国 対 応 電話相談可
お問合せ |
|---|
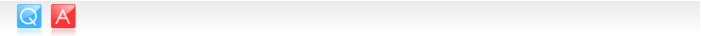
医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q21. 証拠保全はどの弁護士に頼んでも同じですか?
A21. 医療過誤、医療事故事件を専門とする弁護士に依頼しましょう。
医療過誤、医療事故事件の経験がない弁護士が証拠保全のみ受任することがありますが、経験の浅い弁護士に依頼すると以下のように、いろいろな不都合が生じます。
証拠保全には、その症例ごとにポイントがあります。例えば、手術中の事故が問題になっている場合には麻酔記録、手術記録、術中の動画、看護記録等、術後管理が問題になっている場合は、バイタルの記録や検査データ、感染症治療の適否が問題となっている場合は、培養検査の結果、血液・尿検査結果等を証拠保全で入手する必要があります。証拠保全に入ると、医療機関側が患者の診療録等を持ってきますが、必要な資料が抜けていることが少なくありません。弁護士が、医療従事者に、動画はないか、画像所見はないかなど問いかけたところ、後から後から大事な資料が出てきたということもありました。医学的知識や経験の乏しい弁護士が、証拠保全をすると、問題点を認識していないため、大切な証拠を入手できない場合がありますのでご注意ください。
証拠保全に入ると、本来あるべき記録がないことがあります。このような時、裁判所に申立てて、当該記録がないことを「調書」に残してもらう必要があります。これによって、医療訴訟になったとき、あるべき記録がないという証拠を作ることができるのです。このような機転は医療過誤専門弁護士のなせる技です。
前医・後医がある場合、相手方医療機関に証拠保全をした後、前医・後医にカルテの自己開示請求をする必要があります。この順番を間違えると、前医または後医から相手方医療機関にカルテ開示請求があったことが伝わり、証拠保全前にカルテ等が改ざん・隠匿される危険があります。医療過誤・医療事故事件の経験がない弁護士ですと、不注意から相手方医療機関にカルテ等の改ざん・隠匿を許す結果になりかねません。
医療事故・医療過誤(医療ミス)について法律相談をご希望の場合には,『医療事故調査カード』をダウンロードし,必要事項をご記入の上,当事務所宛にご郵送ください 担当弁護士が内容を拝見した後,ご相談日をご連絡いたします 電話相談も可能です
※ 歯科・精神科・美容のご相談は受け付けておりません



| 当事務所の業務内容やご相談方法。弁護士費用などのご案内です
| お問合せ時によくある質問をQ&A形式でご紹介します。 | 過去の医療過誤裁判事例のご紹介。 |
光樹(こうき)法律会計事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号 三菱ビル9階 969区
※丸ビルの隣、KITTEの向かい
TEL:03-3212-5747(受付:平日10:30~17:00)
F A X :03-3212-5740




